エリオ・グレイシーは43歳のときに弟子のヴァウデマー・サンターナと対戦し、3時間以上の戦った末、KO負け。
この試合を最後に引退した。
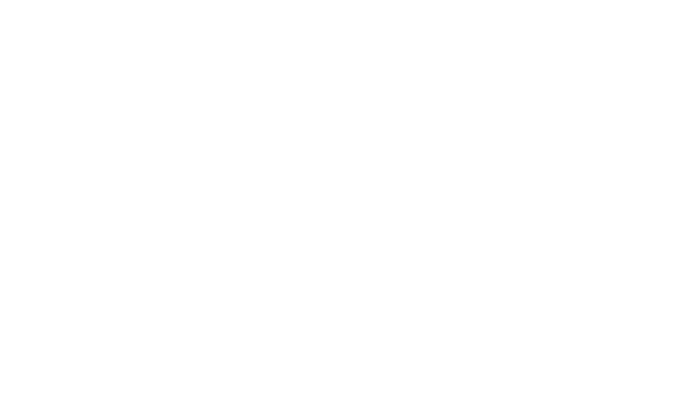
ヒクソン・グレイシーが生まれたとき、父のエリオ・グレイシーは45歳だった。
長男:ホリオン・グレイシー。
次男:ヘウソン・グレイシー。
三男:ヒクソン・グレイシー。
四男:ホウケル・グレイシー。
五男:ホイラー・グレイシー。
六男:ホイス・グレイシー。
七男:ホビン・グレイシー。
エリオの指導の下で兄弟は稽古をした。
エリオ・グレイシーは、まずは負けないこと、決してあきらめないこと、臨機応変に動くことを強調した。
文字通り、生き残ることが命題だった。
グレイシー一族は、柔術同士の戦いだけではなく、道場破りにきた様々な格闘技の猛者とも対戦した。
あくまで本来何が起こるかわからない実戦の中で技を磨き、その根源的な格闘技の精神を大事にした。
ヒクソン・グレイシー
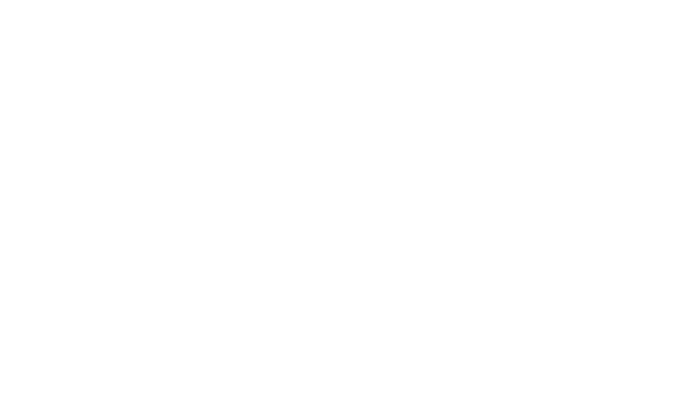
ヒクソン・グレイシーはほとんどの時間をリオデジャネイロの街か海辺か道場で過ごした。
家がコパカバーナビーチの前にあったので、1人でよく家の前や海岸で遊んでいた。
学校の勉強はほとんどしなかった。
エリオ・グレイシーも息子の学校の成績に関心がなかった。
ヒクソン・グレイシーは6歳から柔術の大会に出始めた。
そして初めて優勝して以来、トップでなければ満足できなくなってしまう。
彼は自分にとって何が重要だと思うかを問われて「自分自身」と答えた人以外、みんな間違っているという。
ストリートファイト
リオの街では年上の不良少年グループとも付き合った。
ワイルドな街で男らしさを見せつけ勇気を証明するために危険なことも行った。
柔術や格闘技の試合より、ストリートファイトの数のほうが多いともいわれている。
ブラジルの柔術少年
道場では父親や兄が教えているのをみて、また練習や試合をする人をみて育った。
一番重要な場所は道場のマットの上だった。
そこでは年齢や職業、性別、肌の色などどうでもよくなり、人は本当の自分をさらけ出した。
体が大きく強そうにみえる男がプレシャーに耐えきれず臆病者のようにオドオドしたり、ガリガリに痩せているが粘り強い男もいた。
負けて言い訳を始める人もいれば、結果を認め受け入れる人もいた。
自分より弱い相手には徹底的に攻撃するが、強い相手にはダメージを受け戦えないふりをする人もいた。
プレッシャーがかかっても立派にやれる強い人間もいた。
いろいろな人をみてヒクソン・グレイシーは、日本の武士道、サムライが進むべき1本しかない細い道を理解した。
潔さ、勇敢、善良・・
そんな紳士でありながら強い男が理想だった。
また相手を尊敬すること、謙虚であること、つまり自分が人より優れているとは考えないようにすることも重要なことだった。
自信がありすぎると周りがみえなくなってしまう。
戦う上で「自分の方が有利」と考えた時点で、相手の特徴を理解することができなくなってしまう。
ヒクソン・グレイシーはそんなことにならないように相手を尊敬し感覚を研ぎ澄ました。
決して人を見下したり批判ばかりしてはいけないと思った。
13歳のとき、大人と稽古していていいポジションを取られ首を押さえられ、息ができなくなり命の危険を感じ、怖くなりタップ(まいった)してしまった。
その後、ヒクソン・グレイシーは猛烈に自分に腹が立ち泣いてしまった。
やがて冷静に反省した結果、
なぜ不利な体勢になったのか?
なぜパニックに陥ったのか?
この2つを敗因とした。
以後、同じようなことが起きて息ができなくなっても、
「とにかく息をしながら、このポジションさえなんとかすればいいんだ。
挽回できる。
この体勢から抜け出すぞ」
と考えあきらめようとは思わなくなった。
そんなことを繰り返すうちに、恐怖とは自分の中にあることだということ、そして恐怖を克服するためには問題を理解することであると悟った。
武士道
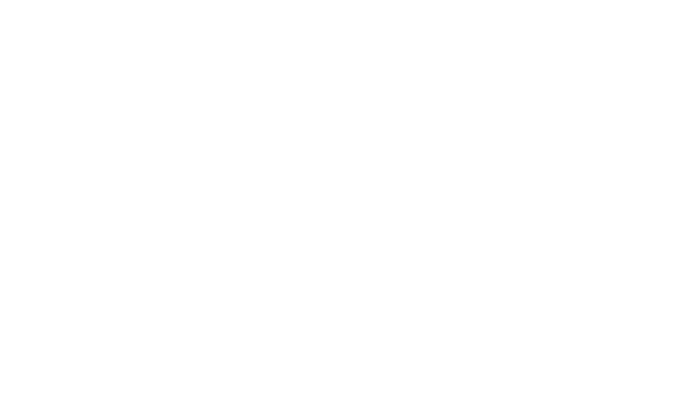
ヒクソン・グレイシーが読んだ「Shogun(将軍)」James Clavell著
Shōgun (novel) - Wikipedia
ヒクソン・グレイシーは、日本の武士道を愛した。
サムライの信じるもののためなら喜んで死んでやろうとする生き方や、彼らが信じ守った信念に感銘を受けた。
彼らは心身の鍛錬によって優れた能力を身につけ、かつ正しく生きようとした誇り高き人に思えた。
しかしヒクソン・グレイシーは、サムライの「主君への奉仕」だけは立派だとは思ったが好きになれなかった。
ヒクソン・グレイシーにとって、自分を1番大切にすること、自分らしさ、自分の幸せを見つけることは生きることの基本だった。
主君のために自分を殺せる人間はある意味で完璧な戦士かもしれないが、ある意味、人間として弱いと思った。
たしかに仕事や責任のために自分を犠牲にするのは価値あることかもしれないが、自分次第で何だってできたり、どんな人生を歩んでも構わないということのほうが素晴らしいのかもしれない。







