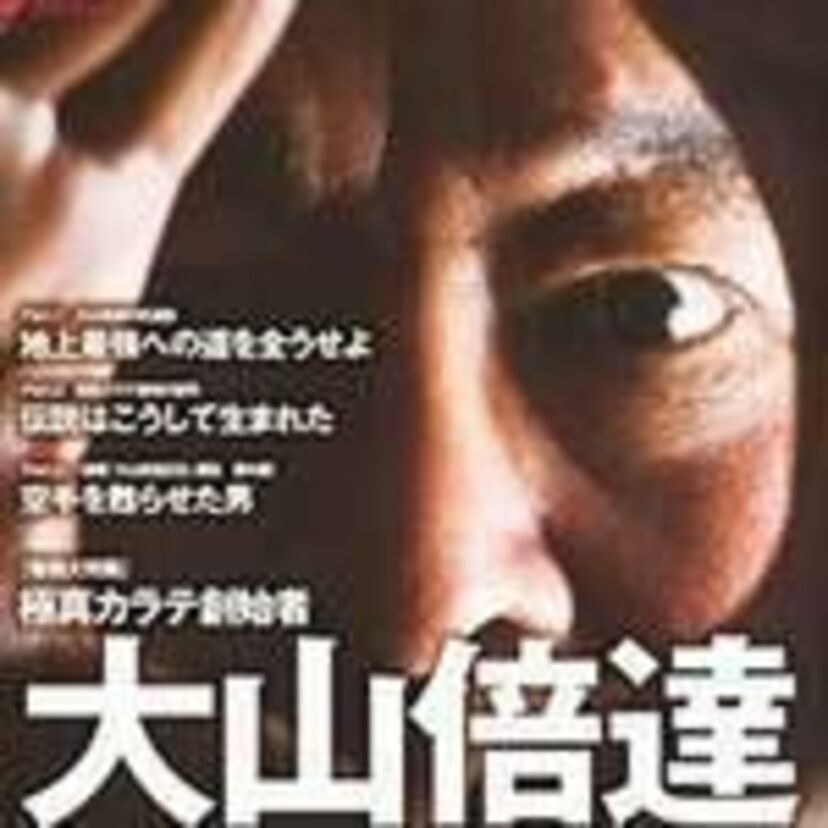1993年4月30日、代々木第一体育館で「K-1」という新しい格闘技イベントが誕生した。
打撃系格闘技世界最強の男はいったい誰なのか?
「空手」「キックボクシング」「拳法」「カンフー」など、代表的な立ち技・打撃系格闘技の頭文字「K」
その中の世界最強、真のNo.1を決めんとする「K-1 GRAND PRIX′93 10万ドル争奪格闘技世界最強トーナメント」
競技、団体、階級の垣根を飛び越え世界王者同士による夢の異種格闘技ワンデイトーナメント。
8オンスグローブを着用。
3分3R(ラウンド)、あるいは3分5R。
頭突き、肘撃ち、バックハンドブロー、目付き、金的、投げ技、関節技は禁止。
その他の打撃技はすべてOKという打撃系格闘技ルール。
出場選手の中には8年間無敗の記録を持つキックの帝王:モーリス・スミスがいた。
そのモーリス・スミスの無敗神話に終止符を打ったオランダの怪童:ピーター・アーツもいたし、
この2人を破ったことがあるアーネスト・ホーストもいた。
佐竹雅昭は、UKFアメリカヘビー級王者、11戦11勝11KOのトド"ハリウッド"ヘイズを2R 0:45、右ローキックでKO。
ブランコ・シカティックの石の拳は、タイの英雄、最強のムエタイ戦士:チャンプア・ゲッソンリットをロープまでフッ飛ばした。
決勝戦ではブランコ・シカティックのパンチがアーネスト・ホーストのテンプルを打ち抜き失神KO勝ち。
波乱万丈の展開に加え、全7試合中6試合がKO決着。
衝撃的なK-1誕生の瞬間だった。
この後、「K-1」は、空前の格闘技ブームを引き起こしていく。
大手スポンサーがつき、東京だけでなく名古屋、大阪、福岡、やがて海外でもイベントを開催。
会場は多数の芸能人が訪れ、チケットのとれないモンスターイベントとなっていく。
1993年7月、アンディ・フグの移籍により大山倍達に絶縁されて1年、正道会館の角田信朗は館長である石井和義から電話をもらった。
「お前、スーツ持ってるか?」
「押忍」
「じゃあ今からすぐスーツに着替えて東京行きの新幹線に乗って、乗ったら電話してこい」
「押忍?」
「プーップーップーッ」
角田信朗はわけもわからないまま着替えて新幹線に乗った。
「押忍。
いま新幹線に乗りました。」
「あっそ、ご苦労さん」
「自分はどうさせていただいたらいいのでしょうか?」
「ホテルニューオータニでね、梶原一騎先生の7回忌の記念式典やってるんだけど、角田、俺の代わりに出席してきてよ」
「オッ、押忍!!??」
「極真の人たちもみんな来てるらしいよ」
「押忍!!!
そんな大事な席に自分のような者では館長の代わりはつとまりません!!」
「なにいってんの。
みんなお前が来るの待っとるで」
「押忍!!
しかし館長!!
極真会館さんからは絶縁状が届いている状態なのに、そんなところへ自分が行って大丈夫なんでしょうか!?」
「プーップーップーッ」
悲惨だった。
東京駅からタクシーでホテルニューオータニへ。
会場に着いた角田信朗はドアを少しだけ開け恐る恐る中を覗いてみた。
すぐ目の前に黄色のブレザーを着た50名ほどの屈強な男がビッシリと並んでいた。
しかも正面で大山倍達が挨拶をしている最中だった。
(ヤバい!!)
角田信朗は静かにドアを閉めた。
(こんな敵陣に絶縁状を回されている組織の幹部がノコノコ入っていったらどうなるのだろう?)
思案に暮れ、もう1度覗こうとしたとき、中からドアが開き、梶原一騎の弟:真樹日佐夫が出てきた。
「いやあ、角田君来てくれたのか」
その声に会場の中の全員が角田信朗をみた。
「ちょうどいい、大山総裁に紹介するよ」
「押忍。
いえでも・・・」
真樹日佐夫にズズッズズッと押されながら角田信朗は大山倍達の前まで来た。
「いやあ総裁。
紹介します。
正道会館の角田君」
「オ、押忍。
せ、正道会館の、か、角田であります。
ごぶたさ、いやご無沙汰しております」
角田信朗は極真空手の全国ウエイト制大会で4位に入ったことがあり、そのとき大山倍達にいわれた。
「君ぃ、世界大会も出てこい!」
(世界大会出場はケガのため実現しなかった)
大山倍達は右手で握手しながら左手で角田信朗の頬をパチパチ叩いた。
「いやあ!
もう1度会おう!」
(もう1度会おうか。
今会ってるのに)
角田信朗は心の中でツッコんだ。

1994年3月15日、若獅子寮の第22期生卒寮式が行われた。
卒寮生の中には、デンマークから空手修業のために17歳で単身来日したニコラス・ぺタスがいた。
大山倍達は祝辞を行ったが、公に姿を現したのは、これが最後となった。
ニコラス・ぺタスはK-1のリングにも上がり「極真会館最後の内弟子」「 青い目のサムライ」と呼ばれた。
3月17日、大山倍達が聖路加国際病院に緊急入院。
3月22日、病院側の制止を振り切り退院し総本部内の自室で静養。
4月15日の若獅子寮の第25期生入寮式には出られず、この日の夜、再び聖路加国際病院に入院。
そのとき大山倍達はいった。
「一部の側近と松井章圭以外は、家族といえども見舞うことは許さない」
急遽、大山倍達の名代としてネパールで開催される第6回アジア大会に行くことになった松井章圭は、その報告を兼ねてお見舞いに訪れた。
そして別れ際
「元気でね」
そう大山倍達にいわれ胸騒ぎがした。
大山倍達は肺ガンだった。
松井章圭はそれを知っていたが、大山倍達には最後まで告知されなかった。
そしてベッドでの排泄を拒否し、内弟子の肩につかまりながらトイレに通った。
担当医は大山倍達の寿命を
「あとわずか」
と診ていた。
大山倍達の病床には、妻の大山智弥子、身の回りの世話をする内弟子を除いて5人の男がいた。
入院中、3人の娘(留壹琴(長女)、恵喜(次女)、喜久子(三女))は1度の見舞いに来なかった。
1 梅田嘉明
東邦大学医学部入学と同時に同大空手部に入部し、極真空手一筋の道を歩み始め、全日本大会ではドクターを務める元極真会館相談役で横浜東邦病院院長。
2 黒澤明(元黒澤組組長)
極真会館相談役。
大山倍達が義兄弟の契りを交わした柳川次郎(殺しの軍団と呼ばれた柳川組の初代組長)の舎弟。
グリコ森永事件の主犯と疑われたことのあるカリスマ大物組長。
3 大西靖人
元全日本チャンピオン、世界大会で松井章圭に敗れた後、引退し、不動産会社や警備会社を経営。
岸和田市会議員、新進党大阪府第18総支部会長、新進党大阪府連常任幹事を務めた。
4 米津等史
大西靖人の城西支部の後輩。
資生堂の社長秘書、大山倍達の私設秘書。
5 米津稜威雄
弁護士
米津等史の父親

1994年4月17日と19日、2日間かけて、大山倍達自身の意向で危急遺言
(いますぐに遺言書を作成しないと遺言者の生命が失われてしまう場合など緊急事態に使われる遺言書。
緊急時に一般の人が対応できないことや、対応方法を知っている人間がいても、妻や子供など利害関係者を除き、証人となりうる人間が3名必要なため、危急時遺言は使用事例が少ない)
が作成された。
自分の病状を知らない大山倍達に死期を悟らせないように危急遺言を選んだと5人はいう。
妻の智弥子もいたが、大山倍達は、家族に知られたくないことがあり、退院できればそれはなかったことにしたいので遺言書の作成に同席させなかった。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
遺言者大山倍達は、平成6年4月17日聖路加病院971号室において、証人米津稜威雄、同梅田嘉明、同黒澤明、同大西靖人、同米津等史立ち合いの下に、証人米津稜威雄に対し次のとおり遺言を口述し、米津稜威雄はこれを筆記した。
一 遺言者死亡のときは次の通りにすること。
1 極真会館、国際空手道連盟を一体として財団法人化を図ること。
2 梅田嘉明は、財団法人極真奨学会理事長、株式会社グレートマウンテン(新会館建設のため現会館の隣の土地を買うために設立された新会社)社長を勤めて欲しい。
3 極真会館国際空手道連盟の大山倍達の後継者を、松井章圭と定める。世界各国、日本国内の本部直轄道場責任者、各支部長、各分支部長は、これに賛同し協力すること。
4 松井章圭は、極真会館新会館建設の第2次建設委員会長として新会館を設立すること。
5 梅田嘉明は、極真会館国際空手道連盟、財団法人極真奨学会、株式会社グレートマウンテン、有限会社パワー空手等、極真空手道関連事業を監督し、松井章圭の後見役として勤めて欲しい。黒澤明は、梅田嘉明を補佐し協力して欲しい。米津稜威雄、長嶋憲一(極真会館相談役、弁護士)もこれに協力して欲しい。
6 池袋の極真会館の土地建物は、新会館の土地を含めて、極真会館国際空手道連盟に寄贈する。これらに対する出費等も同じ。これらは極真空手道のためのみに使用すること。これらの手続きは、米津稜威雄において執って欲しい。
7 妻智弥子と三女喜久子には、石神井の土地家屋を持分平等の割合で与える。
右土地家屋には建築ローンが残存しているので、これを極真側で責任をもって支払って欲しい。千葉御宿の土地、大山倍達個人の預金、現金は智弥子に与える。なお智弥子に対しては、極真側で毎月100万円またはこれに相当する金額を支払って生涯面倒をみて欲しい。
8 「パワー空手」は、極真空手道の機関紙であって欲しい。機関誌として存続する限り、三女喜久子に毎月100万円宛支払って欲しい。
二 遺言執行者を次のとおり定める。
遺言執行者 弁護士 米津稜威雄
米津稜威雄は、右筆記事項を遺言者および証人梅田嘉明、同黒澤明、同大西靖人、同米津等史に読み聞かせ、右各証人はその筆記の正確なことを承認し、次に署名押印した。
筆記者 証人 米津稜威雄
証人 梅田嘉明
証人 黒澤明
証人 大西靖人
証人 米津等史
『遺言書(追記)』
遺言者 大山倍達
一 韓国ソウル特別市在住の・・・・、・・・・、・・・・(ソウルにいる妻子、住所)には、極真側で各金1500万円を支払って欲しい。
一 北海道在住の・・・・(女性の名前)には、極真側で金1000万円を支払って欲しい。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
このように大山倍達は、後継者に松井章圭を指名した。
遺言書は全14項目。
1~5項までは、極真会館と関連組織の運営
6~12項は、家族に対するケア
13、14項には、追記という形式で北海道と韓国にいる愛人と子供に対するケア
について記されていた。

1994年4月26日8時、大山倍達が肺ガンによる呼吸不全によって、あまりに波瀾万丈だった人生を70歳で終えた。
同時刻、松井章圭は予定を早めてネパールから帰国し、日本の空港にいた。
東京の妻と3名の娘も死に目に会えなかった。
その後、棺桶に納めれた大山倍達は、聖路加病院から極真会館の2階の総本部道場に帰った。
入口には
「本日の稽古はございません」
という張り紙が張られた。
昼前、大山留壹琴(長女)の夫で関西本部長の津浦伸彦が到着し、大山倍達の義理の息子として弔問者に対応した。
12時、喪服を着た支部長たちが続々と到着。
「朝9時に電話で亡くなられたと聞きました。
もう信じられなくて、まさかという感じで・・・
すぐに飛んでいって昼の3時半に東京に着いて総裁に挨拶をしました」
(七戸康博)
「鹿児島で大会がありまして、空港に今朝の10時ごろ着いたんですけど、自宅に電話入れるように呼び出しがあって、連絡したら・・・
もうパニック状態でした。
信じられないというか。
飛行機の都合で東京に着いたのは6時10分でした」
(緑健児)
極真会館の周囲はマスコミやファンで埋め尽くされた。
13時、大山留壹琴(長女)が到着。
建物に入る前、玄関先で梅田嘉明に食ってかかった。
梅田嘉明は苦虫を噛み潰したよう顔をして相手するのを避けて人波に消えた。
その後ろでは大山智弥子未亡人が、笑顔であいさつをして回っていた。
16時、梅田嘉明、郷田勇三、盧山初雄、山田雅捻、米津等史 らが記者会見を開き、大山倍達が死亡したこと、その志を継ぐこと、遺言書の存在を発表した。
大山智弥子は、このとき遺言書があることを知った。
それまでその内容も存在も知らなかった。
「私は毎日主人の看病にいってましたが遺言書の事なんかひと言も聞いてません。
私だけが知らされていなかった事になりますよね」
遺言書には韓国と北海道に大山倍達の愛人と子供がいることが明らかになっていた。
「皆さんはその事に気遣って 私に遺言書を見せなかったとおっしゃるんですよ。
でも私が今更ヤキモチを焼くような歳ですか。
50年近く連れ添って、外に子供がいることくらい何の不思議もない人だったことは私が一番知ってますよ
19時、通夜が始まり、支部長、道場生、OB、ファン、格闘家、各界の著名人など500人が参列した。

1994年4月27日12時半、極真会館総本部で告別式が大山智弥子未亡人を喪主にして行われた。
西袋公園はファンとマスコミであふれた。
14時、三瓶啓二、松井章圭、八巻建志、数見肇ら歴代チャンピオンたちによって大山倍達の入った棺桶が霊柩車に乗せられた。
その後、遺族代表として津浦伸彦が挨拶。
そして梅田嘉明が
「生前、大山総裁は遺言状を遺されています。
そこには後継者として松井章圭君が指名されています」
と発表。
突然の発表を、松井章圭は、参列者1500名と共に直立不動で聞いた。
31歳の松井章圭を、後継者の指名したのは、いかにも大山倍達らしかった。
多くは松井章圭が2代目となることに好印象を持った。
しかし快く思わない人間もいた。
同夜、臨時全国支部長会議が行われ
「お前は本当に2代目の指名を受ける気なのか?」
郷田雄三を筆頭に多くの先輩支部長詰め寄られ、2年前に支部長になったばかりの松井章圭は、
「受けます」
と答えた。
その後、会議は紛糾し、なにも決定されないまま終わった
1994年4月28日、告別式の翌日、大山喜久子(三女)がニューヨークから帰国した。
大山恵喜(次女)もアメリカにいたが、大山倍達が死去した日(1994年4月26日)に娘:桃果林を出産したため、来日が遅れていた。

1994年5月1日、神奈川県湯河原で強化合宿が行われた。
毎年春先に行われる恒例行事で、国内だけでなく海外の支部長も参加し、世界大会や全日本大会の優勝者も同行させ、大山倍達が直接指導を行っていた。
没後間もないということで
「今年は中止すべき」
という意見もあったが、松井章圭は
「こういうときだからこそ」
と予定通り、合宿を開催した。
「いま湯河原駅に着いたから出てきてくれ」
合宿初日、三瓶啓二から電話がかかってきて松井章圭は駅前の喫茶店で会うことになった。
三瓶啓二はいった。
「松井、みんなお前じゃダメだといっている。
海外の支部長も国内の支部長もみんな、お前が後継者ということに納得していないんだよ」
「先輩、みんなというのは誰ですか?
誰と誰がどのような理由で僕ではダメだといっているんですか?
具体的な支部長の名前を教えてください。
そうでないと対応の仕様がありません」
「だから誰とかじゃなくてみんながお前ではイヤだといっているんだよ。
松井、これからは民主的に組織を運営して、すべてをガラス張りにしていかなくてはダメだ。
そういっている支部長はたくさんいる。
総裁のときのような独裁じゃ組織は発展しない。
そのためには些細なことも会議で決定する合議制を取り入れたり、館長を選挙で公平に任命する任期制を取り入れたり、みんなで話し合って決める必要があるんだ」
「先輩、僕はいつでも皆さんの話を聞きますし、納得してもらえるような説明をしますから。
だからとにかく仕事をさせてください。
僕は今も合宿のためにここに来ているんです。
支部長たちも、もう集まってるんですよ。
そういった仕事を滞りなく果たせるようにサポートしてください。
お願いします」
「松井、みんなお前のことを心配してるんだよ。
もちろん応援したいと思っている。
俺だってお前のことを考えたからこそここに来たんだ。
とにかく1度、支部長たちの話を聞いてやってくれよ」
「意見があるなら僕はいつでも皆さんの話を聞きますよ。
でも具体的に誰が何をいっているのかもわからず『みんながいっているから』という曖昧な理由だけで『わかりました、ではそうしましょう』とはいえないんですよ。
先輩、物事を進めるには手順というものがあるでしょう」
去り際、松井章圭に試合で3戦3勝の三瓶啓二はいった。
「俺はお前の味方だからな。
俺はお前を応援するから」

1994年5月10日、湯河原で三瓶啓二と松井章圭が話した9日後、郷田勇三が臨時全国支部長会議を開いた。
大山道場時代からの最古参の支部長であり人望も厚い郷田勇三のもとには、松井章圭の2代目に対して否定的な声や極真の未来を憂う声が多く届いていた。
「松井は支部長として経験も浅く年齢的にも1番若い。
末っ子がいきなりトップに立つのだから面白くない支部長が出てきても仕方ない。
でも極真は個人の感情が通用するほど小さい組織ではない」
当日、松井章圭は郷田勇三と共に極真最古参の盧山初雄と一緒に会場に向かった。
支部長会議は、会場の席は、支部長会議はキャリアの長さや実績の大きい支部長から順番で前から座るようになっていた。
松井章圭はいつものように1番後ろに、盧山初雄は上座に座った。
会議が始まり、まず郷田勇三が遺言書の内容を読み上げ、そして松井章圭2代目の賛否を問うた。
長谷川一幸(愛知県支部長)は
「私は松井君でもいいと思います。
遺言書にそう書いてあるのだし。
ただ時期尚早なのではないでしょうか?
とりあえず今回は辞退するべきだと思います。
そしていろいろと勉強した後に3代目と形で館長になったらいいのではないですか」
と発言。
長谷川一幸は、165㎝と体は小さいが第2回全日本大会で、第1回世界大会で優勝する佐藤勝昭を左上段回し蹴りで一本勝ちするなどして優勝した。
大石大吾、西田幸夫(東京城北、神奈川東支部長)も同様の意見を述べた。
大石大吾は
「あの切れ味は、誰にも真似できないよ」
と大山倍達にいわせた足技の天才で、その蹴りは
「妖刀村正」
と呼ばれた。
総本部内弟子を5年間務め、第3回全日本大会3位、第6回全日本大会で4試合連続1本勝ち、第1回世界大会4位。
西田幸夫は、第1~6回全日本大会連続出場。
郷田勇三、盧山初雄が最古参だが、長谷川一幸、大石大吾、西田幸夫はそれに次ぐ極真の重鎮だった。
まるで神話のような地獄稽古に耐え抜き、数々の武勇伝を持つ彼らは、極真を志す者にとっては生きる神様のような存在だった。
3人は、郷田雄三や盧山初雄が館長になった後、松井章圭が引き継ぐべきと主張した。
続く三好一男 (高知県支部長)は
「私は松井が後継者ということ自体おかしいと思います」
と発言。
その後は同様の意見が続いた。
「生前、松井ほど総裁の悪口をいっていたやつはいない」
「まだ若い」
「好き放題にされる」
以前と同様、会議は紛糾し始めた。
その流れを盧山初雄が止めた。
「ちょっと待て。
松井はそんな男じゃないだろう。
全日本、世界大会を含めて3連覇し100人組手も完遂したんだぞ。
空手の実績もあって頭もいい。
私は松井が悪い人間だとは思わない。
1番下の弟子が館長になるのだからおもしろくないのはわかる。
でもそれが総裁の意志なんだよ。
誠、お前も松井を頼むと総裁からいわれたんだよな?」
「押忍」
中村誠(兵庫県支部長)は大きな声で答えた。
「自分は亡くなられる数日前、総裁に呼ばれて病院に行きました。
総裁は『人間は和合だ、和合が大事だよ』とおっしゃられた後に『松井を頼む』といいました。
『君も不満はいろいろあるだろうが、その不満をいまこの場でいってほしい』と。
自分は『不満はありません』と答えました。
だから自分は松井2代目館長に異論はありません」
盧山初雄も中村誠も、入院中の大山倍達を見舞い、直接
「松井を頼む」
といわれていた。
その顔は青白く頬はこけ顔面の半分がマヒし動いていなかった。
郷田勇三、盧山初雄、中村誠らにとって、自分や支部長の個人的な感情など問題ではなかった。
遺言状もさほど重要ではない。
大事なのは「大山倍達の意志」だった。
改めて郷田勇三は前の支部長から順番に1人1人、答えを聞いていくことにした。
「遺言書に書いてあるならいいのではないでしょうか」
「自分もそう思います」
「自分も・・・」
そして三瓶啓二は
「これ以上聞いても時間の無駄じゃないですか?」
と発言。
これにより以降のの意見は省かれ、郷田勇三が
「松井2代目館長に反対の人は挙手をお願いします」
と聞いた。
すると1人も手を挙げなかった。
「館長として会議を進めなさい」
盧山初雄にいわれ松井章圭は前に出て、その後、会議を進行させていった。
そして意見を募った。
複数の支部長が、大山倍達のときのようなワンマンではなく民主的な組織運営を行うことを望んだ。
そして以下の2点が決められた。
・2代目以降の館長に、「総裁」という呼称は使用しない。
・郷田勇三と盧山初雄が館長を補佐する「最高顧問」となる。

1994年5月11日、会議翌日、松井章圭は東京都北区田端の郷田勇三の道場を訪ねた。
「師範、昨日はどうもありがとうございました。
館長になったからには私心を捨てて頑張ります。
よろしくお願いします」
「引き受けた以上、船はもう岸を離れたんだ。
何があっても絶対に戻るな。
とにかく前に進め。
いいな」
「師範も一緒に船に乗ってくれますか?」
「俺は船酔いするからいやだな」
「師範、お願いします。
一緒に乗ってください」
「心配するな。
お前が頑張り続ける限り乗り続けるよ。
だから絶対の弱気になって引き返すなよ」
その後、2人は極真会館総本部の4階の大山倍達の家を訪ねた。
大山智弥子未と喜久子(三女)がいた。
「事務局長、松井が2代目館長になりましたのでどうぞよろしくお願いいたします」
郷田勇三が報告すると2人は笑顔で答えた。
「あら、そう。
私も総裁からそう聞いていたわ」
(大山智弥子)
「2代目を継ぐのは松井さんしかいないわよね。
松井さん、よろしくお願いします。
頑張ってね」
(大山喜久子)
大山智弥子は極真会館事務局長だった。
よく4階から3回の事務所に下りていって事務局で職員と雑談を交わしたが、仕事も空手もやったことはなかった。
「本部道場ができた頃、ヤクザみたいな人がいっぱい出入りしてたんですよ。
母はこれではいけないというんで自分1人でそういう人たちをほうき片手にみんな追い出しちゃったそうです」
(大山喜久子(三女))
1994年5月18日、松井章圭は、自分の個人名義で「極真会館」「極真空手」の商標申請を行った。
商標権とは、商品やサービスの目印(商標)を独占できる権利。
仕事、ビジネスは、必ず何かしらの商品やサービスを売っている。
客は、たくさんある商品、サービスから選んで買う。
仕事、ビジネスをする側は、客に自分の商品、サービスを選び出し買ってもらわなければならない。
商標は、客が商品、サービスを選ぶための「目印」で、その「目印」が「商標」である。
特許庁に出願して登録を認められれば商標権を主張できる。
商標は、早い者勝ちで、先に出願されたものが優先して登録され、同一の商標、類似していると思われる商標は、特許庁に拒絶される。
たとえ昔から自社で使っているネーミングやロゴでも、他者や他社が出願し登録してしまうと商標権を侵害している側になってしまう。

郷田勇三と松井章圭が大山家を訪ねた10日後、大山智弥子から全国の支部長に手紙が届いた。
遺言書のコピーを手に入れた大山智弥子は、作成されたとき、まだ元気だった大山倍達の直筆の署名がないことやその内容に不審を抱いたという。
「この遺言書と称する書類は大山倍達の遺志に基づくものではないと判断するに至り、法的な相続人でもあり、かつ大山倍達と50年近く連れ添った私が、自分、家族、極真会館、そして何よりも大山倍達という名を守るために敢えてこうして人前に出ることを決意するに至りました。
大山倍達亡き今、大山倍達との契約は白紙し、今後、極真会館、極真空手、カラテ極真という名称や極真のマークなどの使用に関しましては相続人の私が管理し新たに再契約を行いたいと考えております。
つきましては平成6年6月1日午後1時30分から総本部総裁室にて今後の問題を話し合いたいと思いますので、お忙しい中恐縮ですがご出席願います。
極真会館にとって重大な問題ですので是非ご出席ください。
ご出席いただけない場合は極真会館を離れていくものと考えさせていただきます」
郷田勇三はすぐに支部長1人1人に連絡を入れた。
「事務長の呼びかけに応じる必要はない。
応えなくても「極真」の名称利用は保証するし支部長の立場を失うこともない」
遺言書に従い
「遺族は大切にしなければならないが組織運営に一切参加させない」
と決めていた。
しかし高木薫(北海道支部長)、小野寺勝美(岩手県支部長)、安済友吉(福島県南支部長)らは、遺族を組織のトップに置こうと考えていた。
大山智弥子が全国の支部長たちに手紙を送った背景には、高木薫の助言があった。
高木薫は、東京本部総裁秘書室室長の肩書をはく奪された後も、変わらず大山倍達に尽し続けた。
松井章圭を館長とする新体制には反対だった。
それは三瓶啓二らも同様だったが、一本気に大山倍達や大山智弥子を敬う高木薫は、合議制や民主的な組織運営を推す彼らとは違っていた。
また高木薫にとって極真は大山倍達1人で、支部長間で広くつき合ったり協調しようとせず、多数派の三瓶啓二らと違い一匹狼的なところがあった。
1994年5月27日、
「総裁が亡くなってからいろいろと大変だったと思います。
別荘で療養なされたらいかがですか?」
と梅田嘉明にいわれ
「そうね。
そうするわ」
大山智弥子は、千葉県一宮町の別荘へ向かった。
松井章圭らには6月1日の大山智弥子の招集を穏便に回避したいと意図があったと思われる。
6月1日、大山智弥子が全国に向けて招集をかけた当日、郷田勇三の意を受け、多くの支部長は総本部に来なかった。
また再契約を求めた差出人も東京にいなかった。
6月10日、大山智弥子は東京に戻った。
高木薫や大山倍達の娘は、
「松井たちに幽閉された」
「招集を阻止するために拉致した」
と非難した。
しかし大山智弥子は自分の意思で車に乗っていた。

6月17~19日、大阪府立体育館で第11回全日本ウエイト制大会が開かれた。
リアルな最強を追求する極真空手の試合は、元来、体重無差別制で行われてきたが、ある時期から体重別の大会も行われるようになった。
毎年、無差別制の全日本大会は秋の東京で、全日本ウエイト制大会は夏に大阪で行われる。
5月10日の会議で2代目館長となった松井章圭が会場に到着しても席を立って礼をしない支部長も多くいた。
「おうっ」
三好一男(高知県支部長)は椅子に座ったまま軽く手を挙げた。
「師範、自分はどこに座ったらいいですか?」
会場には松井章圭の席だけなく、盧山初雄最高顧問の指示を受けてやっと用意された。
「大山総裁が亡くなって最初に開催した全日本ウエイト制大会で、彼らにどれだけ新館長を立てようと気持ちがあったのか。
館長が会場入りしても挨拶もせず顔を背けて冷ややかな態度をとっていました。
会場内には館長が座る席も用意されていなかったのです。
彼らは最初から若い館長を支えていくという努力すらしなかったのです。
というよりそもそも支えるつもりがなかったのです」
(盧山初雄)
大会冒頭、松井章圭が大山倍達の遺影を持って入場するという企画があったが、直前になって津浦伸彦が
「自分が持つ」
といい出した。
津浦伸彦は、関西本部長であり、この大会の実行委員長であり、大山倍達の長女:留壹琴の夫である自分が遺族代表として遺影を持つのが当然と主張。
「どうしても譲れというなら私はこの大会に協力できません」
松井章圭に対して子供のような態度をとる支部長たちにしても、大山倍達に憧れ、空手道に身を投じ、苦しい稽古を耐え抜き、試合などで実績を残した猛者たちだった。
しかし津浦伸彦は娘婿というだけで空手の実力や実績はなかった。
支部長会議で他の支部長と並んで座ろうとして
「お前は何でそこに座っているんだ。
向こうに座れ」
と大山倍達に一喝されたこともあった。
今回は大会開始を30分も遅延させて粘ったが、
「いいか津村、今回は我慢しろ」
と盧山初雄に諭され応じた。
会場の照明が落ち、アナウンスがなった。
「今大会の最高審判長、大山倍達総裁の入場です」
空手バカ一代の主題歌が流れ、スポットライトが会場の隅を照らすと大山倍達の遺影を抱いた松井章圭。
松井章圭は大歓声の中を歩み、「最高審判長」と書かれた座席に遺影を置いた。
隣席は「大会審議委員長」の梅田嘉明。
郷田勇三、盧山初雄が続いた。
大会は滞りなく進行した。