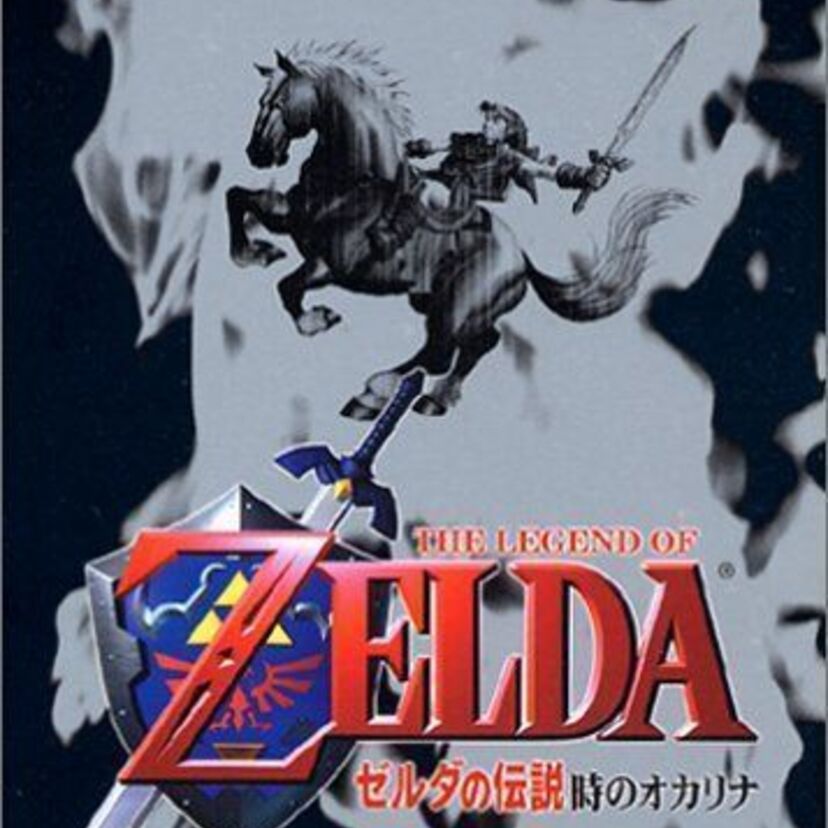ゲームでしか味わえない感動がある
これは『ゼルダの伝説・時のオカリナ』CMのキャッチコピー。
今ほど全年齢的にゲームをしているような時流ではなく、もちろんスマホゲームなんてない頃に
「ずいぶんと大きく出た」キャッチコピーなのですが
これがもうその通りの素晴らしいゲームだったのです。

ゼルダの伝説 時のオカリナ
Amazon | ゼルダの伝説 時のオカリナ | ゲームソフト
ファミ通レビューで初の40点満点を取ったゲーム
4人の「週刊ファミ通」編集者が1人10点満点で評価をつける「クロスレビュー」で
レビュー開始12年目にして初めて、4人全員が満点をつけたゲームです。
レビューをざっと抜粋すると
「まさにゲームに身を委ねる感じだ。」
「見上げるとまぶしい太陽、石を持ち上げると逃げ出す虫……。あたかも自分がリンクになったかのように、ゲームのなかの世界が体験できる。それでいて、謎の難易度が絶妙で、本筋に関係ない遊び要素も満載だからたまりません!!」
「誰もが自分だけは解けたと思わせる難しさ。体験がその後に活かせる良さ。」
短いレビューの中にどれだけ絶賛の言葉を入れ込めるか
苦労がしのばれる内容になってますね。
また、海外のレビューサイトの評価をスコア化するMetacriticというサイトにおいても、2016年時点で最高得点(99点)を獲得しています。

週刊ファミ通 1998年11月27日号表紙
ヤフオク! - ■送料無料■H5■週刊ファミ通■1998年11月27日No.51...
『ゼルダの伝説』とはどういうゲームか
名前は聞いたことあるけど、プレイしたことはない、という方のために。
『ゼルダの伝説』は、1986年のファミコンディスクシステム版を皮切りに、
以来30年にわたって15本以上作品の出ているシリーズです。
ちなみに「ゼルダ」は、シリーズに出てくるお姫様の名前。
主人公の「リンク」が、アクションと頭脳を駆使して「ゼルダ姫」を助け
世界を征服しようとする悪(ガノン)と戦い、それを阻止するのが、ゲームの基本です。
ゼルダ姫も、マリオシリーズのピーチ姫みたいに
しょっちゅうさらわれるのがお約束のお姫様じゃなく
一緒に闘ったり、アイテムを授けたり、別人格になって主人公を鍛えたりして
いろいろと重要な動きをします。

amiibo こどもリンク (大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ)
Amazon | amiibo こどもリンク (大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ) | ゲーム
初期のテュートリアルが親切で入りやすい
いろいろなダンジョンがあるのはRPGの基本ですが、
ゼルダシリーズの場合、主人公は最初は何も持っていません。
剣も武具も、そこらへんの木をゆすったり草を抜いたりして金(ルピー)を集めて買ったり
いろいろ探索をする過程で手に入ったりします。
ダンジョンに入る前の準備を、操作に慣れることで整えていけるのが
本当に初期のテュートリアルとしてきちんと作られています。
経験値システムではなく、アイテムで成長
FFやドラクエなどのRPGは経験値システムですが
ゼルダシリーズは経験値という概念がありません。
剣や武具だけでなく、いろいろなアイテムをもつことが
ストーリーを進めるためのキーポイントになります。
ダンジョン攻略やさまざまなおつかい、
本筋には関係なく思えるミニゲームやコレクションで入手できる「アイテム」が
今攻略中のダンジョンにとても有効なツールとして活用できるように用意されていて
ダンジョンでどうしても先に進めないとき、
持っているアイテムを、それまで思いもよらなかった方法で使って
解決できたりするんです。
その「謎解き」がゼルダシリーズの「成長」であり
正解を表すメロディが、なんとも言えない快感をもたらすのです。
「時オカ」ならではのポイントその1 コントローラ操作
nintendo64というゲーム機は3Dの世界を広げたマシンです。
64マリオが出た時の衝撃は忘れられません。
そして3Dキャラクタをコントローラで動かすのは、実はとても難しい。
その操作のハードルを上手に超えやすくしてくれたのが「時オカ」でした。