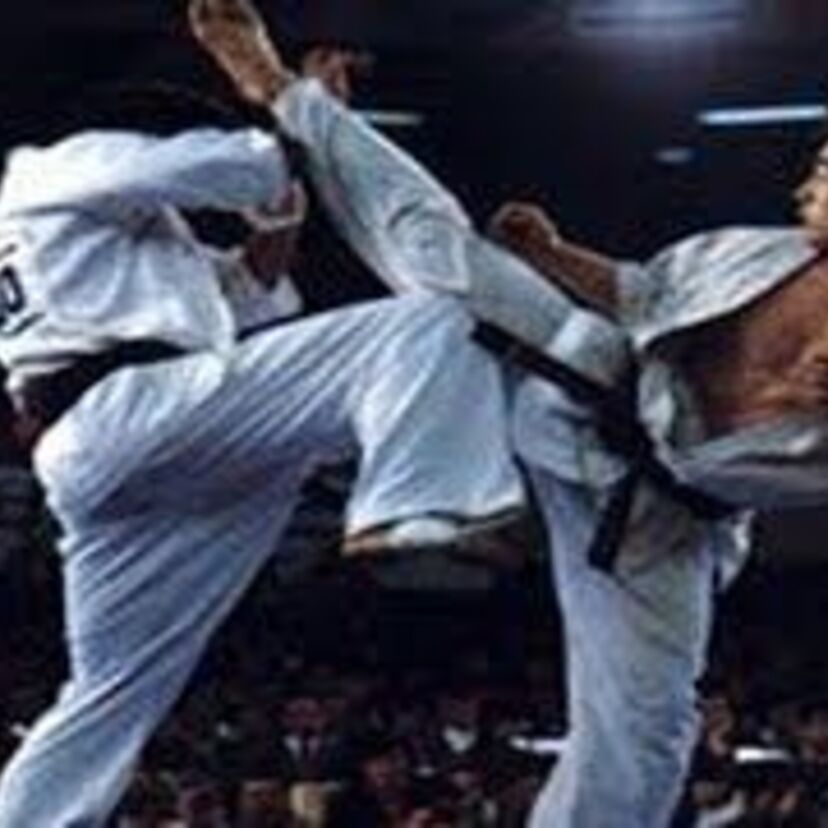「2倍も3倍も努力しなくては認めらない」
松井章圭は、「極真会館」ができる前年(1963年)に生まれた。
父親は、大韓民国(韓国)の済州島で生まれ、
「日本で勉強し、アメリカで実業家になる」
という志を立て、19歳のときに漁船に乗って広島県の尾道に渡った。
2年後、東京で愚連隊に因縁をつけられていたところを「松井」という親分に命を助けられた。
これをきっかけに日本での通名(外国籍の者が日本国内で使用する通称名)を「松井」にした。
その後、働きながら法政大学を卒業。
しかし朝鮮戦争勃発すると韓国人難民を装った北朝鮮のスパイの入国を危惧したアメリカが朝鮮人の入国を制限した。
そのため父は「アメリカで実業家になる」という夢を断念し喫茶店を始めた。
そして数年後には広い庭つきの2階建ての家を建てた。
しかし親戚の借金の保証人になったことで、数億円の借金を背負い、家も喫茶店もとられ、4畳半のアパートに移った。
その後、10年間、スナック、サウナ店、焼鳥屋、食堂と転々と経営し、13回も引越しをしながら、借金を返し続けた。
家を借金で失いアパートにうつったとき松井章圭は小学生だった。
体が小さく、色白でぽっちゃりし、勉強も体育も真ん中だったが、強い正義感を持っていた。
また偏見を持つ日本人から差別を受けた経験から自然と
「2倍も3倍も努力しなくては認めらない」
と認識していた。
学校で、女子につい傷つけるような言葉をいってしまったあとは自己嫌悪に陥り、その子のところにいって謝り
「これからは絶対に悪口をいわないからな」
といって握手した。
部活動で後片付けをサボっている上級生5人を
「みんなで後片付けをするのが決まりじゃないですか」
と注意すると、翌日、その5人に体育館の倉庫に連れ込まれ殴られ蹴り回された。
松井章圭は、悔しくて眠れなかった。
「正しいことを行うためには強くなければならない」
『つらい』『苦しい』『痛い』禁止

ある日、松井章圭は、「週刊少年マガジン」を立ち読みをしていると
「これは事実談であり、この男は実在する」
という引き込まれる見出しで始まるマンガに遭遇した。
「空手バカ一代」だった。
松井章圭は、大山倍達の超人追求物語をみて、まるで神の啓示に打たれたような心境になった。
その後、「空手バカ一代」だけではなく、大山倍達の著作も買って読破していった。
それらはすべて強くなるための方法が書かれたもので、すべて松井章圭のバイブルになり、本棚に並んでいった。
そして1人で極真空手の基本稽古、拳立て伏せなどのトレーニングをやり始めた。
それをみた父親のすすめで少林寺拳法の道場に入った。
しかし相手を叩きのめさない稽古に物足りず、稽古中につい
「極真はこんなものじゃないだろう」
といってしまい周囲をいやな空気にさせてしまったこともあった。
結局、この道場を半年でやめた。
1975年11月、東京体育館において極真空手の第1回世界大会が行われた。
これは「地上最強のカラテ」というドキュメンタリー映画となった。
松井章圭は映画館でそれを観た。
やがて電柱や壁など硬いものがあると拳を当てて鍛えるようになった。
そして隣町に極真の道場ができると親に通わせて欲しいと頼んだ。
母親は、800人中、300~400番くらいの成績だった息子に
「100番以内に入ったら許します」
といった。
すると60番まで上がった。

1976年6月12日、松井章圭は13歳で極真に入門した。
家からバスで30分のところにあった極真会館千葉北支部流山道場は、20畳ほどのプレハブ小屋で、指導していたのは加藤重夫だった。
加藤重夫は、155㎝50㎏。
160㎝60㎏の松井章圭より小さかった。
16歳のときに大山道場に入門。
高校卒業後、豊島区役所に勤務するも空手に熱中するあまり8ヵ月後に退職。
血まみれになりながら稽古を続けた。
そして相手の蹴りや突きを肘で受ける受け技「落とし」を体得。
国内だけでなく、オーストラリア支部へ派遣され指導を行った。
また映画「007は二度死ぬ」で、姫路城の屋根の上のシーンを演じた。
加藤重夫は松井章圭に入門の動機を聞いた。
「将来、空手家になりたいんです。
極真空手を一生続けていくつもりで来ました」
「よし、わかった。
それならば
お前は極真のチャンピオンになりたいんだな?」
「はい」
「よし、がんばれよ。
そのかわり今日から『つらい』『苦しい』『痛い』という3つの言葉だけは絶対にいうな。
できるか?」
「はい」

松井章圭はさっそく練習に参加した。
まず
「押忍」
という挨拶の仕方を覚えた。
そして稽古は神前への礼、師範への礼、門下生同士の礼から始まった。
準備体操が終わると拳立伏せ、腹筋、背筋などの補強運動。
そして基本稽古に入る。
正拳突き、裏拳、肘打ち、手刀、上段受け、中段外受け、内受け、下段払い、前蹴上げ、内回し蹴り、外回し蹴り、膝蹴り、金的蹴り、前蹴り、横蹴り、関節蹴り、後ろ蹴り、回し蹴り・・・
各30本、気合をかけながら行う。
その後は深く腰を落としたまま移動し、連続して基本の技を出す移動稽古。
「苦しいときこそ足の親指に力を入れろよ。
親指があらゆる技を出すときの源なんだからなあ」
加重夫の怒声に
「押忍」
と全員が答え、汗にまみれながら動いた。
「いいか、苦しくなってきてからの頑張り、すなわち一枚腰ってやつは誰だって持ってるんだ。
これを乗り越えて次にやってくる苦しさで半分のやつは音を上げるんだ。
ここまでが二枚腰ってやつだ。
さらに苦しさが増す。
だがさらに自分を追い込んで逃げないやつ。
根性で食らいついてくる人間。
こいつこそが三枚腰の人間なんだ」
「押忍」
移動稽古後は、2人1組で攻撃側、防御側に分かれて技をかけあう約束組手。
その後、さらに型の稽古を行う。
そしてやっと組手となる。
直接技を当て合う直接打撃制の組手を1~3分、相手を変えながら行う。
加藤重夫は、入ったばかりの松井章圭にも組手を命じた。
相手は緑帯を締めた同じ中学校に通う同級生だったが、松井章圭は突きで押しまくられ、鼻に蹴りをもらった。
鼻血を出して倒れたが、痛みや屈辱よりも
(やっぱり極真は強い)
という感動と興奮のほうが大きかった。
組手が終わると柔軟体操を行う。
そして正座して黙想。
全員、大きな声で道場訓読み、礼をして稽古は終わった。
その夜、松井章圭は自宅の鏡の前に買ったばかりの左胸に紺色の糸で「極真会」と刺繍された道着を着て立った。
「俺は絶対に黒帯になる」
20㎝の距離があればハイキックが蹴れる
厳しい極真空手の稽古に強くなりたいと門をくぐったはずの多くの人間が道場から遠ざかった。
しかし松井章圭は稽古を1日も休まなかった。
稽古時間の30分前に道場にいき個人稽古。
稽古中は、加藤重夫との約束通り、どんなつらい稽古にもキツい表情をみせず、やり抜いた後も得意がることなくポーカーフェイスで押し通した。
しかしその目は輝いていた。
通常の稽古が終わった後は居残り稽古。
そして帰宅した後は、夜の縄跳び1000回、風呂に入った後の入念なストレッチを欠かさなかった。
入門3ヵ月後、加藤重夫は松井章圭に、
・目隠しサークルシャドー
・合わせ技
・下段回し蹴り禁止
という3つの特訓を与えた。
目隠しサークルシャドーは、床にチョークで直径3mの円を描き、その中に目隠しした2人が入り、3分間、相手を想定したシャドー組手を行う。
これにより恐怖心の克服、高い集中力を養う。
合わせ技は、蹴り技で攻めてくる相手の軸足を蹴って倒すことで、相手が蹴り技を仕かけてくる瞬間、相手の技を読み切るのと同時に地を這うような蹴りで相手の軸足を蹴る。
スピード、フットワーク、瞬時に相手の技を読む力が要求される。
下段回し蹴り、つまりローキックは、フルコンタクト空手では主力の技だが、加藤重夫は、松井章圭に中段から上の多彩な蹴り技を完璧に身につけさせるために下段回し蹴りの使用を禁止した。
やがて松井章圭は、壁に向かって立って20㎝の距離があれば、左右の上段回し蹴りが蹴れるようになった。
極真史上最年少の黒帯
千葉県の一宮海岸で行われた夏合宿に参加したとき、松井章圭は神のように崇拝する大山倍達を初めて生でみた。
合宿2日目の夜、大山倍達は、サングラスに道着のズボン、白いランニングシャツで登場し講話を始めた。
白帯の松井章圭は最後列だったが、一言も聞き漏らさないように正座したまま話を聞いた。
「バシッ!」
技を説明するために大山倍達が左手に右肘を打ちつけると、全身が反応した。
「君たち、1度立ち会ったら1発で相手を倒さなければならないよ」
大山倍達の講話が終わっても松井章圭は正座を崩せなかった。
白帯の松井章圭が初めて昇級審査に参加したとき、再び神と遭遇した。
審査課題の中に「拳立て伏せ×50回」があったが、松井章圭は42回しかできなかった。
すると審査に来ていた大山倍達が声をかけた。
「君は何回やったんだね?」
「押忍、42回です」
大山倍達は激しく怒った。
「なんでそのあと8回ができないのか。
死ぬ気になればできるよ」
松井章圭は、落ち込んだ。
自分の取り組み方が甘かったと、夜の縄跳び1000回、風呂に入った後のストレッチに加え、腹筋、背筋、拳立て伏せも毎日行うようにした。
こういった得意な部分を伸ばすことよりも、自分の弱点の克服に全力を尽くす稽古の方向性も、松井章圭の特徴だった。
中学3年生になり茶帯の昇級審査を受けた松井章圭は、再び大山倍達に声をかけられるになる。
基本稽古、移動稽古の審査ではひときわ高く美しい蹴りを、組手の審査では、大人を相手に、跳び2段蹴り、後ろ回し蹴り、上段回し蹴りを連続的に繰り出して華麗な組手を行った。
「君、ほんとに14歳?」
「押忍」
「うーん」
と大山倍達は唸り
「君は必ず強くなるから頑張って稽古しなさい」
と励ました。
こうして入門1年という異例の速さで茶帯に昇級した。
極真空手の帯は、白帯から、青帯、黄帯、緑帯、茶帯と昇級していき、有段者になると黒帯となる。
黒帯の端には締めている者の段位を、初段なら1本というように金糸の線が刺繍され、段位が上がる度に1本ずつ増えていく。
この頃、黒帯になれるのは、門下生数百名に1人だった。

茶帯になった松井章圭は、加藤重夫に、大山倍達が直接指導し、圧倒的な強さを誇る総本部道場への出稽古を申し出て快諾された。
こうして許可を得た翌日、新しい茶帯を巻いた道着をもって電車で東京へ向かった。
地下のロッカールームで着替え、稽古が始まった。
加藤重夫の指導では、基本稽古は1つの技が30~50本だが、総本部は、そんな数では終わらず、最後の回し蹴りは500本だった。
組手稽古が始まると、最初の相手は、自分より体の小さな茶帯だった。
太鼓が鳴り構えた瞬間、右の顔面に衝撃が走り視界が曇った。
相手の左上段回し蹴りをもらっていた。
次の瞬間、体が宙を舞い背中に衝撃が走り息が詰まった。
相手は松井章圭の襟をつかんで体落としで床に投げつけていた。
「大丈夫か」
遠くに相手の声が聞こえた。
次の瞬間、腹部に強烈な痛みが走り完全に息が止まった。
相手は松井章圭の腹部に極めの足蹴りをめり込ませていた。
この後の組手でも、松井章圭は突かれ、蹴られ、投げられ、踏まれ続けた。
自分の技はまったく決まらず、逆に相手の技は1つ1つが、速く、痛く、重かった
当時の総本部の組手は、失神しても殴る、蹴るという激しさだった。
門下生は
「死んでしまうかもしれない」
という恐怖心に潰されるかバネにできるかだった。
やっと稽古が終わると、松井章圭は、逃げるようにして総本部を飛び出し電車に乗って帰宅を急いだ。
車中で涙が出た。
(もうやめようか)
入門以来はじめて極真空手をやめることを考えた。
しかし数ヵ月後の1977年10月、入門して1年4ヵ月の松井章圭は昇段試験を受け、合格し、黒帯になった。
まだ中学生の極真史上最年少の黒帯だった。
ワルにもガリ勉にもスポーツ系にも顔が利く優等生