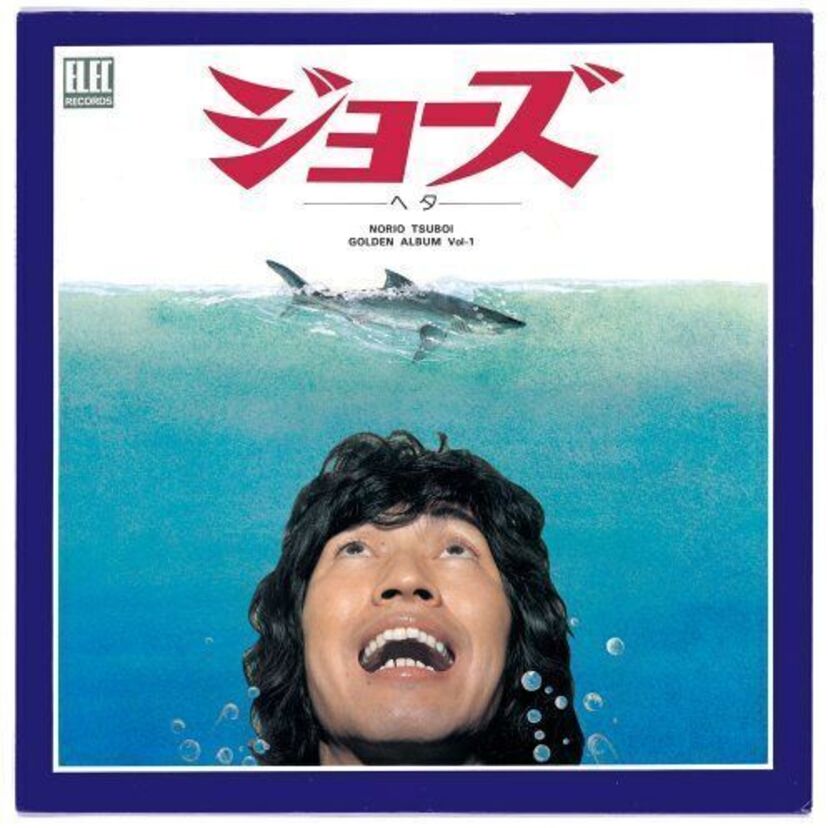コミックソング
いつの時代も私たちを楽しませてくれるコミックソング。実はコミックソングとは和製英語で、英語ではノヴェルティ・ソングと呼ばれています。いずれにしても笑える音楽の総称です。
笑える音楽といってもいい加減では誰も笑ってくれません。いい加減にみえて実はしっかりとした音楽性に裏付けられていたりするのがコミックソングだったりします。なかなか奥が深いジャンルなんですよね。
それでは、70年代前半の代表的なコミックソングをご紹介します。
1970年 老人と子供のポルカ
今にして思えば、70年代というのは実に良い時代でした。オイルショックなどというものもありましたが、なんとものんびりとしていて貧しくとも余裕がありました。そして、温かみがあった。人と人の交流があった。
そんな時代を反映したコミックソングから70年代は始まります。1970年2月に発売された「老人と子供のポルカ」がそれです。

老人と子供のポルカ
歌っているのは、左卜全とひまわりキティーズ。左卜全は明治27年生まれの俳優で、当時すでにおじいちゃんだったのですが、その彼がひまわりキティーズという女の子と一緒に歌うというだけでインパクトがありました。
ほがらかです。今聴いても十分脱力しますね。当時「ズビズバァ~」という歌詞は、当然のように流行りました。
1970年 走れコウタロー
1970年には、もう一曲忘れられないコミックソングがあります。ミリオンセラーとなったソルティー・シュガーの「走れコウタロー」です。

走れコウタロー
後にソロで大活躍する山本コータローが在籍していたことでも知られるソルティー・シュガーですが、「走れコウタロー」は2枚目のシングルになります。デビュー曲が全く売れなかった彼らにとってこの曲は、歌詞同様に起死回生の一曲だったのです。
1973年 悲惨な戦い
1973年、年明け早々に発売されたのがなぎら健壱の「悲惨な戦い」です。当時は「なぎらけんいち」と名乗っていました。
「悲惨な戦い」、よくできた曲です。とにかく聞かせます。いきなり歌の世界にひっぱりこまれてしまいます。これはもう職人技としか言いようがありません。

悲惨な戦い
職人技といえば、ジャケットのイラストも本人が描いています。なにより、歌ばかり聴いていると聞き逃してしまいがちですが、ギターが上手いんです。コミックソングだからと言って侮るなかれ。本気度が伝わってくる名演でもあります。素晴らしいとしか言いようがありません。
1973年 赤とんぼの唄
1973年は続けざまに優れたコミックソングが発売されます。「悲惨な戦い」から2か月後の3月に「赤とんぼの唄」が大ブームとなります。
歌っているのは、これがデビュー曲のあのねのね。ご存じ清水國明と原田伸郎のコンビです。