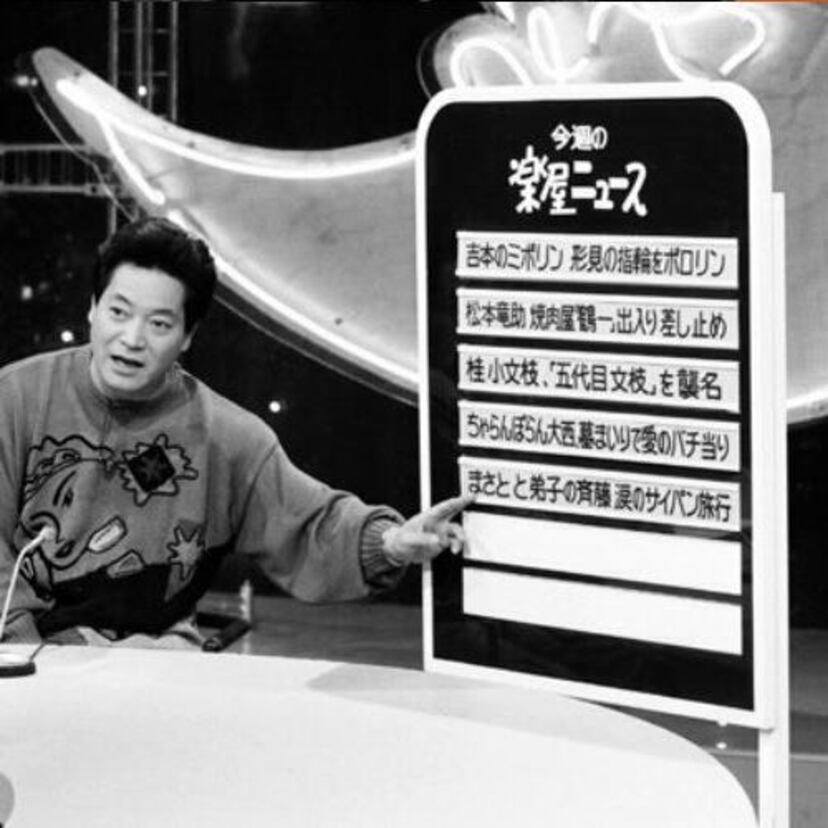月亭八方、本名:寺脇清三は、大阪府大阪市福島区出身
経済の中心地、中之島に隣接し、キタの梅田にも歩いていける福島区に、現在も住んでいる福島人。
姉、兄、姉、姉、姉、そして自分という6人兄弟の末っ子。
1番上の姉は20歳上、兄は18歳上という歳の離れた兄妹の中で、ご飯を食べるときは焼き魚の骨を取ってもらい、自分だけ甘いものを出たり、非常に大切に育てられた。
「ボクがかわいくてしょうがなかたんじゃないかな」
という月亭八方は、大人になって20歳以上下の芸人、メッセンジャー黒田の子供の頃の貧乏話を聞くと
「壮絶やな」
と驚いた。
プロ野球が大ブームで、大の阪神タイガースファンである兄に
「阪神はええチーム」
「巨人は悪いチーム」
「藤村富美男はええヤツや」
「川上哲司は悪人」
と吹き込まれながら、月亭八方は野球少年に。
近所の空き地で始めた野球は、中学生になると野球部に入り、阪神の天才ショート、吉田義男をマネしながら内野でプレーした。
「中学で野球部に入って以来、野球が好きというより、日常生活、人生そのものを野球に関連づけて生きてた気がします」
銭湯に行けば下駄箱の番号は、憧れの吉田義男の背番号、23番。
23番が空いてなければ、長嶋茂雄のライバル、村山実投手の背番号、11番。
王貞治の1番、長嶋茂雄の3番、川上哲司の16番は、
「敵だから」
と絶対に使わず、23番も11番も空いていないときは、
「どっちかが空くまで待ってた」
野球と阪神タイガーズのことばかり考えて暮らす月亭八方が好きな電車は、もちろん阪神電鉄。
福島駅は大阪環状線もあったが、できるだけ阪神電車を使い、デパートに行くなら、阪神百貨店で、
「阪神ブレーブスのデパート(阪急百貨店)で買い物するなんて、とんでもない」
5人の姉と兄は、全員、中卒だったが、月亭八方だけ高校に進学。
名門、浪商高校(現:大阪体育大学浪商高校)野球部に入り、
「中学でそれなりに活躍してたから高校に入ってもかなり上の方、うまい方や」
と思っていた月亭八方は、甲子園出場を夢みていた。
しかし新入部員が数百人いたことに、まずビックリ。
そしてその中には中学の全国大会で優勝したピッチャーや各県のスターがゴロゴロいることにまたビックリ。
そしてそういった選手は1年生から練習させてもらえたが、月亭八方たち普通の新入部員はグラウンドの外で声を出しているだけという状況にガッカリ。
さらに2つ上の先輩、高田繁(ドラフト1位で巨人入団)の高校生離れしたプレーをみて、またまたビックリ。
月亭八方は、
「上には上がある。
野球は大好きだけど、甲子園に行くことやプロ野球選手になることは、とても無理」
とあっさり野球部を辞めてしまった。
大阪人である月亭八方は、元々、お笑いが好きだった。
特に漫才や新喜劇が好きで、吉本興業の劇場、うめだ花月やなんば花月にいくと演目の中に落語もあったが
「年寄り臭い」
「邪魔やな」
と思いながらやり過ごし、漫才や新喜劇の
「うどん300万円~」
で大笑いしていた。
しかしある日、高校の落語好きの友人に
「絶対、面白いから」
と誘われ、電車に乗って京都の市民寄席へ。
入場料が安かった上、確かに落語も面白かった。
その後も市民寄席に通い、うめだ花月やなんば花月でも落語を真剣に聞くようになるとお笑いに対する考え方が変わってきた。
「漫才は新喜劇は、瞬発力のある笑い。
だからドーンとウケるけど、同じネタを繰り返しみてると面白さが減っていく。
一方、落語は、爆発的な笑いはないけど、いい回しに様々な味があり、ユーモアがあり、落語家によっておもしろおかしくうまいこというなあと耳になじんできます」
特に笑福亭仁鶴の存在は大きかった。
「仁鶴さんは、27歳か28歳だったと思うけど、風格も声もオッサンそのものだった。
で、独特のダミ声でラジオもやってたんです。
ハガキを読んだり、音楽をかけたりもしてたんですが、1人で話すときには落語家ならではの落語的な展開があった。
1人で近所のオッサン、お兄ちゃん、オバハンになりきって話していく。
落語の1人しゃべりを聞いているようでした。
すっかり仁鶴さんの芸に魅了されて、仁鶴さんの落語があると聞けば万難を排して観にいくようにしてました。
枕でラジオそのまま日常の些細なことをしゃべるから、こっちはうれしくてたまらん。
気持ちが盛り上がったところで、スッと古典落語の噺を始める。
この時代のエピソードから昔々の古典落語の世界にすんなり入っていく。
何の違和感もなく古典落語の世界を満喫できた」
何度も笑福亭仁鶴の落語を聞きにいっているうちに落語にハマっていき、
「若手の仁鶴さんがこんなにおもろいなら古株はどんなもんなんやろう?」
と思い、師匠クラスのベテラン落語家も聞くようになり、その貫禄のある話術に引き込まれた。
3代目桂春団治、6代目笑福亭松鶴も面白かったが、1番は、3代目桂米朝で、月亭八方はファンクラブにも入会。
「すると次の高座の案内もやってきますから、米朝師匠の追っかけみたいになってしまった」
こうして野球少年から見事に落語少年になってしまった月亭八方は、家に帰ると
「ただいま」
とはいわず、米朝師匠が落語でいっていたように
「いま戻った」
家の中で母親に会うと
「しばらく顔みせなんだが、オカンどないしよってん」
教室に入るときは
「派手に上ろか、陰気に上ろか。
それとも陽気に上ろか、哀れに上ろか」
と落語の一節を話し、
「よしんば」
「さりとて」
「そんなこというたとてやな」
など落語のいい回しを使って、友人に
「古いなあ」
といわれるとうれしくて仕方なかった。
「いろんなことが好循環していって、どんどん落語に惹きつけられて、ほんま落語に夢中でした」
しかし高校3年生の冬、進路を考える時期になると憧れてはいたが落語家になる自信はなく、笑福亭仁鶴に弟子入りしたり、米朝一門に入るなど考えもせず、姉の嫁ぎ先である機械工具店に就職。
高校卒業後は、大阪市福島区にある機械工具店で働きながら、休日は落語三昧という生活が始まった。
仕事は、荷物を運ぶ単純作業だったが、教習所に通い、自動車運転免許証を取得すると配達も任されるようになり、運転しながら笑福亭仁鶴のラジオを聴き、配達先に着いても途中だと停車したまま最後まで聴いた。
そうしているうちにどうしても落語家になりたくなった月亭八方は、働き出して1年過ぎた19歳の春、母親に
「落語家になりたい」
と打ち明けた。
「高校までいったのに、なんで芸人やねん。
アホなこといいな。
もったいない」
と反対する母親を、
「頼むから少しの間だけ飯だけ食わせてくれ。
もちろん小遣いはいらん」
となんとか説得。
とはいえ会社は辞めず、働きながら、
「誰に弟子入りしよう?」
と思案。
桂米朝が1番良いが、弟子入り志願者は間違いなく多く、
「門前払いされたり、弟子入りできても浪商野球部のように競争率が高い」
と却下。
あれこれ思案しながら落語会に通っているうちに師匠にしたい落語家を発見。
それが桂米朝の直弟子である桂小米朝(後の月亭可朝)だった。
桂小米朝は、高校を卒業後 3代目林家染丸に弟子入りし、高座に上がったが、不行儀を起こして破門。
3代目桂米朝の預かり弟子となり、2代目桂小米朝として再出発した若手落語家。
師匠、米朝は、弟子に
「面白い芸人にならんでエエ。
エエ人間になりなさい」
と指導し、71歳のときに人間国宝(重要無形文化財保持者)に認定された超マジメ人間。
それに対して筆頭弟子の小米朝は、型破りで破天荒。
70歳のときにストーカー規制法違反容疑で逮捕された。
小米朝は、米朝を心から尊敬する他の弟子たちと少しスタンスが違った。
「米朝師匠のところにはオムツしてる子どもが3人おったんですよ。
長男と次男が双子や。
そのオムツを替えるのは弟子の仕事やったのに、僕は、それができんかったんや。
枝雀くんとざこばくんは、ずっとオムツ替えてとやってたけども、僕は、それやれいわれたらもう辞めて家に帰りますわ。
いつの間にやら師匠はオムツを替えてる弟子たちに「あいつはどうしようもないやっちゃ」ということをいうて、世間にもそんなことをいい出したんや。
終いには「あれはわしの弟子やない」とまでいうたけども、僕は「ああ、けっこうですよ」と思うとった。
師匠は家では僕に落語を教えませんねん。
家では枝雀くんとざこばくんがオムツを替えたり、哺乳瓶で乳を飲ましたりしとるわけやから、なにもせんとブラブラしとる僕にを教えるわけにいかんのですよ。
だから外に出たときにどこかの小さい安い宿屋の部屋を借りて、そこで教えてくれた。
外に出たら、たいがい稽古もついてましたから、それは他の弟子にはいわずに僕と師匠の間だけやった」
「お笑いの世界はギャンブルみたいなもんでっせ。
ハッタリというか駆け引き。
ゼニは入ってくるし、刺激はあるし、舞台もやったらやっただけ反応が返ってくるし。
僕らの感覚では芸人のギャラなんて仕事した報酬じゃないわね。
みんなで遊んで騒いでるだけのこと。
そんなんでもらったカネを貯金するっちゅうのはおかしいわな」
という小米朝は、飲む、打つ、買う(酒、バクチ、女)を
「芸の肥やし」
「芸のうち」
と積極的に行い、競馬は、
「2倍、3倍ではおもろない」
と不人気馬を買って大穴狙い。
親密な関係になった女性の数は100人以上いるという。
「自分ではモテたためしはないと思ってる。
そんなタイプやない。
けど、モテへんでも100人くらいはいける。
昔、遊郭あったやろ。
そんなんは抜きや。
横山ノックは1000人いったというてたけど遊郭も入れとる。
みんなプライドが高くてフラれたらどうしようかとか思ってる。
そういう風潮はアホですな。
寝つきにくいとき、羊が1匹、2匹って数えるやろ。
僕は眠られへんときは自分がいった女を北から思い出すねん。
北海道から女1匹、女2匹や。
70くらいで寝てまう。
北から数えて九州にいくまでに寝てまう。
数えとったらな、あの女だけはやめといたら良かったいう女が出てくるんや。
自分でも残念でしゃーない。
あんなんいかなんだら良かった。
それが京都の女で、西から数えても東から数えても出てきよんねん。
人妻やったわ」