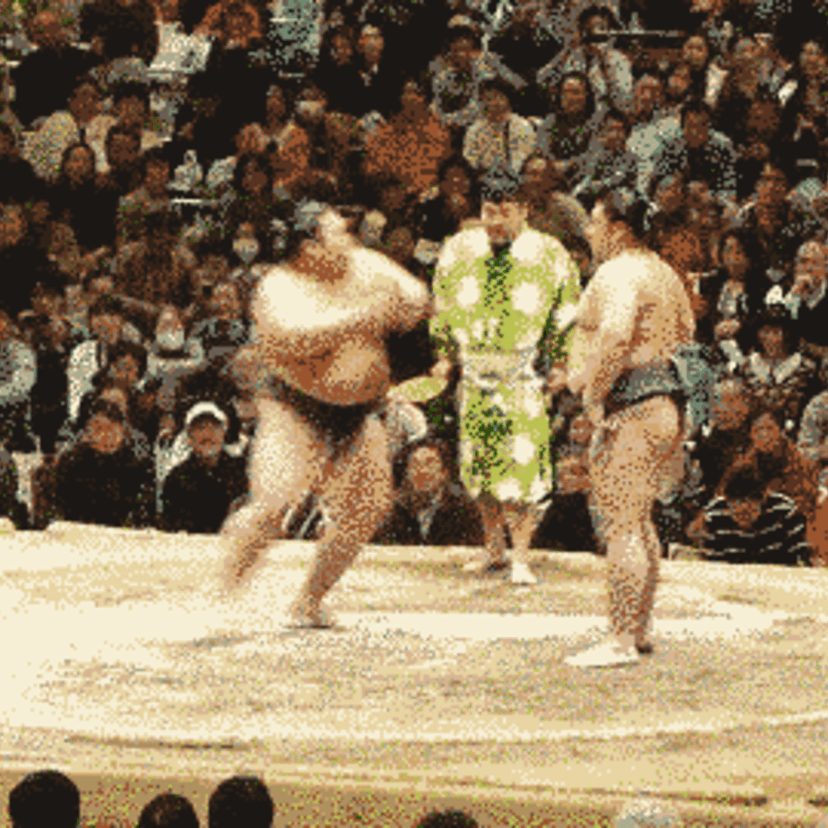まずは、相撲初心者の質問ー「お相撲の力士が仕切りで何故塩を撒くのか??」
相撲はもともと、どちらの力士が勝つかによって、豊穣や豊漁を占う神事としての相撲でした。
この占いとしての側面から、取組みの前に「占いの場=神聖な場所」を浄める「清めの塩」として、土俵に塩を撒く風習が生まれたと言われている。
現在の大相撲でも、実は三段目以下の力士は、「塩をまく事ができない」そうだ。幕下になってようやく、しかも、時間に余裕がある時だけまく事ができるのである。
「塩を大量にまいたら相手がビビるかも?」と思い、大量の塩を撒き始めた”旭日松”!!

旭日松(あさひしょう)の塩撒き

旭日松 広太(あさひしょう こうた)
私の世代だと、”若秩父”が思い出の筆頭に来る!!

若秩父 高明(わかちちぶ こうめい)
'54年夏場所に花籠部屋から初土俵を踏み、'58年秋場所に19歳で新入幕。富樫(後の横綱・柏戸)らとともに「ハイティーントリオ」と注目される。1メートル75、150キロの体を生かした左四つ、寄りで'63年名古屋場所新関脇。糖尿病に苦しみながら、幕内在位51場所で敢闘賞を2度受賞した。'68年九州場所限りで引退後は常盤山親方として後進を指導した。
なので、皮肉って川柳でこう詠まれたそうだ。
『塩などは、安いもんだと、若秩父』
現在、私は若秩父の正確な顔や姿を忘れてしまったようだが、大量の塩を撒く相撲力士として誰を思い出すかと聞かれたら、やはりまず第一に若秩父という名前が蘇ってくる。
きっと子供の頃の”彼の大量塩撒き”に相当大きな衝撃を受けたのだろう・・・!?
オイルショックの余波で塩が”もったいない!”と批判されたこともある”青葉山”!!

青葉山 弘年(あおばやま ひろとし)
いわゆる”ソップ型”力士で、筋肉質の長身を生かした、右四つからの豪快な吊り技を見せてたり、肩越しの上手を取って振り回す大きな相撲だった。また、森繁久彌主演の或るテレビドラマのセリフにも、「青葉山みたいに塩をいっぱい持って来い」と名前が塩撒きの代名詞として登場するほどの派手な塩撒きで人気があった。しかし、自身が十両に上がったばかりの頃はトイレットペーパー騒動が発生してから日が浅かったこともあって、大量の塩撒きが物資の無駄であるとして批判が出た時には、青葉山の後援者から「もっと撒かせろ」と、ドーンと相撲協会に大量の塩を送って来たツワモノがいたそうだ!!。昔は剛気なタニマチがいたんだなぁ、これが!!。
あいにく、彼のこれといった画像や動画が見つかりませんでした。あしからず!!
あだ名を「ソルトシェイカー」と命名された”水戸泉”
新十両の場所の8日目から付人の奄美富士の「勝ち星に恵まれないときはせめて塩だけでも景気よくまいたらどうですか」という進言により、大量の塩を撒くようになった。
初めの頃は1回目から大きく撒いていたが、後に制限時間いっぱいの時にのみ大きく撒くようになった。1回にとる塩の量は何と600gにもなったという。イギリス巡業で「ソルトシェイカー」と紹介され、日本でも「水戸泉といえば豪快な塩まき」として定着した。同時代で同様に大量の塩を撒く力士には朝乃若がおり、対戦した際には豪快に撒き上げる水戸泉と叩きつける朝乃若の両者の塩撒きに観客が沸いた。

水戸泉 眞幸(みといずみ まさゆき)