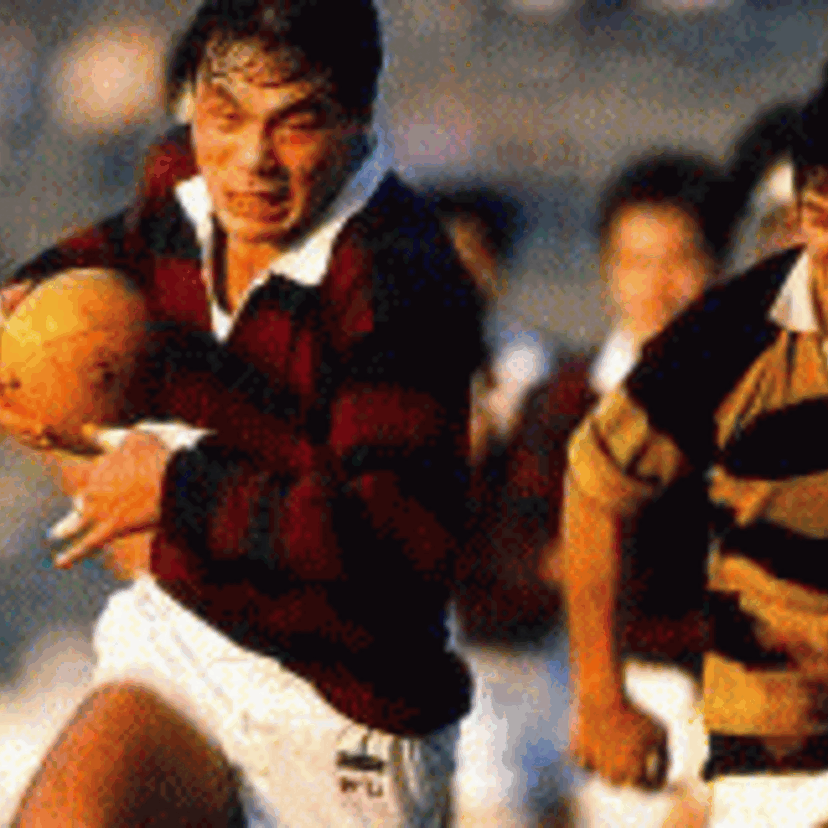教師の一言

清宮克幸は大阪府福島区に生まれた。
小学生では野球部、中学ではサッカー部に入り、番長だった。
体が大きくて、力も強く、エネルギーがありあまって、それがどうしても喧嘩に向いてしまった。
しかしそれは弱いものいじめや、多数で少数を痛めつけるようなことはせず、武器は持たず素手と素手の力比べだった。
中学3年生のときに他校の番長と喧嘩し、警察で事情聴取された。
学校に戻ったとき、清宮に担任の女性教師が言った。
「寒くなかった?」
女性教師の目の下にはクマができていた。
普通なら、「理由は何だ?」とか、「どうしてそんなことをしたんだ?」だろう。
もしかしたら「どアホ」だったかもしれない。
この女性教師の言葉と気持ちは、清宮の心にきた。
その後、自宅謹慎中にいろいろと考えていると、自分には親友と呼べる友が1人もいないことに気づいた。
清宮は改心することを決めた。
髪形や服装も改め、勉強をするようになった。
その直後、別の教師が、清宮にラグビーをすすめた。
「ラグビーするなら茨田(大阪府立茨田高等学校)へ行け。」
茨田高校は、比較的、新興の学校だったが、ラグビー部は有名だった。
清宮はここで素晴らしい先輩や同期に恵まれた。

茨田高校ラグビー部監督:吉岡隆は、自主性を重んじ、キャプテンに練習メニューを考えさせ、そのほか何から何まで選手が行うことを望んだ。
練習時間は60~90分。
決して長い時間ではなかったが、過去に何度か花園の全国大会に2回出場していた。
吉岡隆は、清宮の面、体格、センス、その他すべてを認め、1年からレギュラーとして起用した。
清宮は、2年生でオール大阪の代表メンバーにも選ばれ国体に出場し、3年生になると、茨田高校ラグビー部の主将となり、3度目の全国大会出場に大きく貢献した。
そして高校日本代表の主将もつとめた。
そして自分の人生を変えてくれた教師たちを尊敬していた清宮は、教員免許が取れてラグビーが強い早稲田大学の教育学部に進んだ。
雪の早明戦

大西鐵之祐(左)、木本建治(右)早稲田大学ラグビー部監督
1987年、ここ9年の優勝回数は、明治4回、同志社4回、早稲田0回。
完全に置いて行かれた感がある早稲田大学ラグビー部に、あの男が監督としてやってきた。
伝説の早稲田ラグビー部監督:大西鐵之祐の下、熱血主将として名をはせた木本建治である。
木本建治監督は、「先手、展開、連続支配、必殺タックル、荒ぶれワセダ」をテーマに掲げた。
このときの主将は永田隆憲。
また堀越正巳、藤掛三男、今泉清など、かつて高校No.1といわれた選手も戦力にいた。
そして1年生からレギュラーとなり、2年生になった清宮もいた。
「早稲田のラグビー部には、全国から集まった160人の部員がいました。
一番感じたのはその160人の人の熱です。
7軍まであって、下に行けば行くほどたくさん練習するんです。
関西では試合に出る選手が一番多く練習するという考え方が普通でしたから衝撃でした。
これが勝ち続ける理由だと思いました。
私は高校日本代表のキャプテンをやっていたのに最初はロック
(スクラムを組む際、最前列のフォワードを後ろから支えるポジション、チームで最も体の大きい人が任されることが多い)をやらされました。
181cmありましたから私が一番大きいという理由でしょう。
しかし不満に感じることもなく不思議なぐらい素直に受け入れていました。
先輩たちは私には無いものを持っていたからです。
試合当日、先輩たちはロッカールームで朝から一言も話さず、瞑想したり、壁を殴ったり頭付きをして集中します。
それをビッグゲームだけではなくて普通の練習試合でもやるんです。
新鮮な感覚でした。
1軍として出るからには常に1軍らしい試合をしなければいけない。
それぐらい1軍には責任がある。
先輩の姿を見ていれば自然にそういうことが伝わってきました。」
毎年12月の第1日曜日は、早稲田大学ラグビー部と明治大学ラグビー部が激突する早明戦が行われる。
1987年12月6日、早稲田は、ここまで全勝。
明治は、1敗しているものの、優勝への望みを捨てず伝統の一戦にのぞんだ。
未明からの降雪でぬかるんだグラウンドで、早稲田は先制トライをあげた。
しかしすぐに明治も反撃し、逆にリードを奪った。
前半38分、今泉のペナルティゴールで早稲田が追いつき7-7の同点で前半終了。
後半4分、再び今泉がペナルティゴールを決めついに逆転。
後半30分から明治は怒濤の攻撃を開始した。
しかし早稲田は激しいタックルで3点のリードを守り抜き、「雪の早明戦」として語り継がれる激戦を制し、関東大学対抗戦を優勝した。
10年ぶり4度目の大学日本一、そしてラグビー日本一に
1988年1月、早稲田大学ラグビー部は、同志社を破り、大学日本一になった。
それは大学王座から10シーズン見放されていたチームの4度目の日本一だった。
そして大学王者として、社会人王者:東芝府中と対戦。
22-16で勝ち、ラグビー日本一となった。
アクの強さ

清宮は4年生になって主将になった。
同期には森島弘光、前田夏洋といったキャプテンにふさわしい面々もいた。
とくに森島は、品行方正、頭脳明晰、正義感にあふれ、リーダーシップもあった。
2年生からレギュラーとなり、声を出し、最大限の力で練習した。
早稲田スポーツ(早稲田大学の学生新聞)に清宮と森島の比較記事が出たことがあった。
『森島は、全国の娘を持つパパがうちの娘をぜひ嫁にというような好青年。
清宮は、水道橋の場外馬券売り場で赤鉛筆を耳に挟んで歩く姿がよく似合う。』
清宮はこの記事に憤慨した。
しかし後に清宮は就職先にサントリーを選ぶが、その理由はサントリーのグラウンドが府中競馬場の近くだったからだった。
学生時代から麻雀やパチンコでは負けなかった。
ある日、新宿でパチンコをしているとき、いつもスロットマシンで大儲けしているプロ集団の存在に気づいた。
清宮は彼らを斜め横から観察し続け、ある法則に則ってコインを多く出していることを発見した。
それを何度も見て、その仕組みを理解した。
ある日、東伏見にパチンコ屋がオープンした。
そしてそこに同じ機種のスロットマシンがあった。
以来、清宮は勝ち続けた。

「私は高校でも、高校日本代表でも、早稲田大学でもサントリーでもキャプテンになった。
しかし私は初対面の相手にとって非常にとっつきづらい相手らしい。
また下の選手への気配りも足りなかった。
ただキャプテンに選ばれた理由はごくシンプルで、いい意味でも悪い意味でも、清宮を真ん中に置いていないとチームが前に進まない。
清宮をキャプテンにしてないとうるさくてしょうがねえというなアクの強い存在だったからだ。
要するに下級生のころから練習やゲームを仕切りたがったというわけだ。
私が森島に勝っていたのはアクの強さだけだろう。
実際私は練習メニューでも戦術でも自分の思い描く理想と少しでも違っていると納得しなかった。
高校、大学を通じて納得できない指導や練習には監督に対しても上級生に対しても徹底的に質問し反論した。
不合理と感じることに対してはそれを明確にするためにものすごいエネルギーを使った。
先輩や監督に反抗し、無視して自分の納得できるラグビーをやった。
上級生に「走れ」といわれても面と向かって「いやだ」と言っていたし、目的のわからないこと、納得できないことに従うつもりはなかった。
また徒党を組もうとする集団に入るのも拒んだ。
普通だったら口に出せないことでも平気で上級生や監督に意見した。
反骨ではなく反抗といわれるかも知れないが、そういう気持ちはキャプテンになってからも変えなかった。
何かの練習をするときでも、キチンとその目的を説明され理解した上でなければ簡単に人の指示に従おうとは思わなかった。
特に運動部は根性論というか意味なく理不尽なことが起こる。
しかし私は理不尽なことには我慢せずやりあった。
何事も無批判に受け入れない自信、反骨精神、いまやっていることが正しいかどうか自問する力、そんな自己主張があった。」
清宮を主将とした早稲田大学ラグビー部は、全国大学選手権を優勝した。