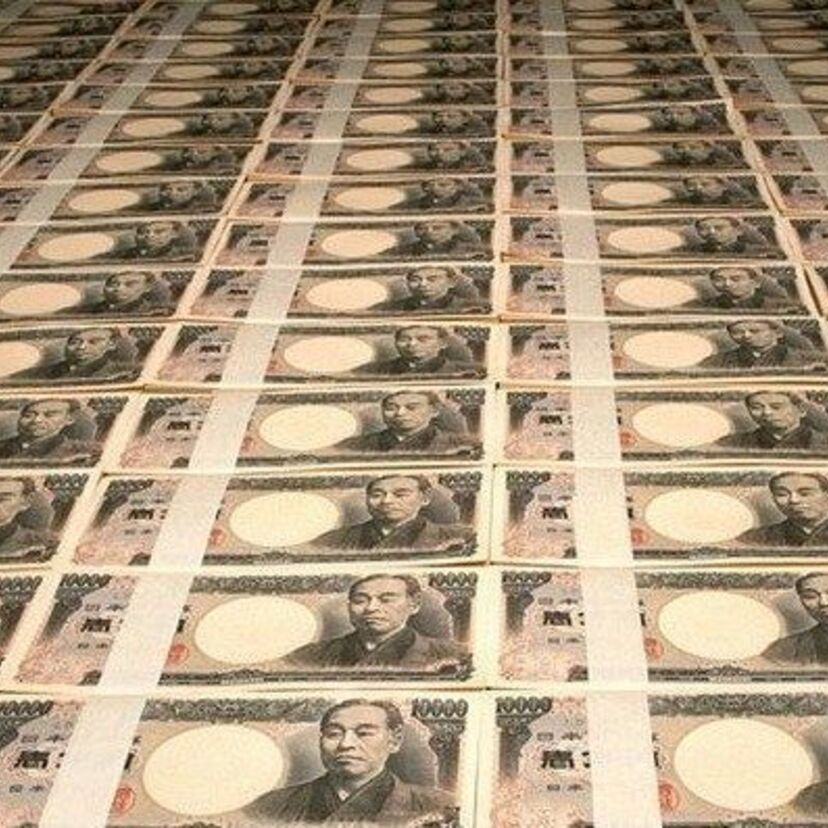『チューリップ・バブル』(チューリップ狂時代) ネーデルラント連邦共和国(オランダ)で1637年に起こった世界最初のバブル経済事件。

愛好家たちが絶賛したチューリップの高級品種「Semper Augustus」(「センペル・アウグストゥス」の日本語訳:「無窮の皇帝」)

チューリップ愛好家によるパンフレット(1637年出版) 高級品種の球根ひとつと邸宅が交換されることもあった。

1637年2月3日、チューリップ市場が突然暴落する
『南海泡沫事件』(なんかいほうまつじけん) 1720年にグレートブリテン王国(イギリス)で起こった投機ブームによる株価の急騰と暴落。

『南海泡沫事件』イングランド人画家エドワード・マシュー・ウォード(英語版)による作品

南海会社(1831年)

南海会社の株価推移
『ミシシッピ計画』(1720年代初頭)

スコットランドの実業家ジョン・ローがフランス領ルイジアナ植民地を巧みに宣伝する

インド会社の株券
『運河バブル(キャナル・マニア (英: Canal Mania、「運河狂」「運河熱」の意))』(1790年代)

イギリス最初の近代運河である「ブリッジウォーター運河」。1790年代前半には「運河熱(canal mania)」と呼ばれる投資ブームが発生した。

ブリッジウォーター運河(マンチェスター市内)