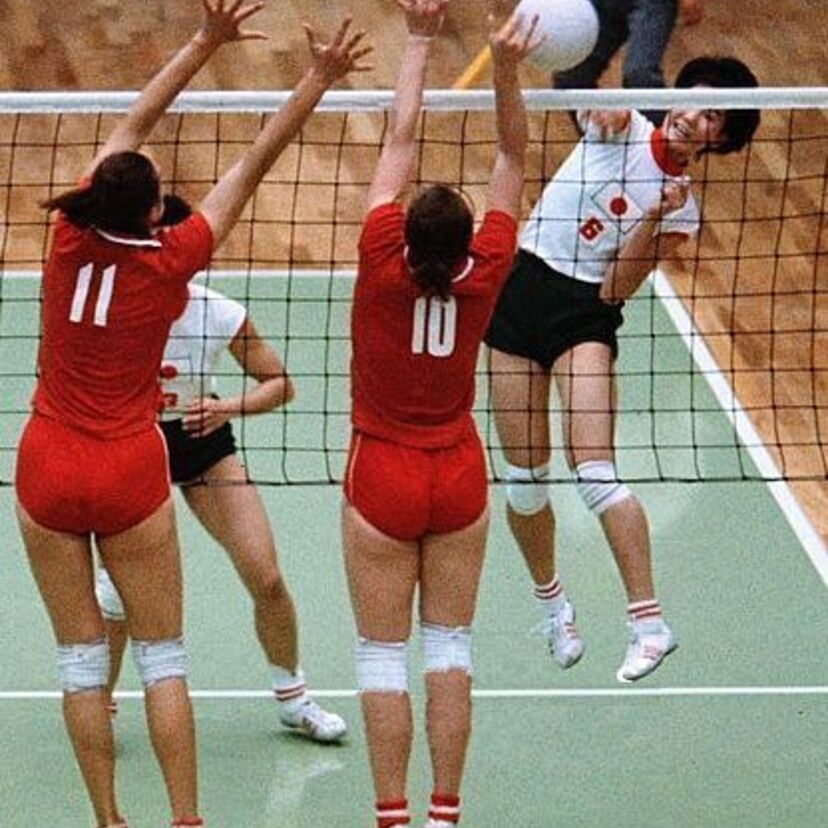全国的な小学校の建築ラッシュ!ひとりにひとつの机時代の幕開け!

憧れの超最新型の机「ホウトク学生机2型」(1963年)が徐々に普及し、ひとりにひとつの机時代の幕開け!

この当時は、木製の机が中心であり、二人用の机がザラだった。

同じ木製の机であっても、ひとり用なら、かなりマシであった。

この噂の最新型の机「ホウトク学生机2型」が全国に完全配備されるには、10年程度は必要であっただろう。
「隠密剣士」が忍者ブームの火付け役となり「忍者ブーム」が巻き起こる。「忍者部隊月光」「風のフジ丸」「サスケ」「伊賀の影丸」と続く。

「隠密剣士」(第二部 忍法甲賀衆・1963年1月6日)が忍者ブームの火付け役となり忍者ブームが巻き起こる。

「隠密剣士」が「水蜘蛛の術」を初めて映像化した作品とされている。

『忍者部隊月光』(1964年1月3日)

『少年忍者風のフジ丸』(1964年6月7日)

漫画『サスケ』

テレビアニメ『サスケ』

『伊賀の影丸』(1961年から1966年まで「週刊少年サンデー」に連載) 黒装束に鎖帷子を着るという忍者の視覚的イメージを確立した漫画である。

人形劇「伊賀の影丸」(TBS系・1963年11月5日から1964年11月3日まで)
NHK総合テレビで放送された人形劇『ひょっこりひょうたん島』(1964年4月6日 - 1969年4月4日) 放送当時子供たちの絶大な人気を得た。

NHK総合テレビで放送された人形劇『ひょっこりひょうたん島』(1964年4月6日 - 1969年4月4日)

『ひょっこりひょうたん島』 も最初は人気低迷、非難殺到。最初はさっぱり人気が出なかったんです。
特集記事から探す | NHKアーカイブス

『ひょっこりひょうたん島』の声優の収録