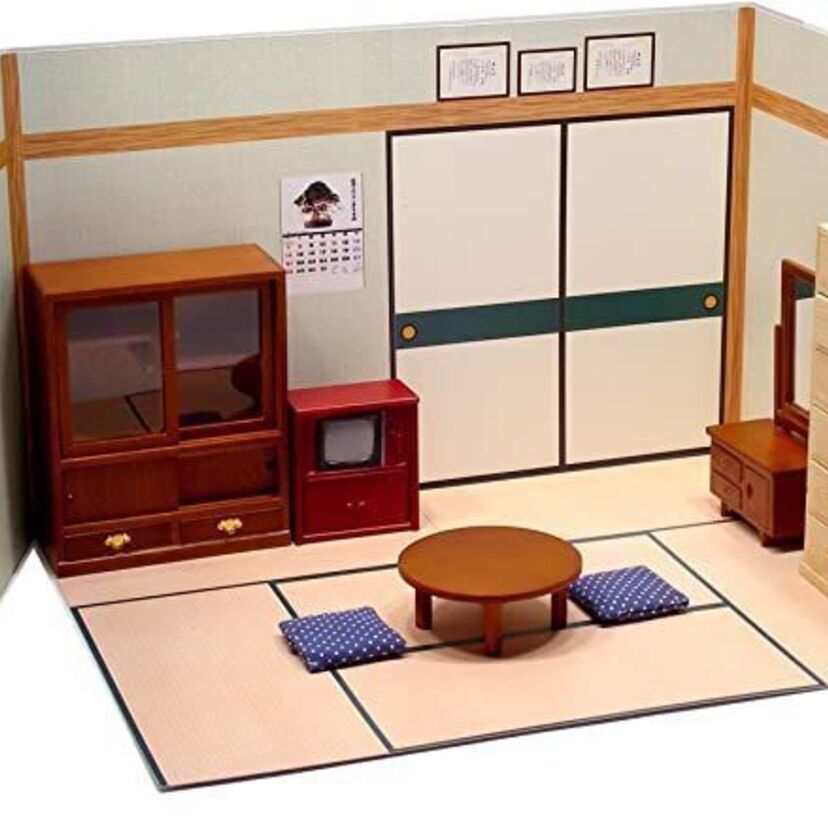吊り下げ式手洗いタンク

今ではトイレに手洗い蛇口は当たり前ですが、当時はトイレの小窓の外に手洗い水タンクがぶら下げてある家は多かったのではないでしょうか。
トイレは水洗ではなく、汲み取り式だったのでトイレの中に水道を通している家は少なく、トイレの汲み取り口付近に水道が引かれていましたね。
この手洗いタンクは、水を入れて屋外の好きなところに吊り下げることができます。
トイレの軒先に下げてあり、カランの軸を持ち上げれば水がポトポトっと水が落ちてきます。
掘りごたつの暖にもメザシを焼くのも「七輪」

電気こたつが普及する前は、掘りごたつが主流。
この掘りごたつの暖の元が、なんと七輪。
今思い出しても危険なものが居間の中心にありましたね。
この七輪に練炭(れんたん)や豆炭(まめたん)を入れて火を付け、掘りごたつの床の真ん中に設置します。床の真ん中に七輪が入るような穴がありましたね。
すぐにこたつの中が温かくなりませんが、じんわりほんわか温かい。
ですが、この練炭や豆炭は、石炭や低温コークスや亜炭や無煙炭や木炭などの粉を混ぜ、結着剤とともに成形した固形燃料。
火入れをしたら、だいたい一日もちました。
また、火力も一定に保つことができるので、調理器具としても重宝し、魚を焼いたり、煮物をしたりと活躍していました。
しかし、練炭や豆炭は一酸化炭素発生するので、屋外で使用することが限定なのです。
でも、掘りごたつに入れていたんですね。
定期的にこたつと部屋の換気が必要でしたが、この練炭で一酸化炭素中毒で亡くなる方は少なくなかったのです。

練炭
【楽天市場】【即日出荷】ミツウロコ マッチレンタン 14個入 練炭【お一人様1個まで】:セキチュー楽天市場店

豆炭
【楽天市場】【送料無料】【即日発送】エコロン炭 ECOLONGTAN 簡単着火 火持ち抜群(バーベキュー用炭1.8kg 着火用炭0.2kg)【キャンプ BBQ 豆炭 まめたん バーベキュー 炭 木炭 着火剤 固形燃料 アウトドア 七輪 練炭】:買援隊2号店
ガス炊飯器と保温ジャー

ガス炊飯器
楽天ビック|パロマ Paloma PR-6DSS 業務用ガス炊飯器 [3.3升 /プロパンガス][PR6DSSLP] 通販
今では、電気炊飯ジャーが主流ですが、当時はガス炊飯器でしたね。
このガス炊飯器は、手動式が1902年(明治35年)に開発されした。
その後、1957年(昭和32年)にガス自動炊飯器が開発され、1979年(昭和54年)になると電子ジャー(保温機能)付きガス炊飯器も登場したのです。
ガス炊飯器は保温ができないため、保温機能が付いた炊飯器が登場するまでは、保温ジャーなるものがありました。
ガス炊飯器でご飯を炊いたら、保温ジャーへ移し食卓へ。
この保温ジャーは、あくまでも炊いたご飯を保温するだけなのです。

保温ジャー
TYA-C18 象印 電子ジャー 1個 象印マホービン 【通販モノタロウ】 88819193
魔法瓶

炊飯器もそうでしたが、とにかく当時は保温できるものが開発され始めた時代ですね。
この魔法瓶もその一つ。
お湯が必要な時、いちいちヤカンで沸かすしかなかった時代に沸かし置きができる画期的な器具です。
保温性を高めるため内びんと外びんの二重構造でその間を真空状態にすることで長時間にわたり保温できるようになっています。
蚊帳

このワンタッチ蚊帳が登場するや、どこの家庭でもほぼ使われていたのではないでしょうか。
食卓の準備をしているとハエなどの害虫が飛んできて、追い払うのに手間を取っていました。
しかし、紐を引っ張るだけで傘のように広がる小型の蚊帳の登場で、食品を衛生的に保護することができるようになったのです。
蠅取り紙