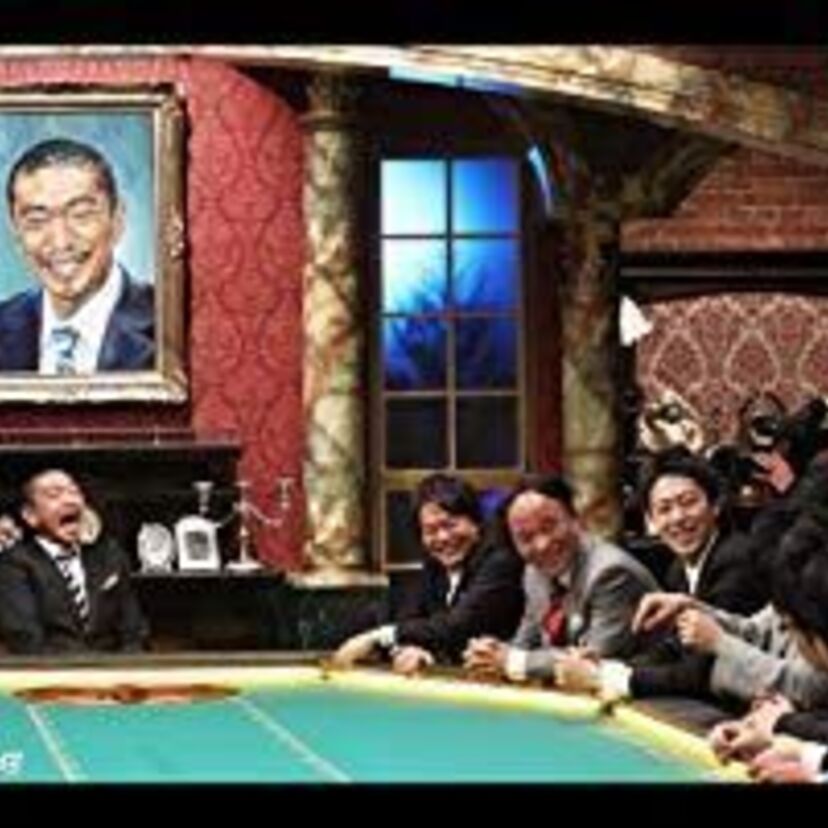元々はお笑いが「演芸」「漫才」の順でムーブメントとなり、その次にテレビで一大ブームを巻き起こした流れを差して、当時のテレビで活躍していた世代を「お笑い第三世代」と称したことから始まっているようです。
従って「演芸=第一世代」「漫才=第二世代」は後付け、第四世代以降については曖昧(第三世代が中心のまま裾野が広がっていったようにも見える)で、ただ単に芸人さんたちのデビュー時期で括っているようにも見えます。
もしかすると「テレビ全盛期のお笑い=第三世代」と一纏めにして「ネット(youtuber)=第四世代」の方が、後世には分かりやすいのかもしれませんね。
お笑い第一世代
1962年頃から1969年頃まで続いた、テレビの演芸番組を中心としたブーム。
景気後退の中、番組制作費が抑制された各局は制作コストがかからず視聴率が取れる演芸番組に傾斜。また、視聴者の側も不景気による沈滞ムードの中、テレビに笑いを求めていました。
代表的な番組
多くの人にとっては「笑点」くらいしか分からないかもしれません。
笑点は第一世代からずっと続いている唯一の番組ということになりますね。
代表的なタレント
超がつくほどの大御所たちの名がズラリと並びます。
すでにお亡くなりになった方も多いですが、この方たちが50年以上前に「お笑い」を日本社会に届けていたのですね。
歴代の笑点司会者の経歴をプレイバック - Middle Edge(ミドルエッジ)
お笑い第二世代
1979年から1982年頃まで続いた、テレビの演芸番組を中心としたブーム。
演芸ブームの後、コント55号やザ・ドリフターズの2強時代となり、彼らがけん引する形で東京発のバラエティー番組がお笑いの主流を占めていました。
大阪では演芸ブーム以降に吉本興業の漫才師が台頭し、特に若者に人気の高かった中田カウス・ボタンを筆頭に笑いの潮流が吉本側に傾きつつあったものの、全国向けの関西演芸はかしまし娘やレツゴー三匹などが松竹芸能の力が強い時代でした。
1979年になると澤田隆治、横澤彪といったテレビマン達によって、当時は寄席演芸の色物(傍流)だった漫才がテレビのメインコンテンツに躍り出ました。これを機に当時の若手上方漫才師達は一躍時代の寵児となり、笑いが流行の最先端となりました。
東京においては小劇場やライブ・スペースを活動拠点にした笑いのストリームが生まれつつありました。また自身でネタを構成する芸人や、深夜放送のハガキ職人出身の放送作家の増加に伴い、若者うけのよい、スピーディーで毒や刺激の強いお笑いが増えていくことに。
また当時は若手の女芸人が少なかったこともあり、芸歴で言えばお笑い三世代に属する山田邦子が新人ながらいきなりブレイク、1つ上の第二世代に混じって台頭していきました。
代表的な番組
「第二世代=漫才」と定義すると上記のような番組となりますよね。
ただ、ここにはあがっていませんでしたが「8時だよ全員集合」や「オレたちひょうきん族」などもこの世代に入ってくるのだと思います。
代表的なタレント
「お笑いビッグ3」や志村けんなど、いまもテレビ番組で大御所として活躍する世代がこの第二世代でしょうね。