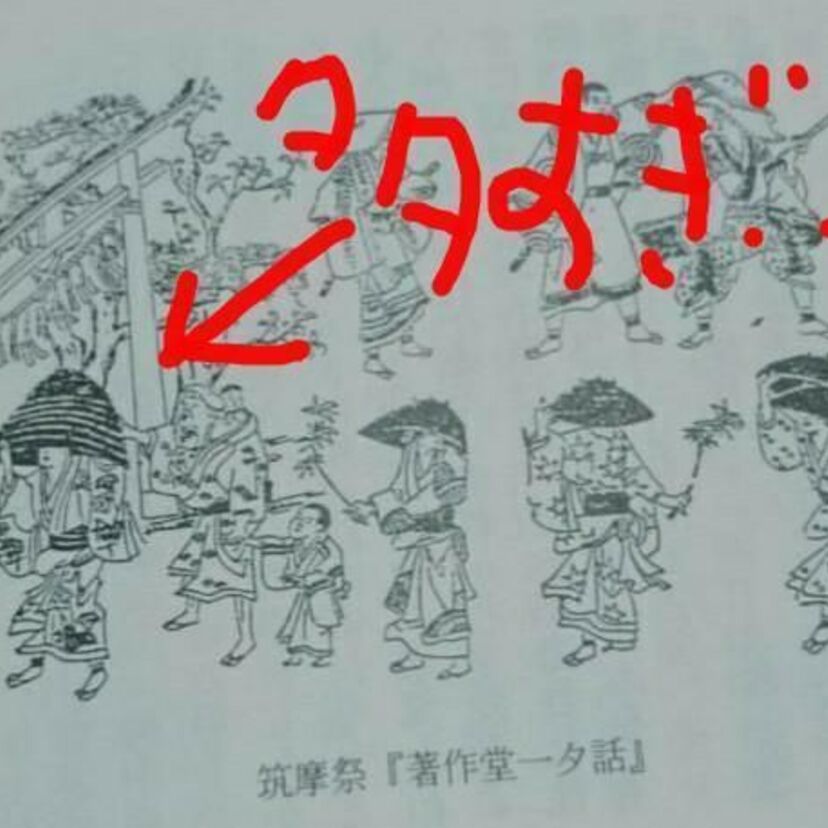まず、今現在目の前で起きている西日本を中心とした豪雨被害で大変な環境におかれている皆様へ自分が出来る支援を、そして亡くなられた方へ心からお悔やみ申し上げます。
防災メディアサイト「防災テック」さんに“日本は国土の75%が山地であると言われており、そのために川は標高の高い部分から標高の低い部分への距離が短くて、他の国に比べると流れが急であると言われています。
オランダ人のデ・レーケが日本の川を見て「これは川ではない。滝だ!」というセリフを残したことは有名ですが、そのために洪水や土砂災害などといった災害が発生しやすい特性を持っているとも言えます。”とありますように、どの地域で暮らしていても災害は起こりえます。他人事ではなく自分事として、大変な時は支えあいと思う自分です。
今回は、今は無き奇祭を紹介
そんな中、日本は夏。夏祭りの季節を迎えます。夏といえば祭。花火も盆踊りも浴衣も、皆で楽しむ季節です。
では祭とは。「まつり」という言葉に該当する漢字が意外と多い。「祭り」・「奉り」・「祀り」・「政り」・「纏り」。現在の日本は政教分離の原則がありますが、古代においては政教は一体だったため、政治の「政」も祭礼の「祭」もおなじ音だったのだ・・・という感じで捉えていただけたらと思います。
このあたりは機会があれば書かせていただくとして・・・祭をメディアさんが取り上げる場合、「面白い」「珍しい」「有名」などの切り口が多いかと思いましたので、今回は、今は無き奇祭をご紹介します。祭自体はあるんですが、祭の中身が今はもう行えない内容なんです。
今はもう行えない内容??
それは5月の「鍋冠祭(なべかぶりまつり)」。滋賀件米原市の筑摩神社に伝わる祭です。
筑摩神社は社伝によると考安天皇28年(西暦142年)スタートという古さを誇ります。この天皇は第六代天皇さんでして、位102年という歴代天皇で最長の記録をもつ天皇です。137歳まで生きたとか『日本書紀』に書かれていたりして色々疑問視されている存在ではありますが、それはそれとしておきます。さておき一気に時代を近づけて江戸時代では、この神社は彦根藩井伊氏からも信仰されておりますので、歴史好きな方にはオススメな神社です。
さてこの神社に伝わる鍋冠祭。筑摩祭とも言います。というか、そも筑摩祭です。この祭礼に登場する数え年8歳頃の女の子8人が鍋を被っていることから「鍋冠祭」と言われているのです。この鍋も、社伝によると1200年以上の歴史がありまして、この筑摩神社の主祭神「御食津神(ミケツカミ)」が食物を司る神であることから、神前に供物と合わせて鍋も捧げたことに由来するそうです。
関係した男性の人数だけ鍋を頭に被る?
現在の筑摩祭では女の子が頭に鍋を被って歩いており、それはそれで奇祭ではありますが、その昔は女の子が被ってはいませんでした。ここが奇祭の「奇」たるところ。被るだけでなく、被る理由と被る枚数がまさに日本唯一。いや、世界唯一かもしれない。
平安初期の歌物語『伊勢物語』に
と、あります。歌の部分だけ大雑把に現代語に約しますと「近江の筑摩神社の祭をすぐにしましょう。男女関係なんて興味が無いという感じの女が何個の鍋を頭にかぶってるか見ようじゃないですか」です。
実はですね、この祭・・・昔は女が関係した男性の人数だけ鍋を頭に被って、それを神に奉納していたんです。関係した男性の人数をごまかすと神の怒りにふれ、鍋が頭から落ちて割れたとか。
わざわざ平安時代の書物に書かれるくらいですから、当時はかなり有名なお祭。この風習は江戸時代まで引き継がれて江戸時代の書物にも登場します。川柳にも歌われており、例えば「鍋かぶる明日の祭が嫁頭痛」など。夫婦の仲に亀裂が入ったかどうか気になるところです。「筑摩祭」は俳句の初夏の季語にもなっておりますので、江戸時代にも有名だったんだろなあ・・・と思わずにはおれません。

とはいえ天保3年(1832年)あたりには現在のように少女が鍋を被るスタイルになっていたそうです(『大日本年中行事大全』より)。ここに彦根藩・井伊氏が関わっております。
ある時の筑摩祭でわざと数を少なめにして鍋を被った女性の鍋が落ちたことをまわりの皆が笑ったので、その女性が池にとびこんで自殺するという事件があり、時の彦根藩主が現在の8歳前後の少女が1つの鍋を被るスタイルに変更したからです。藩主ジャッジで今のスタイルに~。
それにしても、よくこんなルール作ったなあ・・・と思わずにはいられない祭です。
現代社会では絶対不可能でしょうね。ちなみにこの祭、米原市指定無形民俗文化財です。そう、地域の歴史を伝える文化財ですので、ぜひ、ぜひ!
鍋冠祭保存会のホームページにようこそ