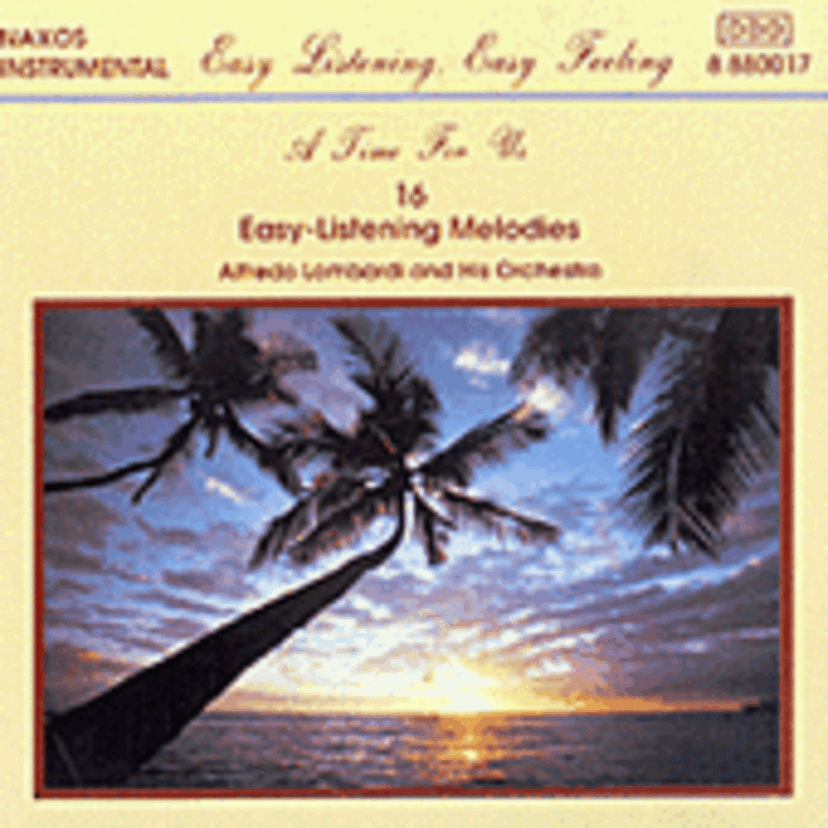イージー・リスニング(Easy Listening)って、どんな音楽なの??

イージーリスニングのディスク・コレクション
イージー・リスニング(Easy Listening)音楽は”ムード”音楽から派生した!!
ヌードではなく”ムード”音楽の定義をすると??
ムード音楽の定義は音楽評論家の中でも見解が割れているようです。多くはオーケストラの形態をとり、かつ、演奏のみであるが、一部のアルバムに見られるようにコーラスに歌詞を歌わせる形態の物もあります。
ポピュラー音楽の中で、管弦楽器などを中心とした情緒豊かなインストゥルメンタルポップスというのが一般的である。広義的には、映画音楽、ラテン音楽をも包含する概念を表します。
ムード音楽というジャンルを広げた初期のアーティストには、”マスター・オブ・ムード・ミュージック”と呼ばれる、ポール・ウエストンを初め、ジャッキー・グリースン、ローレンス・ウエルクなどがおり、日本では特に、パーシー・フェイスやマントヴァーニなどに絶大な人気がありました。
しかし、ポール・ウエストンよりもずっと前から「ムード・ミュージック」という言葉を使っているアーティストが何名かいることがわかっています。
その一人はモートン・グールド。彼が自身のレコード・アルバムのタイトルに「ムード・ミュージック」という言葉を副題として使ったのが、おそらく最初か、あるいは本当に僅差で最初から数番目であると思われます。
モートン・グールド(Morton Goulld)は、テレビ朝日系列『日曜洋画劇場』の初代エンディング・テーマに使用されていたコール・ポーター作曲の「So In Love (ソー・イン・ラヴ)」(ピアノは彼によるもの)を吹き込んだアーティストです。
その他に、ロジャー・ウイリアムス、フランク・チャックスフィールド・オーケストラ、ヘンリー・マンシーニ・オーケストラなどが挙げられる。
ムード音楽からイージー・リスニング音楽へ
ムード音楽全盛時の特徴としては映画音楽としてヒットしたものが多かったことと、イギリスやアメリカのオーケストラが人気の中心であったことが挙げられます。しかし、60年代中頃になると、フランスのオーケストラの台頭が著しくなります。フランスのオーケストラは、当時流行していた8ビートのリズムなどポピュラーやロックの要素を取り入れたサウンドが特徴で、 従来の管弦楽器を中心とした編成ではなく、ブラス群やドラムス等を加えた編成であることから〝グランド・オーケストラ〟と呼ばれました。 主に知られているのが、ポール・モーリア・グランド・オーケストラ、レイモン・ルフェーヴル・グランド・オーケストラ、フランク・プゥルセル・グランド・オーケストラ、カラベリ・グランド・オーケストラという4大グランド・オーケストラでした。これらのオーケストラは、スタンダード、ワールド・ヒッツ、シャンソン、カンツォーネからクラシックまでに独自のアレンジを施して 演奏したアルバムを次々に発表し、特に日本では70年代中頃にかけて爆発的な人気となりました。 この”グランド・オーケストラ”の台頭により、ムード音楽はイージーリスニングと呼ばれるようになったとされています。