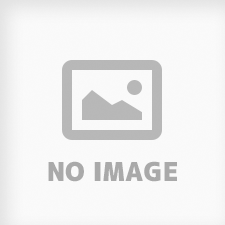琴櫻の土俵入り
琴櫻 傑將(ことざくら まさかつ)
佐渡ヶ嶽部屋入門まで
琴櫻傑將 - Wikipedia

若い頃の琴櫻
大関までは順調な道程であった。
最初はどうしても柔道の癖が取り口に表れていたが、指導と琴ヶ濱との稽古で右四つの型を会得すると、1962年7月場所に十両へ昇進し、優勝。4場所目の1963年1月場所でも十両優勝を果たして3月場所に新入幕を果たした。1964年1月場所には新三役の場所6日目に、柏戸剛との取組で土俵上で足首を骨折する負傷で途中休場。翌場所も全休したため、十両まで陥落の憂き目に遭った。
休場して以降は本人曰く「まわしを取ると青竹で殴られた」、「いつまでも腫れが引かない」という厳しい指導の下に己の相撲を改造し、怒濤の突き押し・強烈なぶちかましとのど輪で一気に攻める押し相撲を得意とし、「猛牛」と異名を取った。1967年9月場所では柏戸と佐田の山・豊山・北の富士と2横綱2大関を倒して11勝4敗という成績を残し、場所後に大関へ昇進した。1968年7月場所には13勝2敗の成績で幕内初優勝を果たした。
初土俵が1959年1月場所だから、大関までは8年半ほど掛かった計算になる訳ですが、他の力士たちの記録と比べても遜色ない速さである。
四股名の由来
琴櫻が入門していた佐渡ヶ嶽部屋では、昔より四股名の始まりの一字に”琴”を付けている。現在でも、大関”琴奨菊”関や平幕の”琴勇輝”関が在籍しているが、このような風習が未だに健在である。これは11代佐渡ヶ嶽(琴錦)の故郷である香川県観音寺市にある琴弾八幡宮に由来している。琴光喜が初土俵時に名乗った琴田宮など、本名で土俵に上がる場合でも本名の前に「琴」の字を付けて四股名を作ることが通例である。また、琴という字は「今に王になる」字だと横綱琴桜が言っていたという記事がある。
琴櫻本人は番付に初めて載った時は本名の「鎌谷」だったが、関取昇進時に「琴櫻」へ改名した。これは11代佐渡ヶ嶽師匠の現役名「琴錦」に、故郷にある「打吹公園」が桜の名所であることから付けられたもの。番付では琴櫻と書かれ、“琴桜”と書かれたものは存在しないが、本人はサインなどでは「琴桜」と書いていたという。
ダメ大関と呼ばれた者でも横綱に昇進した典型的な例!!
この頃の相撲で優勝した”豪栄道”や”琴奨菊”を見ていると歯がゆい思いをした方々がかなりに上るのではと思っています。優勝した翌場所は必ずと言って良いほど、惨憺たる結果に終わっているからだ。2場所連続優勝・横綱昇進というプレッシャーは、それだけ大きいのであろう。そんな現在の状況によく似た時期が過去にもあった。
過去にもダメ大関と呼ばれた者でも横綱に昇進した例はある。その最たる力士が琴櫻である。大関在位32場所で優勝5回とはいえ、2ケタ勝ったのは半数にも満たない15場所。ケガも多く、当時から「ポンコツ」「ウバ桜」などと揶揄されていた。それが現役最晩年の72年に悲願達成。32歳2カ月での横綱昇進は年6場所制以降の最年長記録として、いまも破られていない。
これはまるで、今までうんともすんとも言わなかったパチンコ台がある時、急に「確変」に突入しフィーバーするようなものだ。
琴櫻の時代は大横綱大鵬が引退、後継者たる玉ノ海も急死し、北の富士はいるものの、時代の転換期だった。
琴櫻傑將 - Wikipedia
引退後も精力的に活動!!
琴櫻傑將 - Wikipedia

晩年の琴櫻