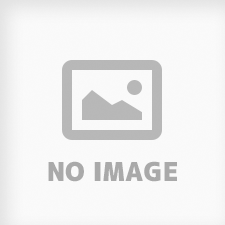任天堂最大のライバル!セガのハード機と代表作を振り返る
今や家庭用ゲームハード機は、任天堂、SONY、マイクロソフトの3強時代となっていますが、その昔、ファミコンを出し、天下を取っていた任天堂の座を脅かす最大のライバルと言えば、セガだった。そこで、1990年代までのセガのハード機と代表作を振り返っていきましょう。

SC-3000

1983年に日本で販売開始したセガの記念すべき家庭用ハード1号機。BASIC言語によるプログラミングなどゲームだけでなく、限りなく初期型のコンピューターの意味合いもあった。価格は29800円。
SC-3000 - Wikipedia
CM
ピットフォールⅡ
SG-1000III (通称マークⅢ)

上記のSC-3000との互換性や、豊富な発色数など、ライバルのファミコンを上回る性能で、マニアを虜にしていました。サードパーティーの参入を早めるなど。ソフト数の充実を図る事ができれば、ファミコンではなく天下を取っていたかもしれません。
セガ・マークIII - Wikipedia