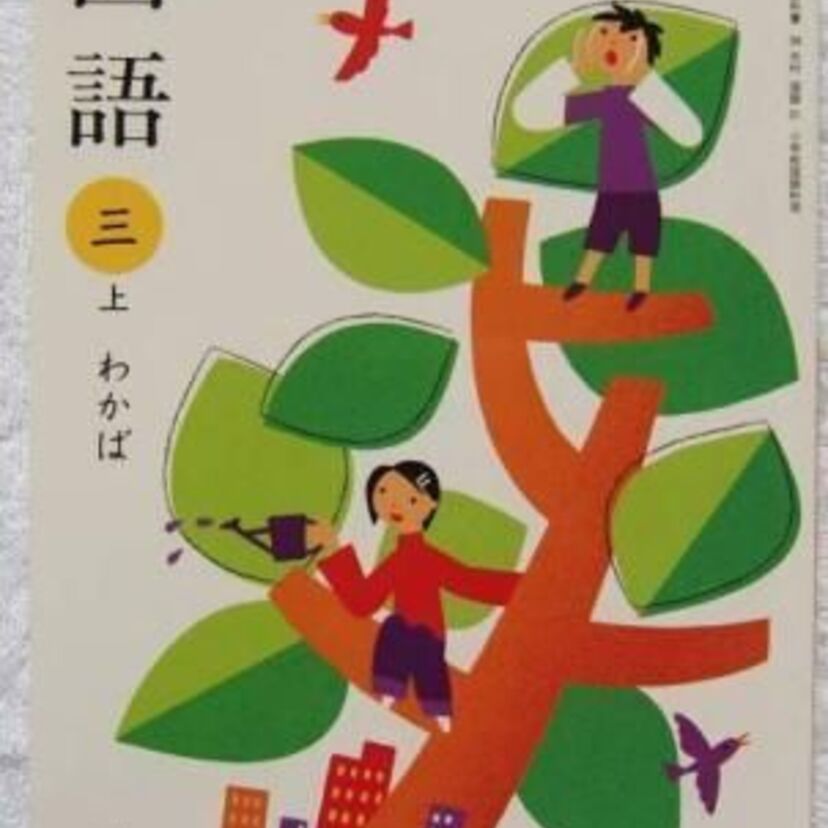「光村図書出版」と聞くと思わず懐かしい気持ちになりませんか?
「どこかできいた…」?そうです、教科書の出版社、特に国語は光村図書の教科書を使っている学校が多いです。三輪民子さんの「平成 23 年度版小学校国語教科書検討」によると、光村のシェアは60%だそうです。「教科書の思い出」を共有しやすいのもうなずけます。
さて、その光村の小学校の国語の教科書、習っている当時はなんの気なしに読んでいたと思いますが、改めて振り返ってみるとすごい執筆陣なのです。
この記事では「文芸編」「挿絵編」と分けて光村の国語の教科書って意外とすごいことをご紹介したいと思います
光村図書の国語の教科書は凄かったんだ!【挿絵編】
■日本の歌謡曲の大御所が書いた「ガラスの小びん」
6年生の教科書に掲載された「ガラスの小びん」の作者は阿久悠さんです。
そう、日本を代表する作詞家、レコード大賞受賞曲を何度も受賞され、日本の歌謡曲の隆盛期を支えたお一人です。
「ガラスの小びん」

阿久悠
「ガラスの小びん」は教科書のための書き下ろしです。
一時期、歌謡曲は子供には聞かせてはいけないもの、と言われていました。その歌謡曲の作詞家が、日本の小学生の教科書用に書き下ろすなんて…まさに歌謡曲の底上げを図ってくれた方なのですね。
■「キャンディ・キャンディ」の原作者!「赤い実はじけた」
新学期が始まると、教科書に名前を書きますよね。保護者の方もお手伝いしたことはあると思うのですが、この「名木田恵子」の名前をみて驚かれた方もいらっしゃるのでは…

名木田恵子
別名に「水木杏子」とありますが、これは名作少女漫画・アニメの「キャンディ・キャンディ」の原作者の方。つまり、「名木田恵子=水木杏子」、つまり、この「赤い実はじけた」を書いた方は「キャンディ・キャンディ」の原作者なのです!
「赤い実はじけた」が掲載されていたころ、そのお子さんのお母さんは「キャンディ」の直撃世代だったはず。
当時「なかよし」にも「水木杏子(本名・名木田恵子)と書かれてたのでわかる人はわかると思うのですが…気づいた方、いらっしゃいましたか?

■テレビドラマ脚本家の第一人者が書いた!「映像を見る目」
ミドルエッジ読者の皆様なら「岸辺のアルバム」「思い出づくり」「ふぞろいの林檎たち」は忘れらない作品として挙げられると思いますが、それらを書いた脚本家・山田太一さんも教科書に書き下ろしています。

「映像を見る目」

山田太一
「映像を見る目」は5年生の教科書に昭和61年から掲載されていますから、当時の5年生は昭和50年生まれ。
山田太一さんはがっつりその頃から大活躍されていましたよね。