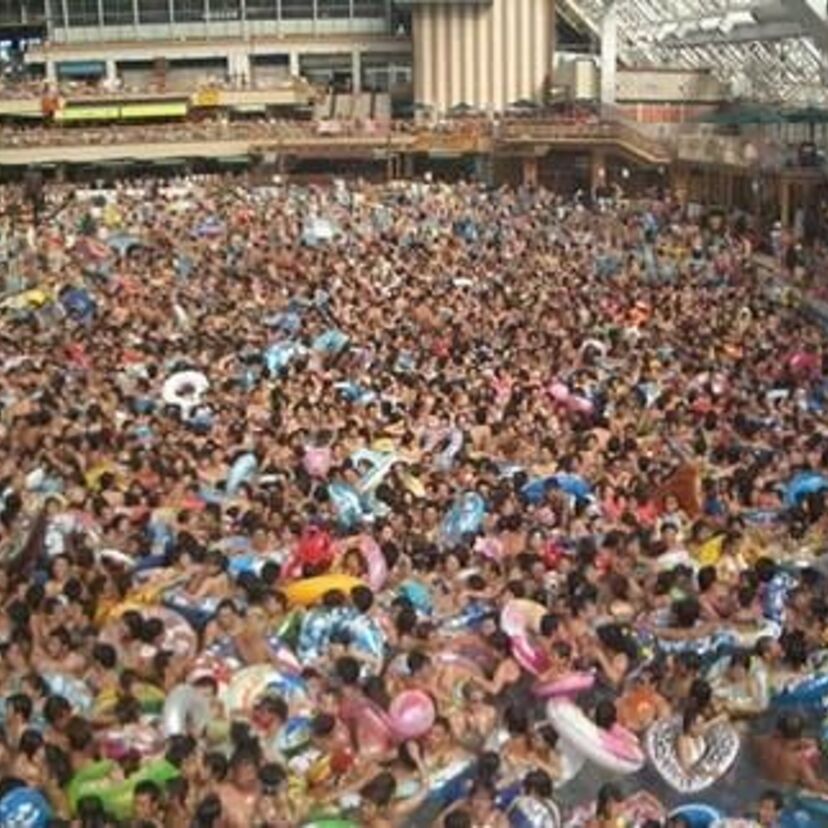夏休みの「おうちドリンク」と「デザート」
かき氷機「きょろちゃん」(タイガー魔法瓶)

みらい「かき氷には、メロンにレモン、ブルーハワイ、宇治金時、イチゴメロンと、様々な味がある」 ことはは「食べてみたい・・・」と心躍らせます。

かき氷機「初代きょろちゃん」(タイガー魔法瓶)

歴代人気ナンバーワンの三代目「きょろちゃん」

ロングセラーの明治屋「マイシロップ」(1950年発売)

ロングセラーの井村屋「氷みつ」(1967年)

森永ミルクの練乳もお好みで加えればバッチリ。

妖精だった頃(小さい頃のはーちゃん)に食べた時、カキ氷はとても甘くて美味しかった事を、ことはは思い出しました。
おうちアイスの大定番「シャービック」(ハウス食品)、プリンとゼリーの素

おうちアイスの大定番「シャービック」(ハウス食品) 1968年の発売以来、今も愛される大定番のおうちアイス。

「アイスペロン」 おうちアイスの「シャービック」がアイスキャンディー状に仕上がる「アイスペロン」という容器も大変人気があった。

おうちアイスの「シャービック」がアイスキャンディー状に仕上がる「アイスペロン」

ハウス食品「プリンミクス」

ライオン「ママプリン」

ハウス食品「ゼリエース」 なんともラグジャリーだった。

ハウス食品「フルーチェ」 独特のプルプル感がたまらない!クセになるロングセラー!
夏の渇きを癒してくれた「おうちドリンク」の大定番は「麦茶」

売上げナンバーワンを誇っていたヒタチヤ(常陸屋本舗)「江戸麦茶」

石垣食品「フジミネラル麦茶」