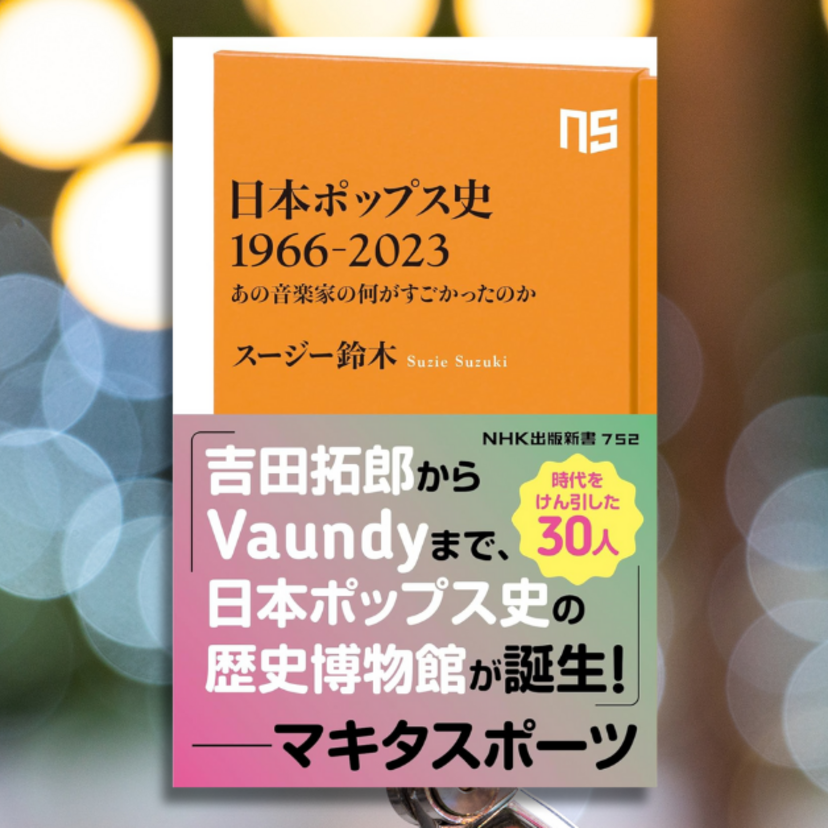音楽通史の決定版!スージー鈴木が描く「日本ポップス史」の全体像
日本の大衆音楽、特にロック、フォーク、ニューミュージックといった「ポップ音楽」の歴史を、多角的な視点から体系的にまとめ上げた一冊が、NHK出版より発売されました。音楽評論家・ラジオDJ・作家として活躍するスージー鈴木氏による新刊『日本ポップス史 1966-2023 あの音楽家の何がすごかったのか』です。
2025年11月10日に発売されたこの書籍は、日本の大衆音楽史におけるレジェンド音楽家たちが「何を成し遂げたのか」、そして「何を誰に継いだのか」という一本の軸を通し、その全体像を知るための「決定版の見取り図」となることを目指しています。

「作品性」に留まらない独自の「通史」
本書の特徴は、従来の音楽評論が陥りがちな「作品性」のみに傾倒するのではなく、「あの音楽家がいちばんすごかった時代」と「あの時代にいちばんすごかった音楽家」という2つのユニークな視点から、「時代性」、ひいては「大衆性(≒セールス)」までをしっかりと捕捉している点にあります。このスージー鈴木氏独自の「通史」的手法によって、各時代で「てっぺん」を取った音楽家の功績が、より立体的かつリアルに浮かび上がります。
1966年の「かまやつひろし」から始まり、現代の「Vaundy」に至るまで、約60年にわたる日本のポップス史を、レジェンドたちが築いた系譜として再構築しています。
時代を彩ったレジェンドたちの「すごさ」を徹底考察
本書は、以下の3つの時代区分に分けて、それぞれの時代で重要な役割を果たした音楽家たちを詳細に考察しています。
【第1章:1966-1979】
日本のポップス史の土台が築かれた黎明期。GS、フォーク、ニューミュージックが混ざり合う時代です。
1966年のかまやつひろし、1968年の加藤和彦: ポップスの源流と先進性。
1972年の吉田拓郎、財津和夫: フォークからニューミュージックへ、時代の旗手たち。
1973年の井上陽水、1974年の荒井由実: 歌謡曲とは一線を画す独自の感性。
1978年の桑田佳祐: サザンオールスターズとして、時代の「てっぺん」を塗り替えた大衆性。
特に、吉田拓郎(1972年)は、フォークを大衆に広く浸透させ、その後の日本のポップスに絶大な影響を与えた存在として、序章でも深く掘り下げられています。
【第2章:1980-1994】
ロックの台頭、テクノロジーの進化、そしてバブル経済がもたらした、豊かで多様な音楽が花開いた時代です。
1981年の大滝詠一、1982年の山下達郎: 洗練されたシティポップの確立と、その後の影響。
1986年の氷室京介と布袋寅泰(BOØWY): ロックバンドが時代を席巻する流れを作り上げた功績。
1993年の小室哲哉: 時代を象徴するプロデューサーとして、ミリオンヒットを連発した「大衆性」の極致。
1994年の小沢健二: J-POPシーンに新たな風を吹き込んだ独自性。
【第3章:2016-2023】
インターネット、サブスクリプションが普及し、音楽の聴き方が大きく変わった現代のポップスシーンです。
2016年の宇多田ヒカル: 変わらぬ作品性と、時代の変化への対応力。
2018年の米津玄師: デジタル時代における圧倒的な存在感とクリエイティブ。
2023年のVaundy: 最新のヒットメーカーとして、次の時代を担う存在。
これらの音楽家たちの「何がすごかったのか」を、その当時の社会的背景や音楽シーンの構造と結びつけて解説しており、音楽ファンはもちろん、日本のカルチャーに関心があるすべての人にとって、新たな発見に満ちた一冊となっています。
本書は、日本のポップス史全体を俯瞰したい時の「最初の1冊」として、また、熱心な音楽ファンが自身の知識を体系化するための「決定版」として、手元に置いておきたい必携の書と言えるでしょう。
【書籍情報】
タイトル: NHK出版新書752『日本ポップス史 1966‒2023 あの音楽家の何がすごかったのか』
著者: スージー鈴木
発売日: 2025年11月10日
定価: 1,133円(税込)
判型: 新書判 288ページ
ISBN: 978-4-14-088752-3
出版社: 株式会社NHK出版