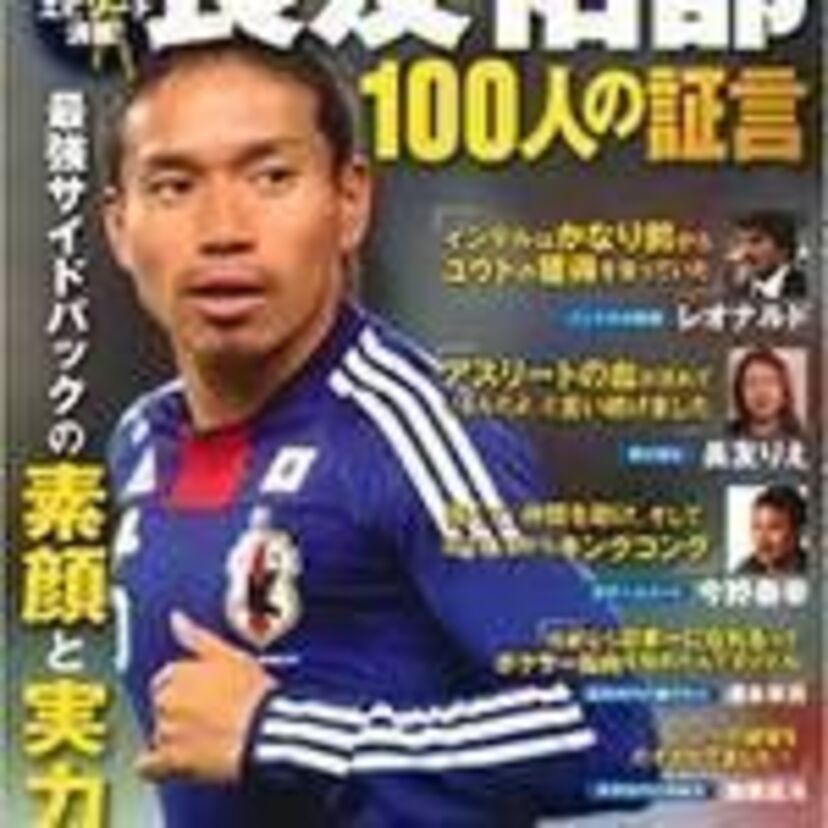ガキ大将で王様

長友佑都は、1986年9月12日に愛媛県東予市(現:西条市)三芳で新聞配達店を営む裕福な家に生まれた。
体は小さかったが,運動では誰にも負けず
「俺に逆らったら許さんぞ」
というようなガキ大将だった。
幼稚園に入ると地元のアイドル的な女子がいて長友佑都も好きになった。
なんとか振り向かせたい。
「長友君、かっこええわ」
といわせたい。
長友佑都は自分のすごさを見せつけるためにサッカーを始めた。
小学生になった頃、Jリーグが始まり、ゴールを決めてカズダンスを踊る三浦知良に憧れた。
「めっちゃカッコええやん」
長友佑都はボールを持ったら基本的に離さない。
ドリブルで相手ゴールに向かい、相手ディフェンダーも勝負を仕掛けた。
ある試合では自陣からドリブルをはじめ、次々と相手をかわし、そのままゴールを決めた。
そして最高の気分に浸った。
このように完全に王様状態だったが、小学校3年生のときに1年生の弟:宏次朗がサッカースクールに入ってくると一転した。
兄はドリブル一辺倒だったが、宏次朗はボールコントロールやパスセンスも持っていた。
「長友兄弟は佑都もうまいけど弟の方が才能がある」
指導者の評価を聞いてショックを受けた。
その後、兄はフォワード、弟は中盤として一緒に試合に出たが
「宏次朗!なんでパス出さへんねん」
と試合中に怒った兄がボールではなく逃げる弟を追い回すこともあった。
弟の才能に怒り狂う長友佑都は、すでに王様ではなく(北斗の拳の)ジャギだった。

「これから母さんと麻歩と佑都と宏次朗の4人で生きていくことになったから」
地元の高校の先輩後輩だった両親が離婚。
母親は子供と共に実家がある西条市に引っ越した。
新しい家は、母親の実家の近所で、前の家より古くて小さかった。
母親は、結婚式や葬式の司会の仕事をした。
(そして3人の子供を大学へ進学させた)
以前も新聞配達店を手伝っていたが、比べ物にら七位ほど忙しくなった。
朝早く家を出て遅く帰宅するので、子供たちの夜ゴハンは、コンビニ弁当かおじいちゃんの家だった。
「こんなんイヤや。
学校にやめてっていうて」
転向した小学校で生徒名簿をみてみると、ほかの子は保護者の欄が父親の名前だったがが、長友佑都だけが母親の名前だった。
長友佑都は、それを恥ずかしがり、母親は学校に頼んで父親の名前に変えてもらった。
長友佑都は母子家庭であることを知られるのを嫌った。
恥ずかしさもあったが、何よりも
「お母さんだけで大変やねえ」
「お母さん、仕事でいないのに偉いね」
と同級生の親に同情されるのが嫌だった。
「なんでこんなボロい家に住まなアカンねん」
長友佑都は父親に対して憎しみのような嫌悪感を持った。

転校後もサッカーは続けた。
ボールを追っているときは嫌なことを忘れることができた。
小学生5年生のとき、テレビでワールドカップフランス大会をみた。
日本代表は初戦でアルゼンチンと対戦。
一瞬のスキをついて決めたガルリエル・バティストゥータのゴールが衝撃的だった。
「世界には凄い選手がおるんや!」
愛媛県でサッカーの頂点は、「愛媛FC(フットボールクラブ)」だった。
社会人チームだけでなく、高校生、中学生のチームを持つサッカークラブで、愛媛県の優秀な小学生はみんな愛媛FCジュニアユース(中学生以下)に集まっていた。
長友佑都も愛媛FC憧れていた。
「愛媛FCに行かへんかったら先はない」
とさえ思っていた。
自信はあったが、もし落ちると恥ずかしいので、神拝サッカースクールの監督と母親以外には内緒で、セレクションテストを受けるために特急列車で1時間かけて愛媛FCのある松山市にいった。
「じゃあ長友君、一緒にやってみて」
ジュニアユースチームの練習に参加することがテストだったが、それほど差を感じることもなく練習は終わった。
(やれるやん)
(受かった)
合格を確信して西条市に戻り
「愛媛FCに行くんや」
と周囲に早くいいたくてウズウズ、ワクワクしながら過ごしていたが、松山市から届いたハガキには
「不合格」
と記してあった。
悲しすぎて涙も出なかった。
リアルスクールウォーズ 西条北中学サッカー部

西条北中学でもサッカー部に入った。
しかしそこは不良のたまり場だった。
ボンタン、長ラン、短ランを着た先輩がそろっていた。
部室にはエロ本が散乱し、放課後、練習する部員はわずかで、ほとんどは繁華街に消えていった。
それをみた長友佑都は12歳にして
「俺のサッカー人生は終わった」
と思った。
そして自分も授業が終わるとグラウンドを抜け、ゲームセンターや友達の家にいって遊んだ。
自宅もたまり場となった。
授業中も最前列に座る長友佑都は、教科書もノートも出さず、なにかいわれれば教師をにらんだ。
「それがかっこいいと思っていた僕は、今思えば弱い人間だった」
長友佑都はそういうが、不良ぶってもあまり悪いことはできなかった。
1番悪いことでピンポンダッシュ。
タバコも酒もできなかった。
サッカー部顧問:井上博は、長友佑都の入学と同時にも西条中学に赴任し、その再建に乗り出していた。
「1年生は俺と一緒に北中にきた。
卒業するまでの3年間でお前らがサッカーやれるようなんとかするけえ、先輩のことは気にせんと一緒にサッカーやろうや」
長友佑都はそういわれても
(どうせ口だけやろ)
とサボった。
「佑都、ちょっと話しせえへん?」
「こないだまでサッカー大好きで毎日サッカーやってたんやろ。
どうよ、いま物足りひんちゃうん?
もっとサッカーやりたいやろ」
「小さい頃、プロなりたいいうとったやろ。
ここで諦めたら終わりやで」
井上博先生は積極的に長友佑都にコミュニケーションをとった。
「小学校から佑都の代は強かったしうまかった。
中学のサッカー部がこんな状態やけえ、サッカーへの情熱が薄れてしもてもうた。
お前らサッカーやりたいのに・・・・サッカー部がこんな状態で・・・・」
ときには涙を流しながら話した。
井上博は生徒に本気でぶつかっていくタイプの熱血教師だった。

ドラマ:スクールウォーズのモデルとなった山口良治も、偏差値25、喫煙、飲酒、シンナー、バイクなんでもありの京都市立伏見工業高校に体育教師として赴任。
学校の廊下をバイク走ったり、教師へ暴力をふるう生徒もいた。
ある教師は怯え、ある教師はみてみぬフリをして、不良たちはやり場のない不満や憎悪を募らせ、ただ荒れていく一方だった。
山口良治が廊下を歩いていると教室から声がした。
「ポンッ」
そして笑い声が起きた。
みると授業中に生徒がマージャンをしていた。
山口良治はガラスが割れそうな勢いでドアを開けた。
「お前らなにをやっとるんじゃ、立て」
4人の生徒が不貞腐れながら立った。
「サングラスもとらんかい」
伸びてきた山口良治の手を生徒は払った。
平手打ちが飛び、サングラスをかけた生徒は倒れた。
逃げる3人をまとめて窓際に押しつぶし1人1人平手を食らわせた。
マージャンをみていた生徒6人も
「お前らも同罪じゃ」
と蹴り飛ばした。
廊下で前からバイクが走ってきたときは正直、怖かったが
(生徒を信じよう、信じよう)
と念じ続けた。
するとバイクは横を通り過ぎた。
数日後、バイクを走らせた生徒が訪ねてきた。
「ゴメンな先生。
先生だけや、俺に注意してくれたのは。
誰も俺に注意なんてしてくれへんで」
山口良治はわかったような気がした。
(コイツらは本当は寂しかったんや)
しかし以後も不良たちは山口良治にそれまで経験したことのないような屈辱と不快感を与えた。
(オレはラグビー日本代表やぞ)
(教師なんてなるんやなかった)
その度に後悔と自己嫌悪がこみ上げてきたが、最後は負けじ根性が出てきた。
(問題のない学校に教師などいらない。
教え屋がいればいいのだ。
こういう学校こそ教師が必要だ。
オレは体育教師だ。
体育教師が生徒にぶつけられるのは情熱だ。
闘志だ。
力だ。
そして信頼だ)
苦境になればなるほど、悪い状況になればなるほどより燃えてくる男だった。
そして数年後、
「信は力なり」
を旗印に京都市立伏見工業高校ラグビー部は全国大会優勝を果たした。

井上博は体育教師ではなかったが、サッカー部の生徒全員に本気でぶつかっていった。
どれだけ生徒に煙たがれ悪口をいわれても、同僚の教師に白い目でみられても、ブレずに貫いた。
冬、長友佑都はゲームセンターで遊んでいるところを井上博に見つかった。
「お前ら何しとるんじゃ」
「・・・・・・・」
「立てや」
長友佑都と友人は立ち上がった。
問答無用でビンタが飛んだ。
友人は膝から崩れ落ち、長友佑都は頬を手でおさえ下を向いた。
「お前がこんなことやってるんをみてるお母さんの気持ち考えたことあるんか。
そのゲームやってるお金は誰のおかげぞ」
この頬の傷みが長友佑都の目を覚まさせた。
「俺はお前とサッカーがやりたいんや」
といわれ、涙を流しながら黙ってうなづいた。
そしてサッカーに情熱を注ぐ日々が始まった。
「大丈夫や。
信じられる大人もおる。
あんなヤバいくらい熱い人はおらん
僕もいつか先生みたいな大人になりたい」
心のノート

長友佑都が中学2年生になったとき、井上博はサッカー部員にノートを配った。
「これはな、心のノートやけん。
何を書いてもいいけん。
とにかく毎日書いて持ってこい」
授業中ノートもつけていない長友佑都にとっては、正直、面倒くさかった。
「今日は元気で練習できました」
「ゴールを決められなくて残念だ」
当たり障りのないことを書いて提出した。
井上博はそっけない内容にも必ず熱いメッセージを書き込んで返した。
毎日書いていくうちに長友佑都はある発見をした。
(文字で書くと素直になれる)
真っ白のノートを前に1日を振り返る。
すると自覚していなかった自分の感情に気づくことができた。
また「書く」という作業も独特の作用があった。
書き始める前に気持ちを整理しなければならないし、ノートに書いた自分の気持ちを文字として読むことになるので、客観的に自分を見つめることができた。
まるで自分自身と会話するような感じだった。
現在ではパソコンや携帯電話で文字を打ち込むが、ペンで文字を書くことは、たとえ同じ文章を記してもやはり別ものである。
年賀状も手書きとプリントではまったく違う。
スポーツ選手のトレーニングやダイエットでも、目標や課題、決意を手で書くことで自分の意志を強化できるという。
長友佑都はノートを書くことが面白くなっていった。
家に戻り夕食を済ませるとノートを開く。
井上博の言葉を読み、そして自分の気持ちを書いた。
1日で何ページも書くこともあった。
「両親のやつには負けたくない」
「片親だからと同情されたくない」
いつもそんなことばかり考えていた。
それはあるときは力になったが、いつも必要以上に周囲を意識した気張った状態であり、大きなストレスでもあった。
しかしノートの向かうと素直になれた。
「もっとドリブルがうまくなりたい」
と書けば、なるためには何をしなくちゃいけないか楽しく考えられ、自然と目標が生まれてきた。
「チームが1つになることはボールを蹴ることより大切なこと」
「世界一熱い部活」
ノートには他人にみせると恥ずかしいが大切な言葉も並んだ。
中学時代に書いたこの「心のノート」が、現在の逆境にあっても決して信念がブレない長友佑都をつくったといっても過言ではない。
「強くなろうや」