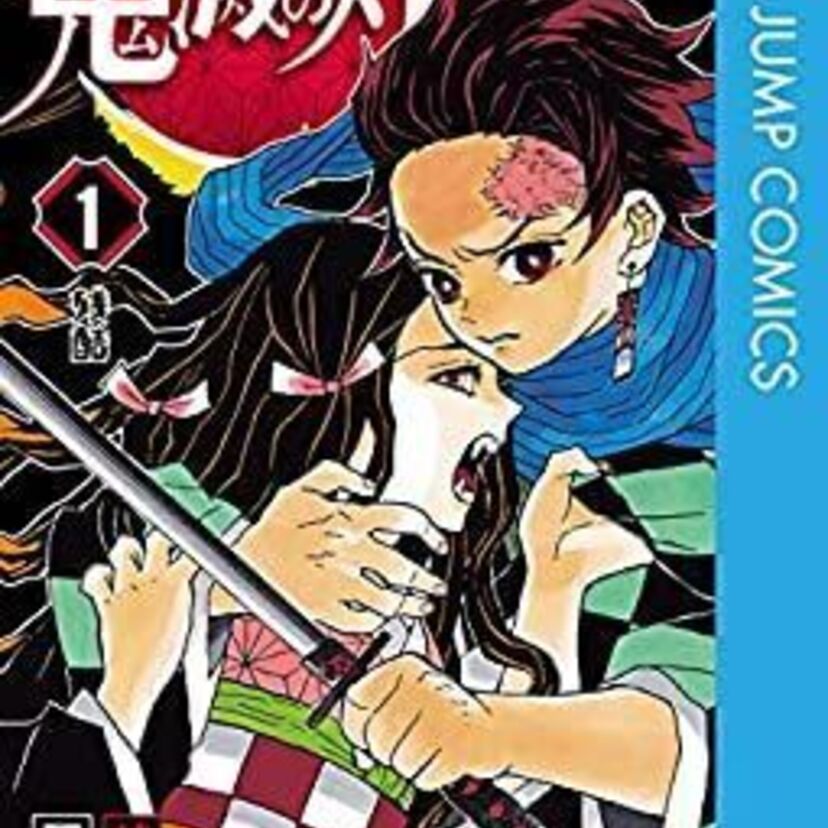このコラムは「鬼ごっこ協会鬼文化コラム」より抜粋・編集したものです。
鬼については多くの研究者が様々な見解を出されておりますが、「おに」という言葉の語源について書かれた最も古いものは、平安中期に確立したとされる日本最初の百科辞典『和名類聚抄』だと言われています。
ここには「鬼和名於爾 或説云、隠字音於爾訛也、鬼物隠而不欲顕形、故俗曰隠也」と書かれております。つまり姿が隠れている「隠(おん)」が転じて「鬼(おに)」になった・・・ということですが、この説に対しても色々の指摘がされてきました。
では単語としてはいつ頃から文献に出ているかというと、例えば『日本書紀』の欽明5年(544)に「粛慎人(みしはせのひと)」に対して「彼の嶋の人、人に非ずと言す。亦(また)鬼魅なりと言して、敢て近づかず。」「人有りて占へて曰く、この邑の人、必ず魅鬼の為に迷惑はされむ。」という表現をしており、「鬼魅」「魅鬼」という単語で登場しています。どうやら、この場合は得体の知れない隠れた存在というより、外敵(人)を指しているようです。
また、斉明天皇の葬儀の際の記述では朝倉山の上に「鬼有て、大笠を着て、喪の儀を臨み視る。」とあります。大笠を着た異形の何かが山の上から覗き見ている・・・これは朝倉山の神さまのことではないかとも言われています。 この2つの例をみても分かるように、「鬼」って何?と言われると、正体は1つではないのです。
さらに、巻2「神代下(かみよのしものまき)」には「悪しき鬼(モノ)」「順(まつろ)はぬ鬼神等(カミたち)」という記述もあります。漢字は「鬼」ですが、オニとは読みません。前者はモノ、後者はカミです。
日本民俗学の折口信夫先生の1926(大正15)年の講演筆記「鬼の話」によると、折口先生は古代日本人の神観念にはカミ、タマ、モノ、オニの4つがあると述べておられます。オニは神様でもあるのです。現在もその姿は祭礼の中に登場するオニたちに受け継がれております。秋田県のナマハゲなどは、外見こそ恐ろしく正しくオニの風貌ですが、その真意は歳の変わり目に人々に祝福を与える来訪神です。

その一方で、誰もが知っている桃太郎に退治される鬼のように退治・調伏される存在としてのオニも、確かに存在してきました。
『古語拾遺』という書物があります。平安初期(9世紀)に書かれた歴史書で、著者は斎部広成(インベノヒロナリ)。斎部(忌部)氏は古代には中臣氏と並んで祭祀を担当しておりましたが、皇極天皇4年(645)の大化改新後、中臣氏から藤原氏が出て政界で勢力を拡大するに伴い、奈良時代には中臣氏が祭祀関係の要職を独占するようになりました。これを憂いた斎部広成が自氏の伝承を同書にまとめました。
この『古語拾遺』の「吾勝尊(アカツノミコト)」のくだりに「鬼」が登場します。このくだりは、大雑把に説明しますと日本神話「国譲り」の箇所。大国主(オオクニヌシ)と事代主(コトシロヌシ)が去り、地上の支配権が高天原の神に譲られた神話についてです。
吾勝尊(アカツノミコト)は古事記では天照(アマテラス)大神と須佐之男(スサノオ)命の誓約で生まれた神として登場しており血統上はアマテラスの子供となります。そのアカツノミコトのくだりに「於是 二神 誅伏諸不順鬼神等 果以復命」という一文があり、ここに「鬼神」の文字が登場します。
現代語訳しますと「それで二柱の神はもろもろの従わない鬼神(アラブルカミ)たちを誅伐して従わせ、ついに天界に報告しました」という意味。鬼は「荒々しい」と表現されております。
この「国譲り」神話は『日本書記』にも「故高皇産靈尊 召集八十諸神而問之曰 吾 欲令撥平葦原中国之邪鬼 當遣誰者宜也 惟爾諸神 勿隱所知」とあります。ここでは「邪鬼」という表現。現代語訳すると「葦原中国の邪神を追い払って平定したいと思っている」という内容です。
これらの鬼は「自分達に逆らう退治すべき者」という意味合いです。桃太郎伝説の鬼を思い出してください。日本各地に「(時の政権側にとって)退治すべき存在」としての鬼が確かに存在します。しかし、彼らには彼らの世界があります。彼らは決して「悪」ではないのです。何事も片方の言い分だけを聞いて判断してはいけない・・・鬼はそれを教えてくれる、大事なことを教えてくれる存在です。
日本古来の「隠」としてのオニ、その後伝来する仏教での「鬼」としてのオニなど、いろいろなオニが日本に広がり今があります。ですから、「鬼」という一言で言い尽くせない存在でもあるのです。
「鬼」という単語から日本の古代が垣間見れる・・・これもまたひとつの鬼ロマンだと思いませんか?
「鬼ごっこ協会」とは?
一般社団法人鬼ごっこ協会 公式HP