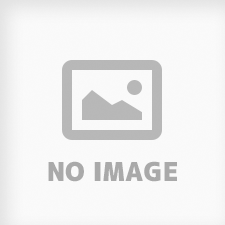放送コードとは
放送事業者(テレビ・ラジオ)が定めている放送基準、番組基準を放送コードといいます。日本では放送法によって多くの放送事業者が番組基準を制定・公表し、それに則って番組を編集しなくてはなりません。
ニュースに限らずあらゆる番組には何らかのジャーナリズム性があると定義し、加えて放送には聴覚性、視覚性、同時性、臨場性があって受け手に与えるインパクト、社会的影響力が大きいとされます。
また放送事業は電波を使わなければ成立しないメディアです。電波は有限・希少な資源であることから電波は国民の共有財産と考えられます。
「社会的影響力の大きさ」「電波利用」の二つの特徴から、公共性が高い放送にはなにがしかの規制が必要という考えが根底になります。
放送は「中立性」を保つために公権力の介入を認めないものとしていますが、いくら表現の自由といっても例えばそれが他の人権と衝突する場合には一定の制限が必要です。このことから各放送事業者はそれぞれ自律するための基準を定め、自らの表現の自由に制限を課すものとしています。
番組基準の制定
放送コードに基づき大半の放送事業者に義務付けられているもの。放送番組の種別・放送対象に応じた番組基準を制定し、これに基づき編集することを公表するよう義務づけられています。制定が義務づけられている事業者は番組審議会も設置しなければなりません。
1950年制定の放送法で番組基準の制定が義務化されたのは1988年の改正時ですが、く義務化される以前から日本放送協会(NHK)、一般放送事業者(当時は民間放送事業者)、日本民間放送連盟は自主的に制定していました。
なお、番組基準はCMについては適用されません。
※基本的には「民放連放送基準」を基に、各放送局のCM担当部署がそれぞれ考査基準を定めて規制
放送番組審議会
歴史としては1953年、放送番組の「低俗化」批判の高まりから日本民間放送連盟内に放送基準審議会を設置。1957年、当時の田中角栄郵政大臣が「放送番組審議会」構想を表明し、1959年より放送事業者に義務付けられていきます。
1985年には郵政省より各局に「過剰な性表現を含む深夜番組の自粛要請」が送られ、各局・審議会より公権力の不当な介入との声が上がりますが、後述の放送倫理・番組向上機構(BPO)設立にも繋がっていくこととなります。
審議会の構成・審議内容
委員は学識経験者で構成され、事業者によって任命されます。審議内容としては
-放送番組の試写・試聴と、その感想
-放送事業者への意見
-視聴者・聴取者からの、放送番組に関する苦情・意見の概要
などですが、放送事業者が自ら委員を任命できるため、審議会による放送局の自浄作用がそもそも強く働かないという懸念が存在します。実際のところ、1985年の自粛要請から急に番組表現が厳しくなった気はしませんね。それよりも後のBPO設立からの方が随分と厳しくなった気がします。
放送コードに従う放送禁止
放送コードに従う放送禁止は、各放送事業者が制定する番組基準に従って自主規制で行われています。
放送禁止の対象
また、個人情報保護法の施行以降はとくに個人情報が特定されるモノも規制対象となっています。その他、元来NHKで規制されていた企業名・商品名(商標)などの取り扱いは、民放でも規制強化の方向にあります。その分、プレイスメント広告による収益手段を生んでいる側面もありますが。
企業名・商品名の扱い(NHKと民放)
NHKでは「テトラポッド」→「波消しブロック」、「味の素」→「うま味調味料」、「ファミリーコンピュータ」・「プレイステーション」など→「家庭用ゲーム機」など、ほぼ一律に一般名称に言いかえますが、民放ではスポンサーとの関係などで慎重な使い分けがなされます。
民法では、たとえばヤマト運輸株式会社提供の番組では、同社の登録商標である「宅急便」の名称やロゴマークが使われますが、他の宅配便事業者の内容を扱う場合において「宅急便」を用いることはありません。
よいテレビ放送の三大要素(「ピルキントン委員会報告書」1962年・イギリス)
放送禁止 - Wikipedia
放送禁止の対象は時代とともに変化していきます。このため、古い番組内容の再放送などでは問題が起きます。
例えば未成年者の飲酒、街中での喫煙、ヘルメット未着用でのバイク運転などがそうで2008年ごろからは、アニメやドラマにおける法抵触場面ですら対象とされるようになり、悪役でも車を運転する際はシートベルトを締め、バイクを運転する際はヘルメットをかぶる。また、大学生の飲酒の場面なども放送されなくなりました。
インターネットの普及が見られ始めた2005年ごろから番組制作・放送の可否は放送局判断よりも視聴者意見によるところが大きくなり、各放送局ともに「問題となりそうな部分ははじめから避ける=ことなかれ主義」がひろがって、あたりさわりのない範囲にとどめざるを得なくなっていきました。
「きょうふのキョーちゃん」にみる放送コードギリギリを攻めるということ。 - Middle Edge(ミドルエッジ)