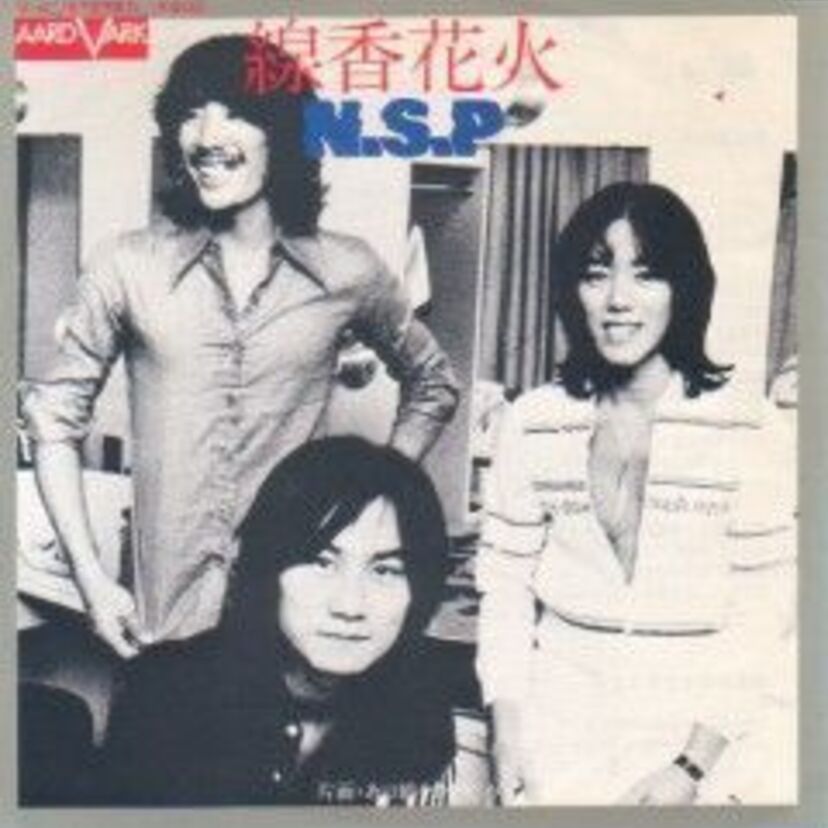N.S.P
70年代の3人組でギター2本にベースとくれば、かぐや姫が代表だと思いますが、かぐや姫よりも繊細で詩情あふれる作品で知られるNSP(エヌエスピー)を知っていますか?!

NSP
NSPは1973年に「さようなら」でデビューしています。デビュー曲にして「さようなら」というのも一筋縄ではいかない感じがしますが、3ヶ月後にでたファースト・アルバム「NSP FIRST」がライブ・アルバムというのも変わっています。

NSP FIRST
変わっているといえば、そのグループ名もユニークですよね。結成当初、アマチュア時代にはロック志向だったそうでニュー・サディスティック・ピンク(New Sadistic Pink)と名乗っていました。
しかし、フォークにそのネーミングは合わないだろうということで、頭文字をとってN.S.Pとしています。N.S.Pというのもフォークという感じはしないように思いますけどね(笑)
夕暮れ時はさびしそう
第5回ヤマハポピュラーソングコンテストでニッポン放送賞を受賞したことで、ファースト・アルバム、シングルともに注目されたのですが、続くセカンドアルバム「N.S.P II」とシングル「 ひとりだちのすすめ 」は厳しい結果となってしまいます。
しかし、神は見捨てません。1974年9月に発売されたサード・アルバム「N.S.P III ひとやすみ」とシングル「夕暮れ時はさびしそう」が大ヒットします。

N.S.P III ひとやすみ
かぐや姫の影響が大きかったのでしょうが、当時のフォークソングといえば四畳半フォークと呼ばれたりしていてティーンエイジャーにとっては実感が湧かない内容でした。
しかし、N.S.Pの楽曲はフォークといっても身近な内容です。優しく、繊細で。その代表曲が「夕暮れ時はさびしそう」でしょう。
ナイーブだなぁ。。。思わずこの歌の主人公になってしまいそうです。この曲、代表曲に違いありませんが、もちろんN.S.Pはこれだけではありません。この年の終わりにも、もう一曲N.S.Pらしい名曲「 雨は似合わない 」を発売します。
「 雨は似合わない 」を収録したアルバム「おいろなおし」を1975年2月に、同年8月には早くも5枚目となるアルバム「2年目の扉」を出します。
タイトルが示す通りN.S.Pは新しい扉を開こうとするのでした。
赤い糸の伝説
いま改めて聴くと胸を掻き毟られそうになるほど切ないN.S.Pの楽曲ですが、結局大ブレイクには至らなかったんです。
もっとヒットしてもよかった、ヒットしなかったのが不思議でなりません。時代でしょうか。。。
そんな中、1976年4月に発売された8枚目のシングル「赤い糸の伝説」は、久々のスマッシュヒットとなりました!
「赤い糸の伝説」に先行シングルだった「ゆうやけ」、更には次のシングルとなる「線香花火」を収めたアルバム「シャツのほころび 涙のかけら」が1976年5月に発売されます。

シャツのほころび涙のかけら