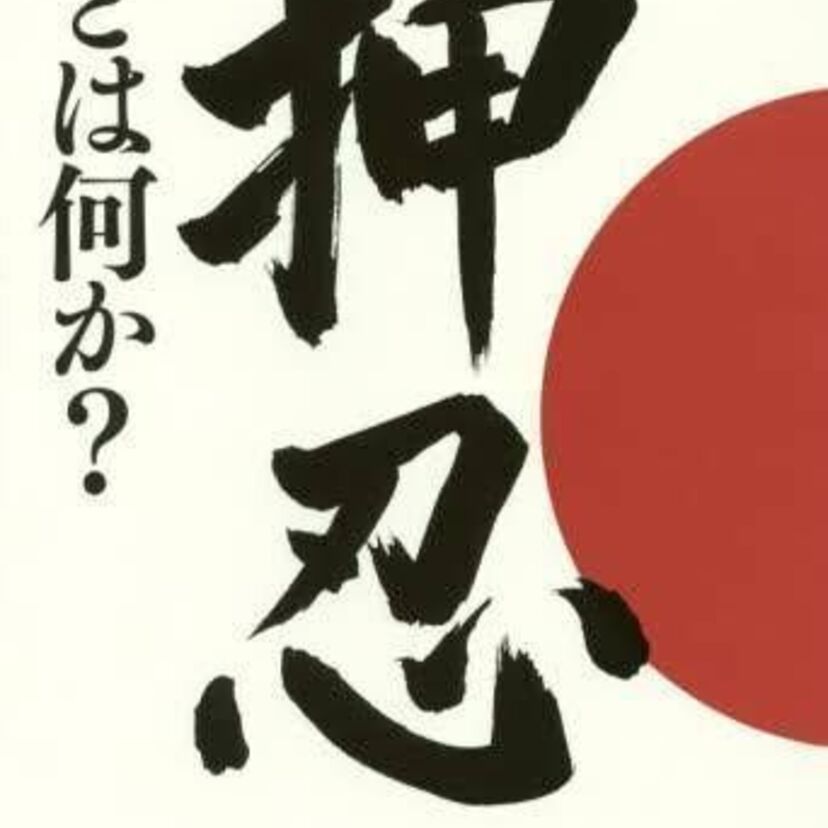2018年になりました。本年もなにとぞよろしくお願い申し上げます。
年始め、第一発目のコラムは挨拶について。
私は宮下あきらさんの漫画「魁!男塾」(集英社)が子供の頃から大好きなので、年末年始も男塾を読んで鋭気を養っていたのですが、挨拶の「押忍!」って何かしら?と。2020年の東京オリンピックにおいて空手が正式種目に決定した時にも「押忍(オス)」という言葉を連想しました。空手家にとどまらず幅広く皆様に愛されるこの言葉のルーツについて昨年、その疑問を解決してくれる本に出会いました。大森敏範氏の『押忍とは何か?』(三五館 2016年)です。

『押忍とは何か?』(大森敏範著・三五館 2016年)
この本には、まず言葉の系譜として『古事記』『日本書記』における「押」と「忍」について、
“本居宣長が35年をかけて書き終えた『古事記』の注釈書である『古事記伝』八之巻には、忍は輕く附云辭には非ず(軽々しく附ける言葉ではない)と書かれている。「押」「忍」は畏敬の尊称として使われていたのだ。(中略)『日本神名辞典』にも、「忍は押さへつけるの意で威力あるものの美称」と書かれており、『相撲大辞典』にも書かれている「相撲界では“押す”は“忍す”に通じる」と一致する。“
と書かれております。
では、いつから挨拶言葉としての「押忍」が広がったのか。
大森氏はまず、現存する起源説を以下の通り取り上げております。
この4つです。そしてひとつひとつを検証され、拓殖大学の説のみがそれを否定する史実や証言を発見することは出来なかったとして、拓殖大学起源説をより深く検証されております。
「押忍」拓殖大学起源説
拓殖大学(明治33年・1900年~。桂太郎が創設)。箱根駅伝で名前を聞いた人も、レスリングで聞いた人も多いかなと思う、東京・茗荷谷にある大学です。「拓殖」とは「未開の荒地を切り開いて、そこに 住みつくこと」を意味する言葉で、言葉通り、拓殖大学は戦前からアジア開拓など外地に携わる人材育成を目的としておりました。元々は台湾への入植者育成の教育機関であったこともあり、同大の政経学部は早稲田大学や明治大学に次ぐ歴史を誇ります。ついでに言うと、創設者の桂太郎氏(かつら たろう、弘化4年(1848年(弘化4年)~1913年(大正2年))は「ニコポン宰相」というあだ名があった首相としても知られております。ニコっと笑ってポンと肩を叩いて「そのうち飯でも食おう」など言って相手の懐に入り込む桂首相のコミュニケーション術にたいしてつけられた単語で、1913年に「ニコポン宰相」やら「ニコポン主義」という単語が流行しました。
ニコポンから話を戻しましょう(汗)
大森氏は拓殖大学のオス(あえてカタカナ)について、
と述べた上で、その高木氏が当時「オス、オス」という気合いを入れていた史実も記しております。さらに合気道養神館創始者・塩田剛三氏が著書『塩田剛三の合気道人生』の中で、拓殖大学を卒業した昭和16年(1941年)に「オスッ」と挨拶をした記述があることなどの史実も丁寧に取り上げて検証。検証の結果、当時の拓殖大学では「オス」であって、漢字表記の「押忍」が確認できないとも。拓殖大学の文化として、「オス」が挨拶、返事、意思表示にとどまらない範囲で使用されていたことも言及。「お前」も「自分」も「拓大」もオス…雑誌『キング』昭和29年(1954年)3月号「紋付大学見聞帖 オスと呼べばオスと応える」にもオスの起源が拓殖大学にあると書かれているそうですが、ラブレターを女性に渡す時にさえ「オス!」と言った人がいたそうなので、拓殖大学おそるべし。本の中で、拓殖大学レスリング部OBの宮澤正幸氏(日本レスリング協会顧問)は「私は(オスは)拓大弁のひとつだと思っています」と語っています。
さてそんなオスがどのように日本に幅広く伝播したのか…ここはぜひ大森氏の著書を読んでいただきたいと思いますが、本の帯を写真にて提出しておきます。

2020年東京オリンピックで初めてオリンピック種目になった空手。そして、世界に羽ばたく言葉「オス(押忍)」。2018年最初のコラムは今使われているオスの起源が拓殖大学にあるというコネタでした。このコラムを書くにあたり、本の紹介を快諾してくださいました大森様にこの場を借りて心より感謝申し上げます。