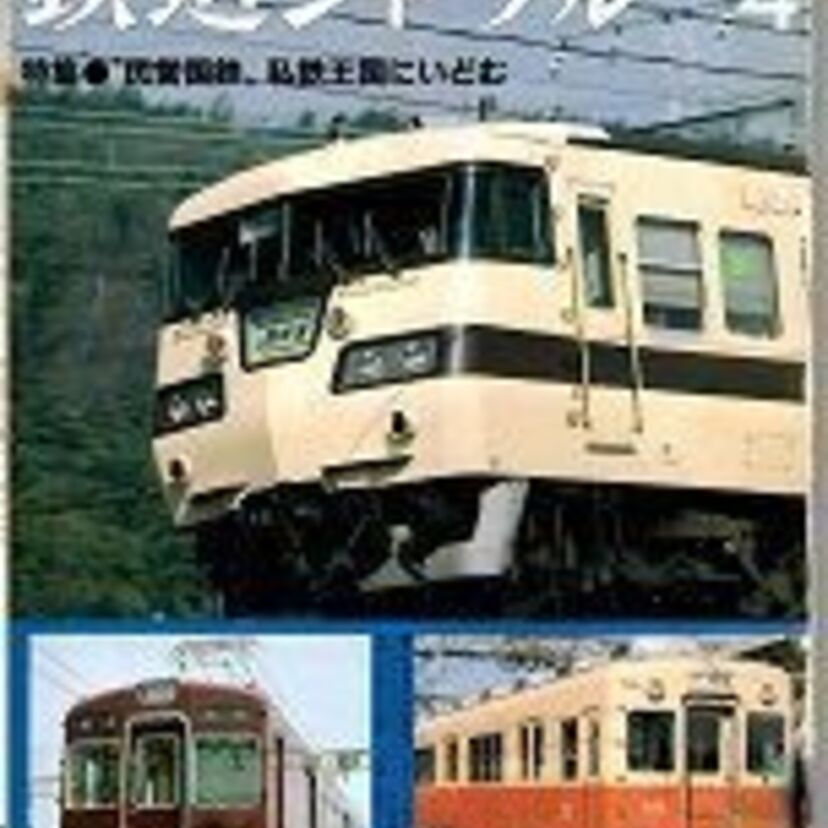「鉄道ジャーナル」最新号はこちら。
「鉄道ジャーナル」1987年4月号表紙。

「鉄道ジャーナル」1987年4月号表紙。
鉄道ジャーナル社「鉄道ジャーナル通巻245」表紙。
鉄道ジャーナル1987年4月号の目次。

鉄道ジャーナル87年4月号目次
鉄道ジャーナル社「鉄道ジャーナル通巻245」目次。
1987年の鉄道シーンの最大のトピックは、何といっても国鉄の分割・民営化です。
4月号は2月20日に印刷となっており、4月以降の変化は載っていませんが、直前に行われた国鉄のダイヤ改正による、新生JRに向けての意気込みを余すところなく伝えている「熱い」一冊となっています。
特集”民営国鉄”私鉄王国にいどむ。
特集ではこのようなタイトルがあり、巻頭で「京阪神複々線をゆく」と題されたテーマが取り上げられています。

117系電車。
国鉄117系電車 - Wikipedia
京阪神地区屈指の鉄道撮影地で、117系新快速と485系特急(雷鳥でしょうか。)との離合の見事な写真が掲載されています。
その撮影地が「神足ー山崎」と記載されているのが、なんとも懐かし過ぎます!!。
私、ジバニャンLOVEは、この当時青春18きっぷを利用してよく東京から祖母のいる京都まで各駅停車で旅行をしたものですが、この当時は米原で乗り換えても、先発の113系各駅停車のほうが、後発の117系新快速よりも先に京都に着く、というのんびりしたダイヤでした。(高槻あたりで新快速が追い抜き、大阪にはさすがに新快速のほうが先に着いていました。)
現在は新快速の本数も多くなり、223系や225系が、快適な旅を提供してくれていますね。
【格安旅行のマストアイテム】青春18きっぷの歴史 - Middle Edge(ミドルエッジ)

現在の最新型新快速 JR西日本225系電車。
JR西日本225系電車 - Wikipedia
この号では、強豪私鉄と競合する京阪神地区で、国鉄が民営化をひかえ、攻めの姿勢に乗り出したということが書いてあります。
特に国鉄はこの地区において、線形が競合私鉄よりも直線的なことを活かし、スピードで優位にたったということが書いてあります。
また、「フリークェントサービスの拡充をはじめた」と書いてあります。
しかし、この時代では、まさか30年後には私鉄がスピード競争からほぼ撤退し、自社路線沿線の住民に向けたサービスを重視していくとは、想像できなかったのではないでしょうか。
【1983年登場】JR西日本京阪神のマストアイテム「昼特きっぷ」が廃止へ - Middle Edge(ミドルエッジ)
ジバニャンLOVEの勝手な個人的な見解ですが、この「昼特きっぷ」の廃止は、「割引なんかしなくても乗ってくれるだけのサービスを提供している。」という、JR西日本の競合私鉄に対する勝利宣言であると思っています。