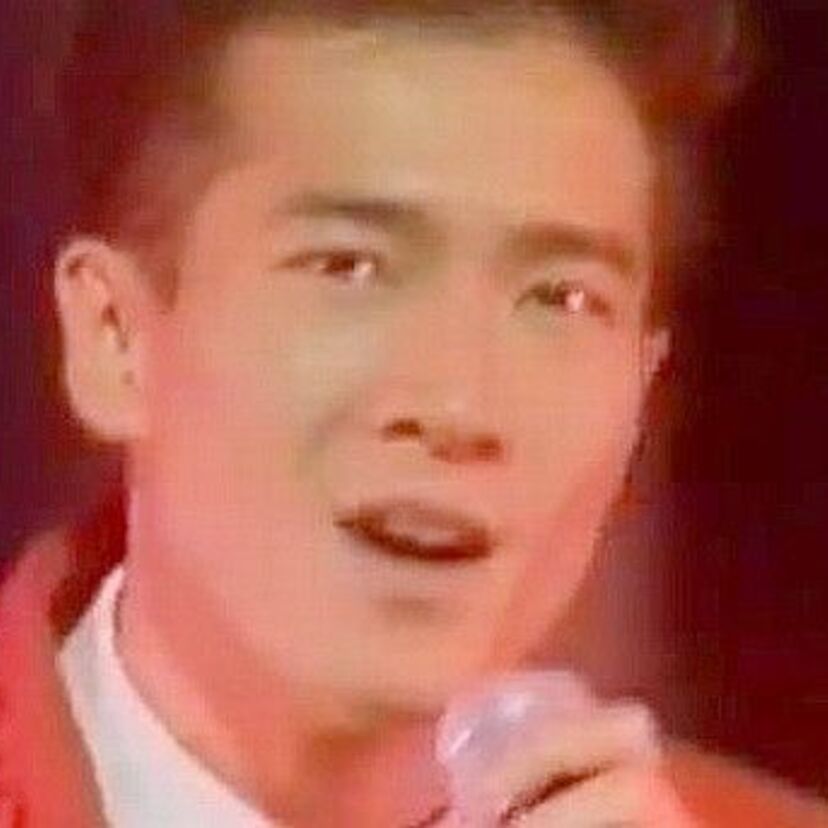『歌って踊れる』とは?
歌えるだけでなく、ダンスも上手い。
そんなアーティスト(歌手)を形容する表現として『歌って踊れる』はよく使われている。
とくに90年代にR&Bやヒップホップ系のミュージックが流行すると『歌って踊れる』と言われるアーティストは増えていった。
その代表的な存在としては、安室奈美恵やISSA(DA PUMP)をはじめとする沖縄アクターズスクール出身のアーティストが挙げられる。
『歌って踊れる』の歴史を作り上げたアーティストたち
現在はデビュー前から歌と共にハイレベルなダンスを訓練しているアイドル・アーティストも多い。
だが、「アーティスト」ではなく、「歌手」と呼ばれていた80年代。
踊りができる歌手というのは視聴者に大きなインパクトを与えた。
そんな『歌って踊れる』の歴史を作り上げた懐かしのアーティストたちを当時の映像を交えながら紹介。
『歌って踊れる』アーティスト:田原俊彦

田原俊彦(たはら としひこ)
マイケル・ジャクソンを尊敬し、積極的にダンスを取り入れていった田原俊彦。
一時期「和製マイケル・ジャンクソン」とも呼ばれ、日本でムーンウォークを広めた男とも言われている。
歌唱力が低いとの批判を受けても、生歌にこだわり口パクを頑なに拒否していたという。
『歌って踊れる』アーティスト:風見慎吾

風見慎吾(かざみ しんご)現:風見しんご
1983年公開の映画『フラッシュダンス』のワンシーンに衝撃を受け、ニューヨークに出向き猛特訓でブレイクダンスを修得。
翌年12月に発売した4曲目のシングル「涙のtake a chance」にブレイキングやアクロバットを大胆に取り入れ、お茶の間とエンタメ界に衝撃を与えた。
5曲目の「Beat On Panic」ではヌンチャクを使用した、本人曰く「バトルダンス」を披露した。
(風見は子供の頃に少林寺拳法を習っていたことがある)
1985年放送のフジテレビのドラマ『スタア誕生』、『ヤヌスの鏡』に出演の際にも一部ブレイクダンスを踊っているシーンが登場し、これをテレビで見てブレイクダンスを始めた者も少なくない。
日本におけるブレイクダンスの先駆者である。
スポーツばりの激しいダンスを取り入れながら「口パクは1度もしていない」と風見は語っている。
全て生歌だった為、息継ぎが聞こえたり、歌唱が乱れることもあった。
音楽に造詣が深い小説家・平野啓一郎は、風見の例によって激しいダンスと歌の両立はムリという認識が広がり、後に歌とダンスの役割を分担するTRFやEXILEのようなグループを生み、他方「口パク」OKで、歌手自らが踊りながら歌うという流れを生んだと述べている。
『歌って踊れる』アーティスト:荻野目洋子

荻野目洋子(おぎのめ ようこ)