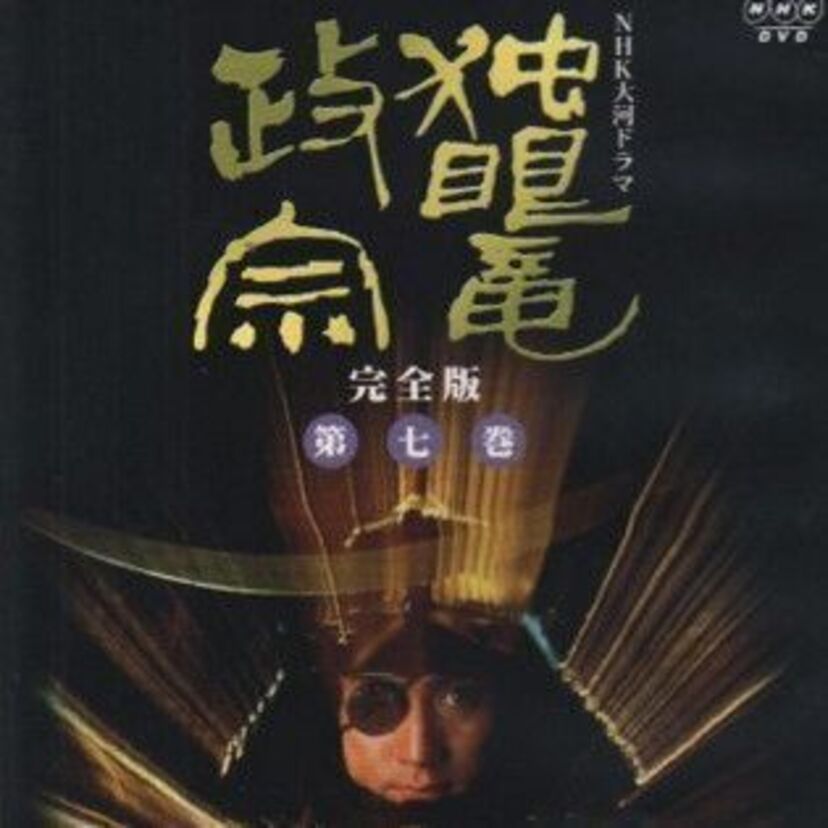NHK大河ドラマ『独眼竜政宗』(1987年) 伊達政宗:渡辺謙 平均視聴率39.7%・最高視聴率47.8% 「政宗ブーム」が起きる

NHK大河ドラマ『独眼竜政宗』(1987年) 伊達政宗:渡辺謙 平均視聴率39.7%・最高視聴率47.8%

伊達政宗:渡辺謙 「渡辺謙=伊達政宗 」の固定イメージが定着してしまう程のはまり役

伊達政宗は逆境にあう度にそれをバネにして活躍する。知恵と勇気、様々な駆け引きや工作を展開していく。
存在感抜群!天下人の関白・秀吉を勝新太郎が演じる

本作が唯一の大河ドラマ出演であった(NHK制作のドラマとしても同様)勝新太郎が秀吉を演じた。

圧倒的な存在感の勝新太郎演じる秀吉。天下人の風格にあふれる。

タヌキ親父な存在感が抜群!徳川家康(とくがわ いえやす) 演:津川雅彦 はまり役!
不動明王について教えられた梵天丸(政宗の幼名)がその養育係である喜多に語った「梵天丸もかくありたい」という台詞は流行語となった。

養育係である「喜多(きた) 演:竹下景子」に梵天丸(政宗の幼名)「梵天丸もかくありたい」

政宗(梵天丸)の正室の「愛姫(めごひめ)」の少女時代は、当時史上最強の美少女として一斉を風靡した『後藤久美子』が演じた。
NHK大河ドラマ『独眼竜政宗』(1987年)の大ヒットにより「仙台市」観光バブルが起こった。大河のヒットで関連する舞台への観光が潤う大河バブルのさきがけ。

城下町仙台の歴史は、伊達政宗がここに城を築いたときに始まります。

渡辺謙や桜田淳子が参加した仙台・青葉まつりも前年比3倍の過去最高の観光客数となって「大河バブル」のさきがけとなった。

「仙台市博物館」 1987年(昭和62年)の「政宗ブーム」の際、前々年までに再建がなされて資料館も付設した瑞鳳殿、および、前年に新築された当館は観光客を多く集めた。
1982年に東北新幹線が開業した影響もあり、渡辺謙や桜田淳子が参加した「仙台・青葉まつり」は、過去最高の観光客数を記録。
http://news.livedoor.com/article/detail/10201208/大河ドラマのすごさ「独眼竜政宗」「風林火山」などの経済効果は - ライブドアニュース
NHK大河ドラマの観光への影響

「大菊人形展」は大河ドラマをテーマにするケースが多い。