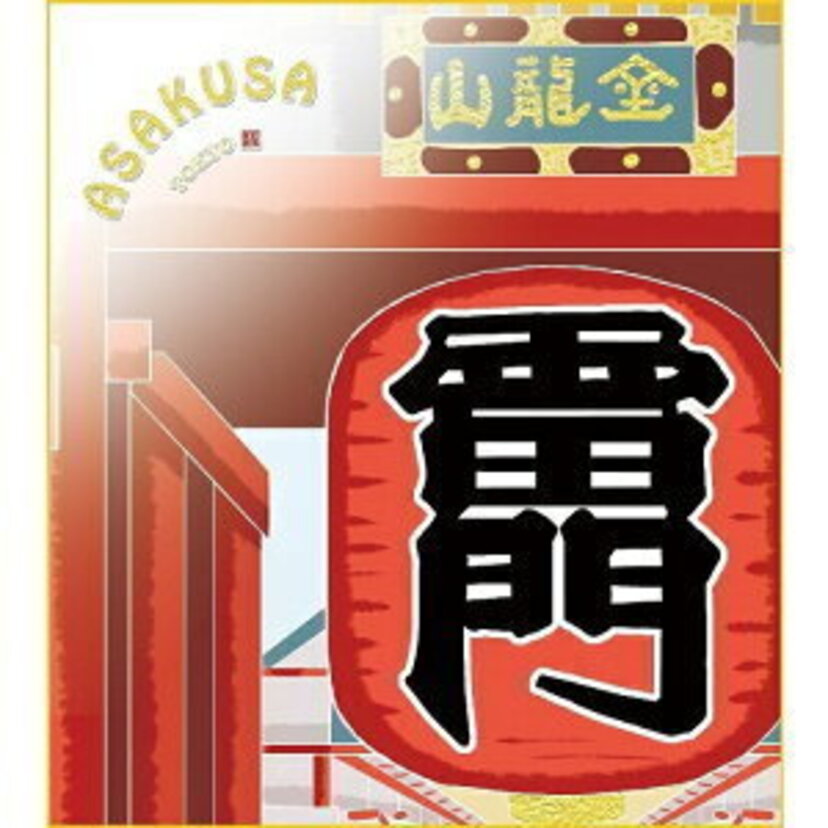提灯

昭和時代には、観光地でしか買えないお土産があり、観光地の名前が入った提灯もその1つです。
各地の提灯を集めるのが趣味だった人も多いのではないでしょうか?
明治末期の生まれだった私の祖父も、自室に全国各地の提灯を飾っていたのを覚えています。
私も中学の修学旅行で関西に行ったときに、祖父に提灯をお土産に買って帰ったところ、大変喜ばれました。
近隣の提灯ばかりになってしまうので、遠方であまり買えない地域の提灯は貴重だったのでしょう。
いつの間にか観光地の土産物屋さんで、提灯を見かけなくなりましたが、なぜ見かけなくなってしまったのでしょうか?
最近、観光地のお土産で提灯、あまり見なくなりましたが、今は、あまり売れない... - Yahoo!知恵袋
なんと、理由の一つは日中関係の悪化だったようです。
意外な理由でした。
なんとなく、観光地名の入ったお土産物を飾る人が少なくなったなどの理由かと思っていましたが、製造側の理由もあったようです。
観光地名の入った提灯がズラーっと飾られた今は亡き祖父の部屋…。
祖父が住んでいた家も随分前に解体されてしまったので、もう見ることは叶いませんが、頭の隅に鮮明に残っています。
レトロで粋な土産物でしたね。
ペナント

提灯とセットで思い出されるのが、観光地名入りのペナントです。
観光地名の入ったペナントも、昭和時代のお土産の定番でした。
若い人や子供へのお土産は、提灯よりもペナントの方が手軽でしたね。
実はペナントのルーツは欧米にあり、騎士が槍につけた「ぺノン」と、船舶に掲げられる「ペンダント」の合成語だということです。
ペナントは日本のお土産の定番とばかり思っていましたが、西欧の騎士にルーツがあるということで、ロマンがありますね。
日本では、大学の山岳部が登頂の際に山頂でペナントを立てていたので、1950年代に山小屋が記念品として製作したことが始まりです。
それが山以外の観光地にも広まり、お土産の定番となりました。
ペナントというと真っ先に思い出すのが「富士山」なのは、ルーツが登山だったからなのですね。
1950年以降の旅行ブームに乗って、お土産の定番となったペナントですが、旅行の目的が「観光」がメインではなくなったことで、廃れていったようです。
確かに旅行の目的がどこに行ったのか?よりも何をしたか?に変わったように思いますね。
寂しいですが、理由に納得です。
こけし

そしてなぜかこけしもお土産の定番でした。
昭和時代にはどこの家にもこけしが1つ、2つ飾られていましたね。
現在も外国人なら、お土産として好まれそうです。
とはいえ日本人には、好きな人は好きだけど、興味の無い人も多いように思いますね。
なぜこけしがお土産の定番だったのでしょうか?
なんとこけしの誕生は、江戸時代後期まで遡ります。
東北の温泉地で木地職人が余材を利用して子供のおもちゃを作ったことが始まりとされていますが、湯治客のお土産として人気になっていきました。
そして各温泉地に広まっていったそうです。
土産物としてのこけしの歴史は古く、提灯やペナントよりも古くから親しまれていたのですね。
形や大きさ、そして顔がそれぞれ違うのが魅力です。
まりも

続いて貰うと嬉しかったのが、まりもです!
子供の頃まりもは生きていると聞いたので、ペットのようにも思えて嬉しかった覚えがありますね。
でもまりもって一体何なのでしょうか?
お土産の定番として見かける球状のまりもは、北海道阿寒湖と秋田県獅子ヶ浜湿原にのみ生息する天然記念物です。
そんな貴重な物がなぜお土産として売られていたのでしょうか。
実はお土産のまりもは、養殖した糸状の藻を人工的に丸めてあの丸形にしています。
天然記念物は守らなければいけませんし、手軽に買えるお土産として当然と言えば当然ですね。
まりもは植物なので、エサは要りませんが光と綺麗な水が必要です。
「まりものごはん」などもありますが、植物の栄養剤に近い成分で作られていました。
植物だから餌を食べることはないのですね。
ペットというよりも、サボテンや観葉植物に近かったようです。
ただまりもは現在もお土産の定番として活躍していますので、お土産のロングセラーですね。