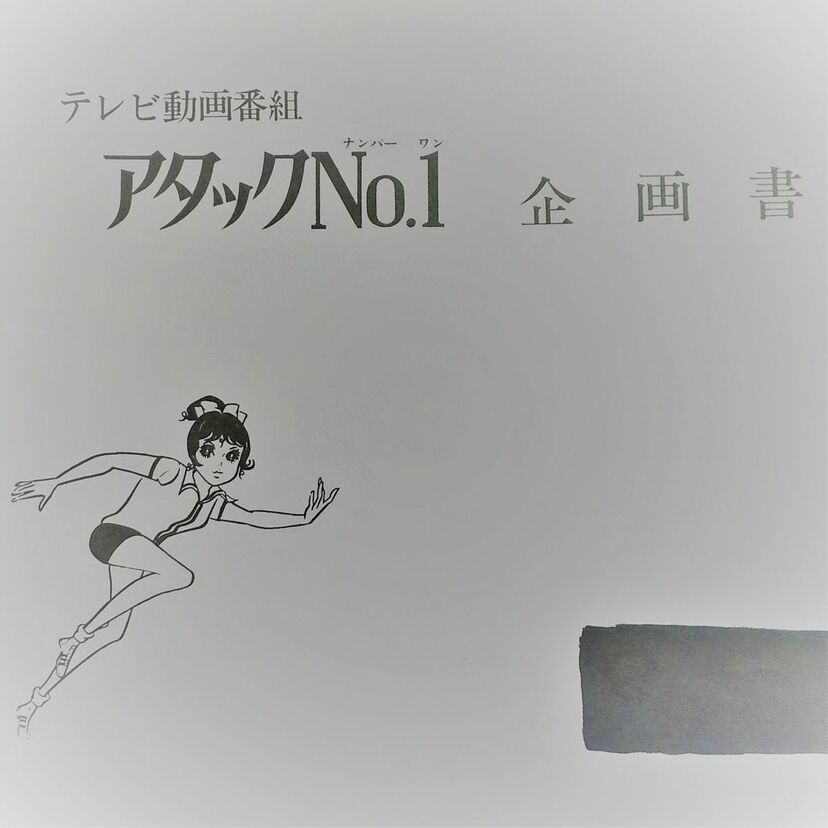アタックNo.1
1969年のフジテレビでのアニメ化の他、2005年4月には上戸彩さん主演のテレビドラマ化もされました。
ここでは1969年のテレビアニメ化を企画した資料から「アタックNo.1」の魅力を当時テレビのプロたちがどのように捉えていたのか、紐解いていきたいと思います。

企画書の表紙、B4判の冊子となっております。
社名(起案者名)については黒くつぶされています。
テレビ動画番組「アタックNo.1」企画書

「テレビ動画番組」
という表現が、50年前であることを感じさせてくれます。
魅力のポイント

「アタックNo.1」はなぜ人気No.1なのか?
この企画が出される時点で、すでにマンガが人気を誇っていたことが分かります。
以降、アタックNo.1の魅力を表している表現を抜き取っていきましょう。

「少女マンガなのに男子も愛読している」
「少女版”巨人の星”」
「アタックNo.1」の人気ぶりは、媒図かずお先生の怪奇漫画以来だと書かれています。

「バレーボールを通じてみせる、多感な少女の成長が、ファイトと友情で前進を続ける努力が、スポーツ特有の明るさと華麗なプレーに彩られて、100万少女の胸を燃え上がらせる」
熱いです、美しいです。
そして「100万少女」という表現がとても新鮮です。これは「全国の少女」ということですよね。

短期連載主義の「マーガレット」で異例のロング・ランを誇っているとあります。
この当時、少女マンガといえば悲劇のヒロイン、そしてバレエ、ピアノ、バイオリン、日本舞踊といった芸事が定番だったんです。

「従来の画調を徹底的に利用し、少女マンガのファンの美意識を満足させつつ、スポーツマンガの定着に努めた」
少女マンガカテゴリとしての美しい描画は守りつつも、従来と全く異なるスポ根マンガを根付かせるのに成功したのです。