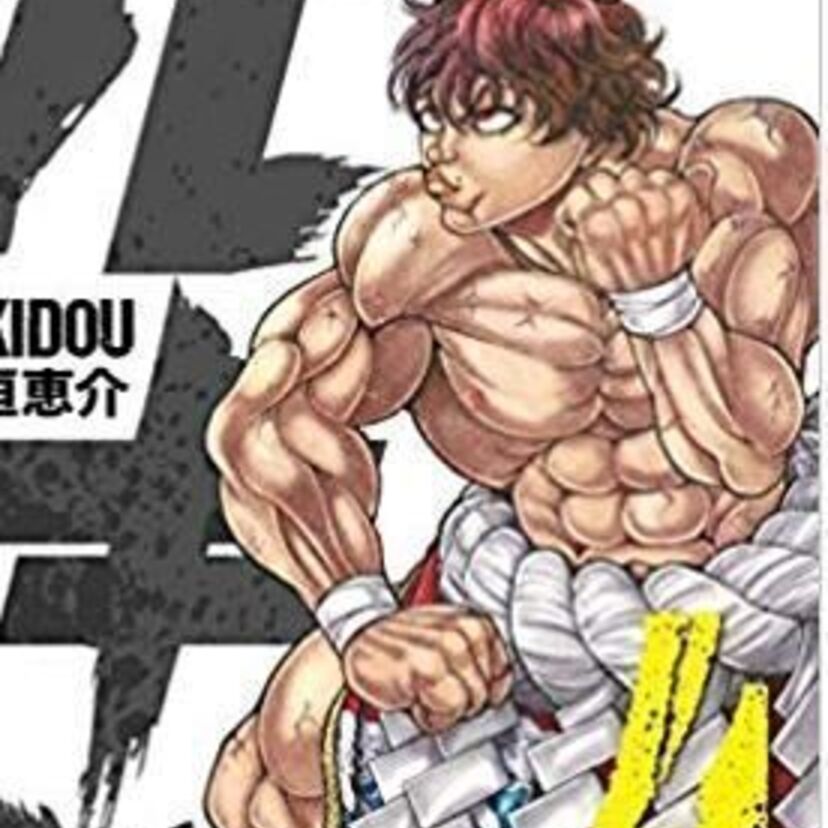板垣 恵介
漫画家
代表作:
『グラップラー刃牙』
『バキ』
『範馬刃牙』
『刃牙道』
『バキ道』
等々
プロレス

1957年4月4日、板垣恵介は北海道釧路市で生まれた。
ジェット機、軍艦、海賊、番長・・・
とにかく強いものが好きで、毎日のようにお絵かきした。
板垣恵介にとって最初の格闘技は、まだ幼稚園に入る前、ニュース番組で放送された「力道山 vs フレッド・ブラッシー」で、その感想は
「なんであんなに汗が出るんだろう?」
だった。
数年後、毎週、金曜日の夜にプロレスが放送され始め、ヒール(悪役)の外国人レスラーをやっつける力道山は敗戦によって外国に対してコンプレックスがあった日本人のヒーローとなった。
板垣恵介もモモヒキをはいて力道山ごっこをやった。

中学2年生のときに地元に国際プロレスの興行があり、板垣恵介は試合が始まる大分前に会場に行った。
そしてジャージ姿のストロング小林に会って、そのデカさに圧倒された。
試合が始まっても、選手の控え室に通じるドアの前から離れず、プロレスラーが通るたびにそのデカさに驚いていた。
ドアが開かれると、控え室の中もみえた。
腕組みをして立っているドン・レオ・ジョナサンは、190cmの長身で顔が壁に隠れていた。
ジョナサンが横へ移動すると、ドアの上に肘をかけたモンスター・ロシモフ(アンドレ・ザ・ジャイアント)がいた。
230cm236kg。
「The 8th Wonder of the World(世界8番目の不思議)」
「大巨人」
と呼ばれたデカさは別の生物だった。
ただのボディ・プレスが、巨体が相手を押し潰す様が圧巻で「ジャイアント・プレス」という必殺技となった。
ジャンプするプレスと両膝をついて相手に倒れこむプレスがあった。
飛行機でビールを1人で全部飲んでしまい、ワインをケースごと飲み干し、ゆで卵を1度に20個も食べた。
(バケモノ!)
叫びそうになるのをこらえ、板垣恵介はサインをもらいにいった。
するとモンスター・ロシモフ(アンドレ・ザ・ジャイアント)は、ゴツい顔に笑みを浮かべて応じた。
その指はプッシュタイプでもダイヤルタイプでも電話をかけるときはボールペンを使わなくてはならないくらい太く、パンフレットに万年筆で書かれたサインは力が強すぎてインクが飛び散っていた。
板垣恵介は、想像を絶するプロレスラーのデカさを大きく尊敬した。
またプロレスやプロレスラーは、どれだけファンをつくることができるかということだけでなく、どれだけアンチファンを生み出すことができるかという点も重要なことを知った。
「好こうが嫌おうが、どれだけ多くの人をひきつけられるか。
それが重要」
幻想がリアルだったアントニオ猪木

アンドレ・ザ・ジャイアントの凄みは肉体だった。
しかしアントニオ猪木の凄みは、
「本当に強い」
と思わせたことだった。
「プロレスこそすべての格闘技の頂点である」
といい、その証明のために異種格闘技戦を行った。
柔道のミュンヘンオリンピック金メダリスト:ウイリエム・ルスカをドロップキックからバックドロップ3連発でTKO勝ち。
ボクシングヘビー級チャンピオン:モハメッド・アリとの対戦は、アンバランスなルールに縛られた猪木が苦肉の策としてスライディングキック(アリ・キック)に終始し引き分け。
「世紀の凡戦」といわれた。
アリは左足を負傷して入院し、猪木はこの一戦のために何億という借金を背負い込んだ。
大巨人:アンドレ・ザ・ジャイアントをリバース・スープレックス、一本背負いで投げ、パンチと鉄柱攻撃で額を叩き割ってTKO勝ち。
パキスタンの英雄:アクラム・ペールワンをアウェイで対戦。
アーム・ロックが完全に極まったがアクラムはギブアップしないので猪木は腕を折った。
映画「Rocky」のモデルとなったヘビー級ボクサー:チャック・ウェップナーと対戦。
猪木はオープンフィンガーグローブを着用し、何度かダウンしながらも最後は空を切ったかにみえた延髄斬りがダメージを与え、逆エビ固めでギブアップを奪った。
「熊殺し」で有名な極真空手家:ウィリー・ウイリアムスとの対戦は、プロレス vs 極真空手という険悪なムードの中、殺気立った雰囲気の中で行われたが、猪木がウイリーを腕ひしぎに捕らえたままリング下に転落。
両陣営のセコンドが乱入し、収拾がつかず、ドクター・ストップの引き分けとなった。
板垣恵介はいまでも
「猪木は強かった」
と思っている。

また数々のエピソードを有するアントニオ猪木の一筋縄ではいかない人間性についても
「まっとうな人の住むまっとうな社会のルールでは最低の人間かもしれないけど、やっぱり借金が1円もなくて年収が500万円の人より、10億儲けて20億借金がある人間のほうが魅力的に決まっている」
「それがアントニオ猪木の人間的な強さであり凄みでもある」
と肯定的である。
例えば、アントニオ猪木は、血糖値596の糖尿病にかかったとき、インシュリン注射の力で治すのは自分の哲学に反するといい、自然治癒で血糖値180まで下げ44日後にはカムバック戦を行った。
その方法はどんぶり千切りキャベツを主食にし
「氷風呂に入り全身の筋肉をガチガチと痙攣させ血糖を消費させる」
と大量の氷を入れた水風呂に入るものだった。
IWGP(InternationalWrestlingGrandPrix)は
「プロレス界世界最強の男を決める」
というテーマで、開幕戦は日本、韓国-中近東-ヨーロッパ-メキシコとサーキットし、決勝戦はニューヨークという壮大なものだった。
しかし各地区のチャンピオンやプロモーターが協力を渋り、紆余曲折あり、新日本プロレスが2年という時間と莫大な費用を使用して準備してきた。
その第1回IWGP優勝決定戦:アントニオ猪木 vs ハルク・ホーガンは、一進一退だったが、途中、劣勢の猪木がエプロン際でホーガンのアックス・ホンバーを受け、リング下に転げ落ちて上がってこなくなってしまった。
レフリーのMr.高橘はカウントを数え出した。
「バカ野郎、待てよ」
坂口征二がそう叫びながらリングサイドから飛び出し猪木を抱えてリングに入れた。
しかし猪木はエプロンでうつ伏せになり、舌を出したままピクリとも動かなかった。
坂口は、舌が巻きついて呼吸困難ならないよう自分の履いていた草履を猪木の口に突っ込んだ。
そして猪木はすぐに病院に担ぎ込まれ面会謝絶になった
坂口は病室の外で待った。
翌朝、徹夜明けで病室に入るとベッドには猪木ではなく猪木の弟が寝ていた。
猪木は周囲の目を盗んで夜中にこっそりと抜け出していた。
ホーガン戦の約2カ月後、新日本プロレス内でクーデターが起きた。
クーデター側の主張は
「会社(新日本プロレス)は年間20億円も売り上げがあるのに利益が2000万円しか上がらないのは、社長である猪木が個人事業に回しているせい」
というものだった
その猪木の個人事業の1つにアントンハイセルがあった。
1980年に設立され、ブラジル国内で豊富に収穫できるサトウキビの絞りかすの有効活用法として考案された事業だった。
当時からブラジル政府は石油の代わりにサトウキビから精製したアルコールをバイオ燃料として使用する計画を進めており、アントン・ハイセルはバイオテクノロジーベンチャービジネスの先駆けだった。
しかし実際、プロジェクトを進めていくとサトウキビからアルコールを絞り出した後にできるアルコール廃液と絞りカス(バガス)が公害問題となった。
そこで家畜に飼料として食べさせると下痢を起こした。
バガスを肥料としえて土の中に廃棄すると土質を悪化させ、農作物が取れなくなった。
さらに追い討ちをかけるようにブラジル国内のインフレにより経営は悪化の一途を辿った。
こうしてアントンハイセルは数年で破綻し、その負債は数十億円ともいわれ、テレビ朝日に放送権を担保に12億円の肩代わりしてもらうがそれだけでは補えず、ついに猪木は新日本プロレスの収入の大半を補てんに回してしまった。
(2005年以降、地球環境問題や原油価格高騰などからサトウキビからエタノールを抽出するバイオ燃料事業は内容が見直され積極的に行われていった)
結局、初代タイガーマスク(佐山聡)、前田日明、長州力など多くの選手が新日本プロレスを去った。
(そして多くは戻った)

1989年6月20日には、「スポーツを通じて国際平和」を合言葉に「スポーツ平和党」を結党し、第15回参議院議員通常選挙に比例区から出馬。
キャッチコピーは
「国会に卍固め、消費税に延髄斬り」
そして最後の1議席に滑り込み当選し、史上初のプロレスラー国会議員となった。
「今話題になっているリクルート問題に対して私はこの一言で片付けたい。
逆十字固め!!」
「国会の場でも俺にしかできないことをやる」
1989年10月14日、福島県会津若松市で講演中、暴漢に刃物で襲われ左頸部などを負傷。
会場が一時騒然となる中、傷口をタオルで押さえたまま講演を最後まで行った。
1990年9月、イラクがクエートに侵攻。
湾岸戦争が危惧される中、サダム・フセイン大統領(イラク)は日本人を含む在留外国人を国外出国禁止とした。
事実上の人質、人間の盾だった。
日本の外務省による人質解放交渉は遅々として進まず、痺れを切らした猪木は決断した。
それはあえて緊張高まるイラクで「スポーツと平和の祭典」を行うため、被害者家族等を率いてバグダッドに向かうというものだった。
外務省はイラク行きを止めたが猪木は拒否。
外務省は被害者家族も止めたが、イラク邦人人質被害者家族「あやめの会」は猪木にすべてを託す事にした。
1990年11月、猪木は日本の各航空会社にイラク行きを要請したが、すべての会社が拒否。
やむなく猪木は、園遊会の会場で駐日トルコ大使に懇願したところ、チャーター機の費用を猪木個人が負担することを条件にトルコ航空の協力でイラク入りが可能となった。
1990年12月1日、猪木は平和の祭典関係者や人質被害者41家族46人と共にトルコ経由でバグダッド入り。
サダム・フセイン大統領は一国会議員でしかない猪木を国賓級の扱いで迎えた。
1990年12月2~3日、スポーツと平和の祭典には猪木の趣旨に賛同した各国の選手、ミュージシャンたちも参加した。
初日は、アル・シャープ・スタジアムでサッカー。
ナショナルシアターでロックコンサートと日本の大太鼓を初めとする伝統芸能や空手トーナメント。
2日目は、長州力、マサ斉藤 vs 馳浩、佐々木健介をメインとしたプロレス大会が開催された。
イベントが成功した一方で邦人人質と家族の面談は許されたものの解放までには至らなかった
猪木と家族たちは落胆の中、帰りの機内についた。
フライト直前、猪木はイラク政府から
「大統領からお話があります」
と告げられ、急遽、飛行機を降りた。
1990年12月3日、イラクの在留邦人の解放が決まった。
1990年12月5日、イラクの在留外国人全員の解放が決定した。
1991年2月、猪木は東京都知事選に出馬表明するも3月に断念。
その後、
「行動派として尊敬していたアントニオ猪木氏が突然、知事選出馬を取りやめたことがきっかけ」
と内田裕也が出馬。
政見放送で、ジョン・レノンの『パワー・トゥー・ザ・ピープル』を歌った。
1993年5月17日、
スポーツ平和党で猪木の公設秘書だった、そして猪木に解雇された佐藤久美子が
「例え返り血を浴びるような結果になっても猪木議員の不正を告発し、その議員生命を断たせたい」
と「週刊現代」誌に
「還付金の不正所得による巧妙な脱税工作の実態と3億円に及ぶ巨額の税金滞納」
という告発を行った。
この記事は5週にわたって取り上げられ、「議員秘書、捨身の告白」という書籍も刊行され
「政治資金規正法違反」
「賄賂」
「脱税工作」
「税金滞納額3億円」
「猪木と佐川(急便会長)&皇民党(右翼団体)の闇のトライアングル」
「選挙応援で1億円の謝礼」
「都知事選出馬撤回を取引に受け取った巨額な佐川マネー」
「右翼(日本皇民党)との癒着問題」
「女性問題(カンボジアで13歳の少女買春)」
「猪木議員手作り1000円(成田空港で本を買い「本代1000円借りました 猪木寛至」と書いた紙を渡した)事件」
「旧ソ連でマンモスの牙不正輸入」
などの悪行が暴露された。
1993年6月30日、疑惑まみれの猪木は記者会見を開き、暴露本や週刊誌に出た数多くのスキャンダルを完全否定。
「なぜちゃんと反論しないのか」
と聞かれ
「めんどくせえ!!」
の一言で終わらせた。

刃牙と対戦した猪狩完至は、試合前に
「勝ちを譲っちゃくれんか」
と哀願し涙を浮かべて土下座。
試合開始後はへなちょこキックとへなちょこパンチを繰り出した。
刃牙にフロントネックロックをかけられると、早々にタップ。
勝ったと油断した刃牙に
「イッツッ ショータイムッ」
と金的蹴り。
「誰も聞いちゃいねェんだよ。
俺のギブアップなんて」
と本気のパンチとローキック。
そして刃牙にプロレスをさせて
「気楽なもんだぜ格闘家なんてものはよォ」
「だいたいよォ、技を受けなくてもいいんだからなァお前らは」
という。
プロレスラーは仕掛けられた技からは逃げない。
すべて受け切る。
技を受けるために覚悟を決めて筋肉を硬直させることでダメージに耐え切る。
「故に覚悟の量を見誤ると即座にあの世行き」
だが人間の反射神経をも凌駕する刃牙の速攻に、覚悟する瞬間=筋肉を硬直させるヒマすら与えられれず、勝負アリかと思われたとき、
「お袋ォッ」
突然、刃牙の母:朱沢江珠に似た女性が現れた。
変装した猪狩完至の愛人だった。
一瞬の気をとられたスキに猪狩は必殺のオクトパス・ホールドを極めた。
ジャイアント馬場

ジャイアント馬場は、脳天唐竹割、ココナッツクラッシュ、川津掛け、16文キックなど、209cmの巨体を利用した豪快な技で、NWA世界ヘビー級王座に3度就いた。
「刃牙」の中で、上空からマウント斗羽が落ちてきて頑丈なアメ車(アストロ)を破壊するシーンがあるが、板垣恵介は、ジャイアント馬場の強さを、その頑丈さだと思った。
またそのスローモーな動きは一流の格闘家ではないが、
「立っているだけで絵になる。
そんな男は俳優でも稀である」
と長年修羅場をくぐりぬけ大きな仕事をやってきた人間力の強さを認めている。
板垣恵介は、格闘技とプロレスは別物であることを理解した上で、プロレスラーをみるとき、
「本当にやったら強いんだろうか?」
「あの格闘家とやったらどっちが強いんだろう」
と思ってしまう。
そういう最強幻想という意味でも、アントニオ猪木とジャイアント馬場を超えるプロレスラーはいなかった。