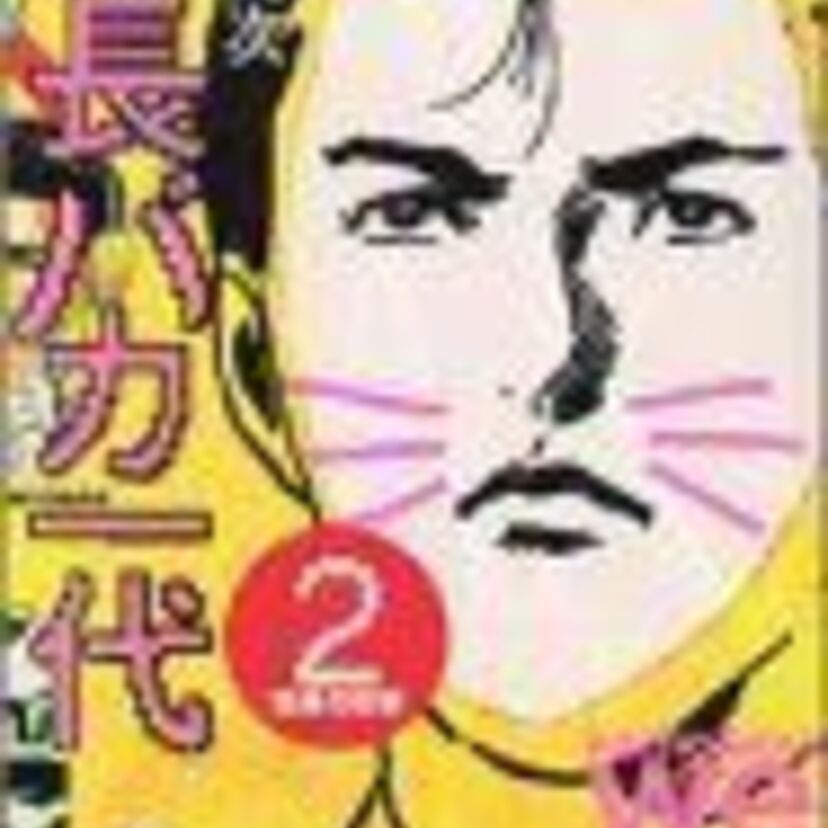前回の記事はこちら。
【バカらしさに絶句】「課長バカ一代」(漫画)の第1巻を見る - Middle Edge(ミドルエッジ)
松芝電機の「画期的新商品」はまだまだあった!!。
前回、ボールペン一体型ラジオ「ラジペン」と、バカでも使えるパソコンOS「ウイントース95」をご紹介しましたが、まだまだ松芝電機の商品開発は続きます。
様々な「迷」商品が松芝から登場し、その真価を世に問うていきます。
「洗えん坊将軍」
もはやガス会社と一体化して開発するような、いや、それともオール電化のお宅をターゲットにしているのか、「洗濯機」と「お風呂」を合体させてしまいました。
お風呂の残り湯を洗濯に使う人は多いと思いますが、いちいち洗面器やポンプでお風呂から洗濯機に水をくみ直すのが面倒!ということで、なんと浴槽ごと洗濯機にしてしまうという、斬新な発想。
他社の追随を許さない「画期的商品」にNCEからの産業スパイが侵入!!。
そこに、NCE(決してNECではありません!)から、松芝電機にこの「画期的」技術を盗もうと、産業スパイが侵入します。
しかし、そこに立ちはだかるのは、松芝電機の期待の星、八神です。
八神は、自分の家の洗濯機が壊れ、秋葉原に行くのを面倒がり、試作の「洗えん坊将軍」を勝手に使います。
「シロートでも簡単操作」が売りなのは、前回の「ウイントース95(決してウインドウズではありません。)」と同じですね。
産業スパイが勝手に撤退。
この「洗えん坊将軍」のデータを集めようと、試作品の設置場所に忍び込んだNCEからの産業スパイ。
しかし、スパイが到着すると、八神は既に今着ているワイシャツまで脱いで洗った後に、風呂に入っていました。
この行動をみて、スパイは勝手に八神もスパイなのだと思ってしまいます。
スパイは、「データを取るより、実際に使うのが一番だった!」と勝手に敗北を認め、去っていきました。
こうして、八神は洗濯と風呂と、産業スパイの撃退という3つの「任務」を完了します。

「洗えん坊将軍」で入浴する八神。
講談社「課長バカ一代」野中英次作 1巻 第14章より。
「コメっとさん」
「全自動米とぎ機」。
言葉を見るだけで「アホかいな!」と思ってしまう新商品です。
しかも、「NASAの新素材を使用した松芝電機の自信作」ということで、社内で説明会を開きます。
技術部門が「PL法」に対応しているか、疑問を提議する。
この「PL法」って言葉も懐かしいですね。
この作品の書かれている当時では、まだ日本にはPL法が浸透していなかったようですが、さすが技術部門の責任者、「洗濯機で犬を洗ったら洗濯機が故障したという事例が欧米で起こっている。そのような事態になったら誰が責任を負うのだ」と、厳しい追及を商品開発にぶつけてきます。
さあ、八神はこの追及に、どう答えるのでしょうか。
その場合には、私が全責任を取る!!
八神はこう答えます。
しかし、すぐに、「一介の課長に過ぎないアナタが、どう責任を取るのか」と返されます。
当たり前の返し方です。
しかし、次に八神が答えたのは・・・?