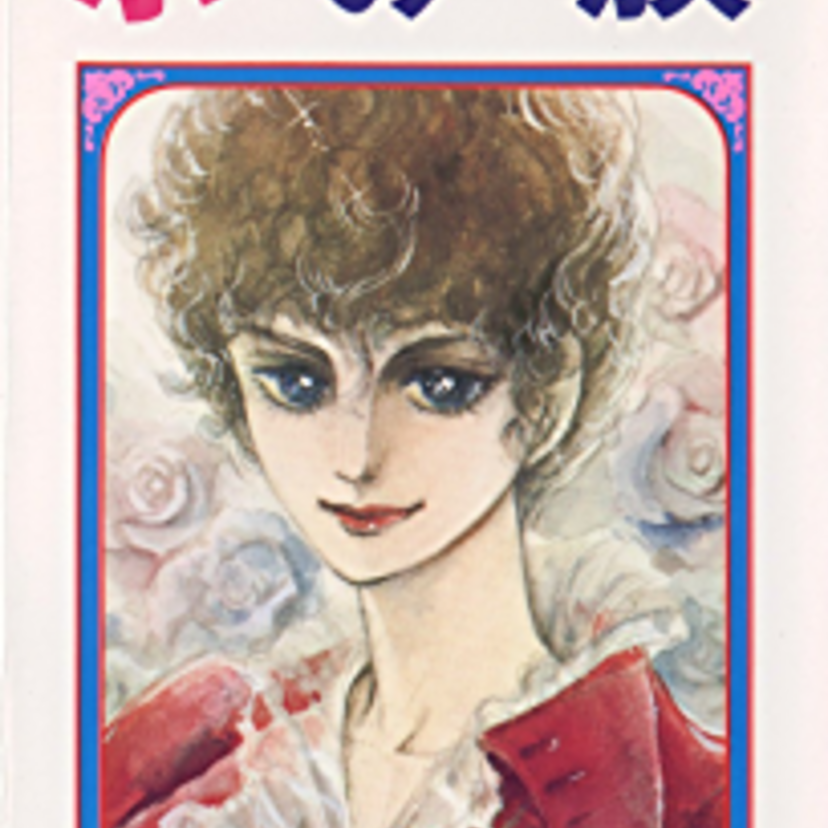いわゆる少女向けの「少女マンガ」が、より幅広い層に受け入れられる「文化」となる、ちょうど過渡期にマンガを読んできた人間として、当時のことを語ってみたいと思います。
24年組とは?
1970年前半に、少女マンガはひとつの転換期をむかえます。
むかえる、というより、マンガの作り手たちからのムーブメントが起こり
それを受け入れる読者が増えてきた、そういう時代です。
そしてその作り手の中心にいたマンガ家が、だいたい昭和24年前後生まれだったことから
「24年組」もしくは「花の24年組」と称されました。
それまでの少女マンガ 24年組の台頭まで
キラキラおめめの少女マンガ
およそ当時掲載されていた「少女マンガ」は、このように世間的には思われていました。
・目が大きい、まつ毛が長い
・目の中に星、しかも不自然なほど
・アップが多い(なおかつ、左向きばかり)、全身像は少ない
・人物の描き分けができていない
・男性(特に成年、老年)が描けない、登場しない
・過剰な装飾(バックに花など)
・描画が平面的
・背景が描かれていない、もしくは下手
・ストーリー性がない、あるいは類型的
(学園ラブコメ、スポ根、薄幸な美少女ものなど)
当時のすべての少女マンガがこうだったとは思いませんが
「少女マンガ」とレッテルがつくとき
それは上記のようなことを揶揄して切り捨てるかのような扱いをされていました。
「少年マンガ」と比較して、語るべきほどのものもないとされていたのです。
選択肢がない、表現の幅も広がらない
なぜこういった内容のものが多かったのか。
出版側が「こういうものが受けるから」と思い込んでいるため、
誌面にほとんど選択肢はなく、読者アンケートも似たようなものを選ぶしかありません。
出版社側もアンケート結果を見て、さらに決めつけを強化し
たとえ描き手が、実験的なものを描きたいと思っても
編集者にダメを出されてしまうわけです。
そういう膠着した状態が、きっと続いていたのだと思います。
はじまりは、後発誌「少女コミック」の苦肉の策から
当時の少女漫画誌は「少女フレンド」「マーガレット」が中高生向け2大誌。
「なかよし」「りぼん」は、ターゲットの年齢層の若干低い2大誌でした。
そこへ後発誌として出てきたのが「少女コミック」(小学館)です。発刊は1968年。
当時「マーガレット」では『アタックNO.1』、「少女フレンド」では『サインはV!』が連載されていて、バレーボールスポ根ものの全盛期。
その後「マーガレット」では
池田理代子『ベルサイユのばら』、山本鈴美香『エースをねらえ!』、
「なかよし」では『キャンディ♡キャンディ』の連載を開始、
「少女マンガ」という、これまでのワクからは出ない世界ながら、少女マンガの業界は興隆していきます。
少女マンガ界が盛り上がる結果、執筆する作家の確保に難儀した「少女コミック」は、
後発誌で、まだ少女マンガ誌として形ができていなかったことを逆手に取り、
作家に自由に描かせるという方法で、意欲のある描き手を集めて行きました。
その筆頭が、萩尾望都でした。
とにかく「SF」を描きたい 萩尾望都
萩尾望都は1949(昭和24)年大牟田市生まれ。「望都」は本名。
高校時代にマンガ家を志し、卒業後専門学校に学びながら投稿を続け、
「なかよし」(講談社)1969年夏の増刊号にて『ルルとミミ』でデビュー。
しかしながら「なかよし」編集部の意向は従来通りの「少女マンガ」。
自分の描きたいものを描かせてもらえない状態が続いたところ
「少女コミック」編集部から声がかかります。
「恋愛」要素のない、抒情の小品
もちろん編集部側としては、恋愛要素を排除してと依頼したわけではないと思います。
萩尾望都も、恋愛要素のある、ミュージカル的な展開のものも描いています。
ですがやはり、恋愛のない、ストーリー性に満ちた、短編小説に近い形のものを
当時から発表していました。
「自由にわがままに思い切り描かせる」というのが、編集部の方針だったそうです。
たとえば『かわいそうなママ』(1971年「別冊少女コミック」5月号)

『かわいそうなママ』「別冊少女コミック」5月号より
小学館文庫『11月のギムナジウム』p172 1995.12