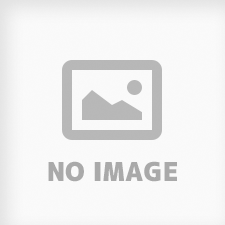はじめに

SLOTの画像です、大迫力ですね!
今回は僕にとって思い入れの強い機体が多いので文章が少し長くなるかもしれません。しかし当時から今でも思うところが多い作品群の時期でその辺はもし、時間があればお付き合いいただければ幸いです。
僕の感じたこと、感じている事がうまく伝わればいいのですが・・・
機体の並び順はUCの時間軸上に合わせているつもりですが、開発の始まりと完成は必ずしも順序が一致するとは限りませんので多少前後しているかもしれません。悪しからず。
第2世代から第3世代へ 可変機登場の産みの苦しみ
MSN-00100

百式[HYAKU-SHIKI]
MOBILE SUIT Illustrated 2015 機動戦士ガンダムMS大全集2015
さて、いよいよ可変機の登場かと思いきや、この機体がその初めての・・・記念すべき1機であったはずが・・・産みの苦しみとはこういうものなのでしょう。可変型のガンダムタイプMSとして設計されていたが、技術不足からこれを断念し通常のMSとして完成したという経緯は詳しく説明をするべきとはいえ、余りに長くなりますのでかいつまんで・・・。
「本機はまず非可変型MSとして設計され、その後可変型MSへの転用を検討、最終的に再び非可変型MSに差し戻された開発経緯を持つ。」と資料にあるということは何があったのか。『エゥーゴがガンダムMK-Ⅱ強奪に成功し、実機を実戦投入しておりそのノウハウを持っていたこと、そのことからAE社にも強奪したうちの1機が持ち込まれ解析され「ムーバブル・フレーム」の開発が進んだこと、リック・ディアスに使われたガンダリウムγ合金がその性能の高さを実証していたこと等により可変機の開発が可能と思われたこと』などにより、設計の時点で変更されていました。しかし開発途中コンピューターによるシミュレーションの段階で変形時のバインダーの耐久性と駆動部のストレス、ムーバブルフレームの強度の問題が解決できず、その構造上の問題から計画を断念せざるを得ませんでした。しかし非可変機といえどもその性能は高くこれを実機として開発、実戦投入可能にしたものです。
第2世代MSとしてはエゥーゴとAE社共同開発の初めての機体でしょう。
それは時間との兼ね合いがあったのでしょう、一刻も早く実機をアーガマに送り込まねばならなかったという事だったのではと想像できます。(クワトロ・バジーナ大尉専用機として)
可変機登場!
MSA-005

メタス[METHUSS]
MOBILE SUIT Illustrated 2015 機動戦士ガンダムMS大全集2015
メタス - Wikipedia
一年戦争も終わり、各地で頻発していた小規模なゲリラ戦が続く中、連邦軍は一年戦争当時よりもさらにピッチを上げてMSの開発に力を注いでいたようです。
そしてUC0083年を迎え、デラーズ・フリートの抗争という大紛争が起きます。このことは連邦軍にさらなる危機感を持たせるに至り、ティターンズの勃興を呼び起こします。このことが連邦軍内部での軋轢を生じさせたのは言うまでもないでしょう。
なぜ今更のようにこの部分をピックアップするかと言えばここからティターンズ対エゥーゴという図式が発生し、両者共に画期的な技術を手に入れたからです。
そうMSの第2世代の幕開けです。ティターンズは「ムーバブル・フレーム」の開発に成功し、エゥーゴはクワトロ・バジーナの持ち込んできた新素材「ガンダリウムγ合金」を手にし、
そして新興ではあるものの既に既存の軍事産業(旧ジオン公国所属企業も含め)を吸収し巨大企業となっていたアナハイム・エレクロニクス社(以下AE社)が(裏表のある企業ですね。どっからそんな金を用意したのでしょうね?答えは…)地球圏に近づいてきたアクシズの技術さえ利用しながら介在することで次の第3世代MSまで視野に入れる事となったようですね。
エゥーゴはガンダムMK-Ⅱを奪取することにより「ムーバブル・フレーム」の技術をAE社と共に解析、転用し、考えとしてはこの時代以前よりあった可変機の開発計画「Z計画」に取り込む形でトライすることになり、ティターンズも素材の問題をどこから漏洩したかは判りませんが「ガンダリウムγ合金」まで入手することから解決、「TMS」(Transformable Mobile Suitの略)の構想を実現しようとしていた時期でした。そして上記引用の通り先に可変機を手にしたのはエゥーゴでした。「メタス」の登場です。それにしても原型とされる「アニュス・デイ」とはどんな機体だったのでしょう?AE社が自衛のために使い又自動で動いていたとの説も在り、なんの資料も無いまま姿を消しています。一体どんな機体だったのか僕で無くとも知りたいですよねw。言葉通り「神の仔羊」であるならば「神」は一体誰なんでしょう・・・
MSZ-006X1

プロトZガンダムX
さてこの3機、非可変機ながらかなりの高性能機だったようですが、戦力UPを急務としていたエゥーゴでなぜ実戦配備された記録が無いのでしょう?それほどピーキーな機体だったのでしょうか?それでは誰がテストパイロットを務めたのでしょうか?様々な資料の矛盾と言い疑問だらけの機体です。まぁそれは置いておくとしても、いよいよZガンダムの完成間近との感じがひしひしと伝わってくることを告げている機体と言えるでしょう。
MSZ-006

Zガンダム[Z-GUNDAM]
MOBILE SUIT Illustrated 2015 機動戦士ガンダムMS大全集2015
Ζガンダム - Wikipedia