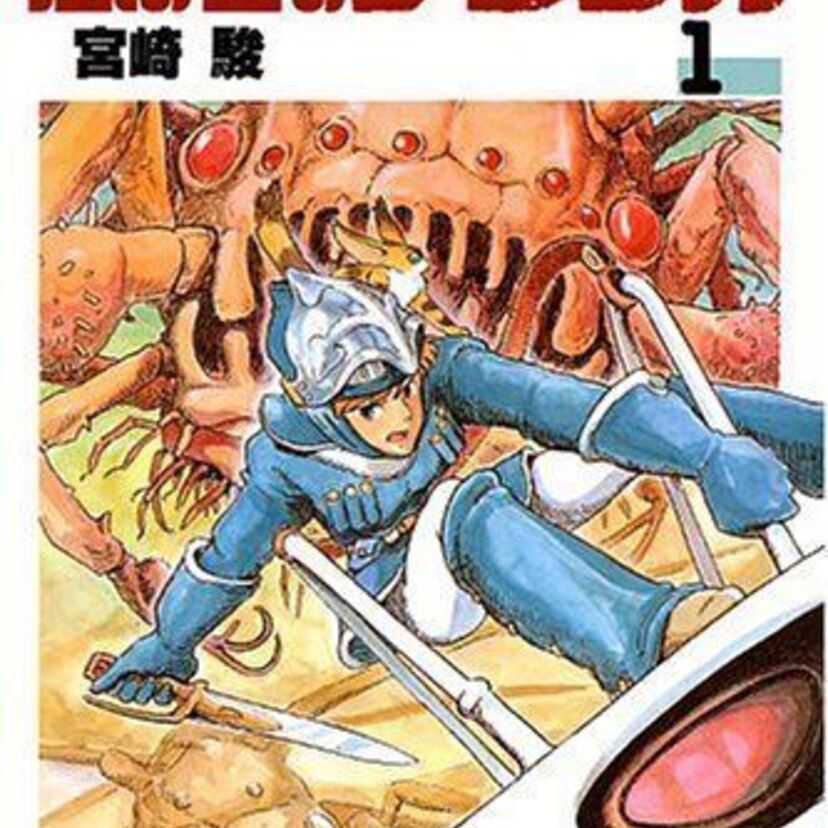『風の谷のナウシカ』と『AKIRA』
本作『風の谷のナウシカ(以下『ナウシカ』)』は、誰もが知っている国民的アニメとして、1984年に(まだその頃、ジブリという企業はなかったが)漫画を描いた宮崎駿監督自身によってアニメ化されたことで有名である。
そういう意味で「天才が、自分で描いた漫画を、自ら監督してアニメにする」という意味では、1988年に公開された、大友克洋原作・監督の『AKIRA』と同じ構造であり、しかしそこには意外な相似性もあって面白い。

AKIRA(1) (KCデラックス ヤングマガジン)
AKIRA(1) (KCデラックス ヤングマガジン) | 大友 克洋 |本 | 通販 | Amazon
『ナウシカ』も『AKIRA』も、原作漫画は多段構造の、複雑な世界観構成で成り立っている漫画である。未来SF、それも、当時流行していた「人類の終末以降」という、『ノストラダムスの大予言』以降『ネクロマンサー』『マッドマックス2』(原題: Mad Max2:The Road Warrior1981年)への流れの隆盛期というわけではないが、当時のSF界隈はその辺りをうろうろしていた。
『ナウシカ』『AKIRA』もその流れにあり、物語上の大きな括りとしては「人類の再生」が挙げられるが、メタ的には「原作は、複雑に入り組んだ構造を、アニメ化するにあたって、当の原作者の陣頭指揮の元、徹底した換骨奪胎が行われ、テーマ性をも犠牲にして“見せ場主義”が貫かれ、結果、アニメ版だけ観ている人には、ものすごくシンプルな勧善懲悪作品だと誤解されるような映像版を、あえて作って成功した」というのも挙げられるだろう。
この時期、特に思春期向けアニメは「試されている時代」であり、富野由悠季監督の『機動戦士ガンダム』(1979年)でピークに達した思春期向けアニメブームが、そのまま世代や時代とシンクロして、一つの定着したコンテンツになっていくのか。それとも一過性の現象で終わるのか、それとも、ごく一部の好事家達だけを市場にした、閉じたビジネスへ落ち込んでいくのか。結果、時代の選択は非情にも三番目であったが、まだそこへ落ち込む前に、先にサブカルチャーとしては、先鋭化を極めていた漫画というプラットフォームで、充分に深遠な設定と世界観を描き出していた『ナウシカ』『AKIRA』が、広く老若男女を劇場に呼び込まなければいけない、二時間しか尺がない「アニメ映画」というメディア変換の岐路で、同じ選択をしたことの意義と意味は、もっと深く追及されても良いだろう。
とりわけ、原作物語の複雑さや設定の深遠さを切り捨て、主に原画や作画、映像ならではの「動きの演出」に特化することで、作劇テーマをエンターテイメントのコンテンツテーマに置換しつつ、それぞれの「『ナウシカ』らしさ」「『AKIRA』ならでは」を、表現していたことは、それぞれの個論としての評価以外においても、当時の劇場用映画アニメの限界論としても評価されていいかもしれない。決して原作漫画が放とうとしたテーマが、映画的に難しすぎるという問題ではないということは、この時期既に多種多様なハリウッドのSF映画群がそれを証明している。
『風の谷のナウシカ』と『戦闘メカ ザブングル』
『ナウシカ』原作版は、これも読んでいる方は多いだろうから詳細は省くが、アニメ版とは意図的に価値観がずらされていて、主にナウシカやそこに生きる人々が、「火の七日間」を境に、実は読み手の我々側ではなかった、遺伝子操作による人工ミュータントだったという設定が明かされる。
つまり、「近未来。地球は一度最終戦争に陥ってしまい、結果的に人類は絶滅寸前になり、地上は生きることも難しい世界に変わり果ててしまった。そこで“地上で生きるために”生み出された人工人類。ミュータントが主人公。この主人公はミュータントといえど、それまでの未来SFに搭乗した“冷たい”存在とは違い、むしろ人間性の発露。人間の、本来の“生きるバイタリティ”をそのままに復元した形で、躍動感と喜怒哀楽、生命感に溢れた人物像として活躍していく。その主人公の周りにも、ミュータント的なる存在達は多く描かれ、むしろそこで描かれる“敵”こそが、人を滅ぼすきっかけとなった旧人類の執着とエゴの残した遺産のような存在でもあり、主人公は様々な冒険を経て、世界を滅ぼすに至った旧体制的な思考に取りつかれてしまった亡霊のような旧人類の残党(我々現代人の末路)を相手に、勇気と活力と体力と生命力で“本当の人間とは、そもそもどのように生きるべきであったのか”を体現しながら、旧人類が滅ぼした世界で生きれるがゆえのミュータントでありながら、ミュータントの存在そのものが、本質的な人間論、人類賛歌となり替わっていく。つまり、作品全体が、現状(当時)の人類社会の在り方を否定して、ネクストワールドに生まれるだろう人類こそが、本質的な“人間”なのだろう、そうあるべきだというメッセージを中核にして描かれている」ということになる。
はたして“これ”がどの程度、80年代のSFシーンにおいて「ありきたりな着想」だったのかは分からない。
「最終戦争の後の、荒廃した未来の世界観」から始まるで言えば、『猿の惑星』(原題: PLANET OF THE APES 1968年)も『マッドマックス』(原題: Mad Max1979年)も『北斗の拳』も一括りで、決して軽々とまとめてしまっては散漫な論になってしまうだろうからだ。
しかし、その一方で、筆者のこれまでの書評やコラムを読んでくださって来た皆様には「またか」と言われるかもしれないが、今、上で書いた大枠が、すっぽりそのまま当てはまる作品が他にもあるのである。
それは、既に紹介した『機動戦士ガンダム』の富野由悠季監督による『戦闘メカ ザブングル(以下『ザブングル』)』(1982年)というアニメである。

戦闘メカ ザブングル 完全設定資料集 (DNAメディアブックス 完全設定資料集シリーズ)
戦闘メカ ザブングル 完全設定資料集 (DNAメディアブックス 完全設定資料集シリーズ) | 書籍編集部 |本 | 通販 | Amazon
このアニメは、あくまでコメディドタバタロボットアニメの体裁を取り繕いながらも、根底に流れている設定は悲惨だ。「“惑星ゾラ”と呼ばれている“地球”」というオープニングナレーションから始まり、ロケーションと背景はどうみても西部劇なのだが、そこにウォーカーマシンと呼ばれる、土木作業機械のようなロボットや、戦艦のような地上用移動母艦が登場し、主人公が乗るウォーカーマシン・ザブングルに至っては、さしずめ青く塗ったガンダムのように、ヒーロー兵器っぽい。
そこでは、富野監督の「いつもの」エピソードが存在しているのだが。
当初、このアニメの企画をした日本サンライズ(当時)は、『エクスプロイター』という、宇宙戦争ロボットアニメの設定骨子を考えていた。そこでの要素のいくつかは、後の同社制作アニメ『銀河漂流バイファム』(1983年)に活かされるのだが、当初の総監督が都合で退き、劇場版『伝説巨神イデオン』(1980年)の製作で忙しい富野監督に無理矢理総監督のバトンが委ねられ、様々な会社事情やスタジオの熟練度、今現在自分に任されている仕事量とのバランスを考えた富野監督が、ホテルにこもりきりで三日で全ての設定をひっくり返して考えたのが、『ザブングル』の世界観と設定だった。