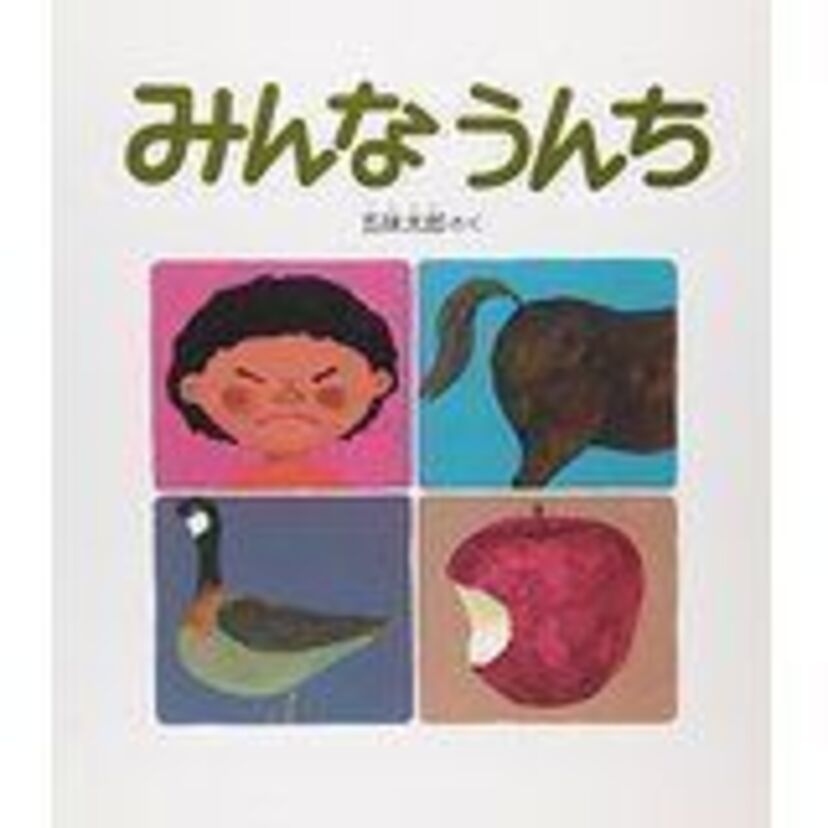幼い頃に読み聞かされたり、小学校の図書としても親しみ育ってきた五味太郎(ごみ たろう)の絵本。
柔らかな絵のタッチに隠されたユーモアがとても痛快でした。
愛情溢れる五味の作品を、いくつか年代を追ってご紹介します。
時代を経ても楽しめる五味の世界をご堪能ください!
1977年、『みんなうんち』
1977年7月1日に発売された『みんなうんち』。
本書で五味は”動物はみんなうんちをするものだ”と伝えています。排泄物という一見扱い辛いテーマを五味独特のユーモアで描いています。
ミッフィーを日本に紹介し、福音館書店の編集者としていわさきちひろなどを発掘した松居直は、本書を「知識の枠を超えた科学の絵本」と評し、「意外性と語りのユーモア」が「心に残る絵本体験」を生みだしたとしています。

『みんなうんち』
みんなうんちとは - goo Wikipedia (ウィキペディア)
1978年、『たべたの だあれ』
第25回サンケイ児童出版文化賞した絵本『たべたの だあれ』。1977年に文化出版局より発売されました。
「どうぶつあれあれえほん」シリーズでは他に『かくしたの だあれ』があります。
同書はページをめくる度に登場する動物が増えていき、数も覚えることができる仕掛けがあります。
当時はまったく気が付きませんでしたっ!

『たべたの だあれ』
1986年、『ことわざ絵本』
1986年に岩崎書店より発売された『ことわざ絵本』。
一つのことわざを1見開きで構成。右が従来通りの絵と解説、左が五味の創作した面白ことわざになっています。発売後にロングセラーとなり、五味の代表作の一つと言えるのではないでしょうか。

『ことわざ絵本』

「帯に短したすきに長し」のページ
1990年、『らくがき絵本 50%』
1990年にブロンズ社より発売された『らくがき絵本 50%』。
「らくがきこそが絵のはじまり」と五味太郎が、らくがきの楽しさを伝えるかきこみ式絵本です。
大ボリュームのページに塗り絵やことば遊び、めいろなどが散りばめられた楽し過ぎる一冊。
以降、「らくがき絵本」はシリーズ化され、人気の絵本となっています。
アメリカ、イギリス、スペイン、フランスなど海外でも翻訳され、発売されています。
フランス版が現地で人気となり、各国で翻訳されるきっかけとなったそうです。