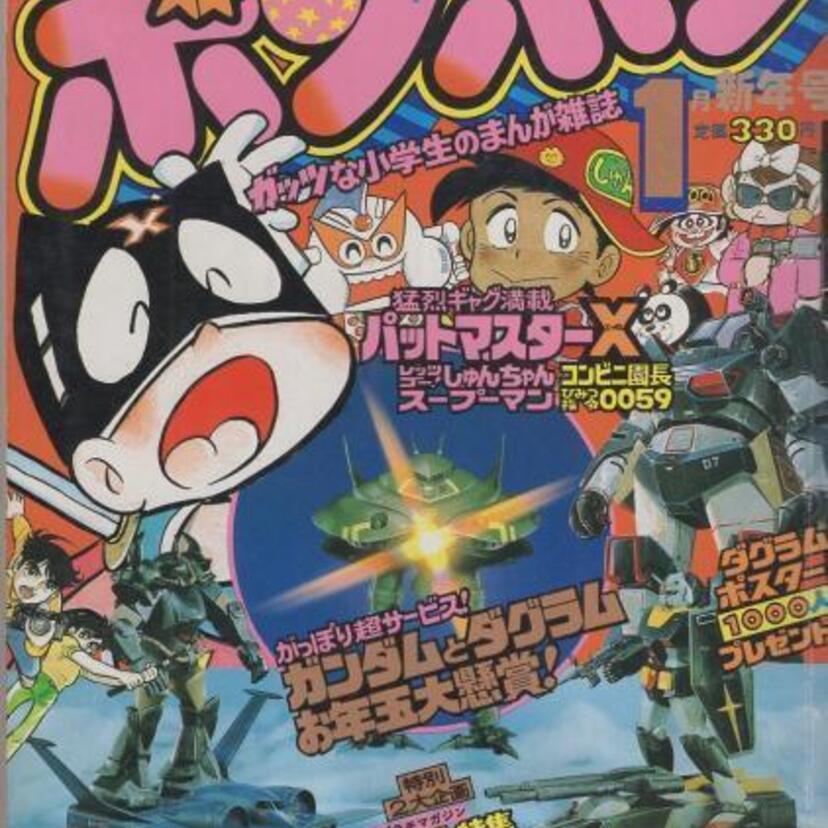少年画報社『少年キング』(1988年休刊)
『週刊少年キング』は少年画報社が1963年に創刊した、少年マガジンや少年サンデーに続く日本で三番目の週刊少年誌です。
1982年に月2回刊の『少年KING』にリニューアルしたのち、1988年に休刊となっています。
60年代から70年代にかけては『サイボーグ009』(石森章太郎)、『柔道一直線』(梶原一騎・永島慎二→斎藤ゆずる)、『怪物くん』(藤子不二雄)、『アパッチ野球軍』(花登筺・梅本さちお)など錚々たる顔ぶれの連載陣を揃えました。
また70年代半ばからは『ワイルド7』(望月三起也)と『サイクル野郎』(荘司としお)が二枚看板となり、他紙とは一味違う連載ラインナップで独自性を見せていきます。
しかし1975年の誌面一新に伴い、連載作品の大半を打ち切ってしまったことで読者離れを起こし、一気に人気が低迷。『銀河鉄道999』(松本零士)、『超人ロック』(聖悠紀)、『5五の龍』(つのだじろう)、『まんが道』(藤子不二雄)などのヒット作はありましたが部数回復には至らず、1982年には一時休刊にまで至ります。
三か月の休刊期間ののち、1982年に当時の漫画界ではまだ珍しかった月2回刊の『少年KING』として復活。
『湘南爆走族』(吉田聡)と『ペリカンロード』(五十嵐浩一)が新たな二枚看板となりましたが、それ以外のヒット作には恵まれず、1988年に再度の休刊となりました。
なお少年キングから名前を受け継いだ青年漫画雑誌『ヤングキング』は、現在も少年画報社より刊行中です。
講談社『少女フレンド』(1996年廃刊)
『少女フレンド』は講談社が1962年より刊行を開始した歴史ある少女漫画雑誌です。
直前に廃刊となった少女向け月刊誌『少女クラブ』の路線を受け継ぎ、当初は週刊、1974年以降は月2回刊として発行されてました。
初期には、ちばてつやも作品を掲載していた少女フレンド。1970年前後からは『サインはV!』(神保史郎・望月あきら)、『アリエスの乙女たち』(里中満智子)、『はいからさんが通る』(大和和紀)などの今も語り継がれる作品が生まれます。
一方で『ねこ目の少女』(楳図かずお)、『聖ロザリンド』(わたなべまさこ)、『不思議のたたりちゃん』(犬木加奈子)等のホラー漫画の系譜が続くなど、少女漫画といえば恋愛ものという枠に囚われない多彩な作品が掲載されていました。
また1977年から連載開始した『生徒諸君!』(庄司陽子)は、続編を含めると通算90巻以上となる長編シリーズになっています。
しかし1980年代以降、少女フレンドは新たな大ヒット作に恵まれなかったこともあって徐々に勢いを失っていきます。1991年には月2回刊から月刊へと刊行ペースを変更しましたが、その後も失速は止まらず、最終的に1996年をもって廃刊となりました。
なお、少女フレンドの姉妹誌である『別冊フレンド』は現在も刊行中であり、また1996年に刊行を開始した月刊誌『デザート』は、少女フレンドから執筆陣を引き継いだ事実上の後継雑誌となっています。
徳間書店『月刊少年キャプテン』(1997年休刊)
『月刊少年キャプテン』は徳間書店が1985年より刊行を開始した少年漫画雑誌です。
競合他誌よりもディープな漫画ファン向けの連載陣が当時の読者を惹きつけました。
『少年キャプテン』はアニメ雑誌から派生した『別冊アニメージュ SFコミックス リュウ』の流れを汲む雑誌だったため、少年誌としてはかなりマニアックな作品も受け入れる方針を打ち出していました。
『宇宙家族カールビンソン』(あさりよしとお)、『強殖装甲ガイバー』(高屋良樹)、『GREY』(たがみよしひさ)などのSF漫画の他、『みすて♡ないでデイジー』(永野のりこ)、『夢幻紳士』(高橋葉介)、『逆境ナイン』(島本和彦)など、オンリーワンの魅力を持った作品をいくつも送り出しています。