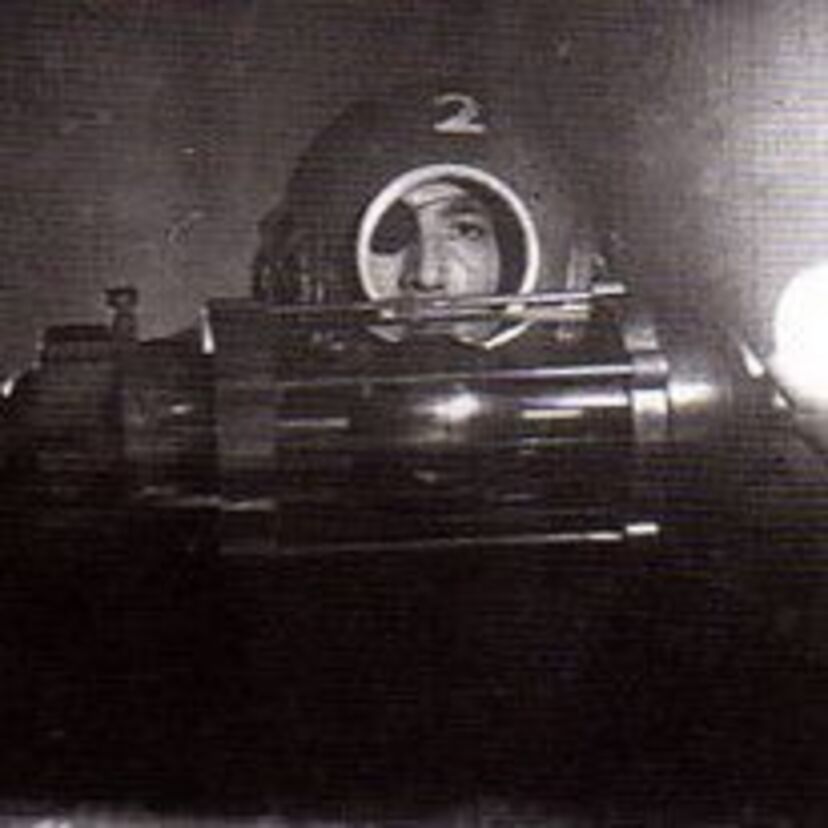オキシジェン・デストロイヤー(水中酸素破壊剤) 登場作品:東宝特撮映画『ゴジラ』(1954年)

オキシジェン・デストロイヤー

仁工房の原寸大模型『オキシジェン・デストロイヤー』

芹沢博士が『オキシジェン・デストロイヤー』でゴジラを倒す -「ゴジラ」(1954年)-

芹沢博士オキシジェン・デストロイヤーのスイッチを入れた。

瞬く間に海中に広がるオキシジェン・デストロイヤー。ゴジラはもがき苦しみながら、海中で骨まで溶けていった…。

オキシジェン・デストロイヤーで骨まで溶け液化するゴジラ
東宝特撮映画の陸上兵器
メーサー殺獣光線車(66式メーサー殺獣光線車)

メーサー殺獣光線車(66式メーサー殺獣光線車)

メーサー殺獣光線車(66式メーサー殺獣光線車)

メーサー殺獣光線車(66式メーサー殺獣光線車)
その他のメーサー兵器・メーサー車

90式メーサー殺獣光線車

90式メーサー殺獣光線車

93式自走高射メーサー砲(ツインメーサータンク)と92式メーサー戦車(メーサータンク)

92式メーサー戦車(メーサータンク)