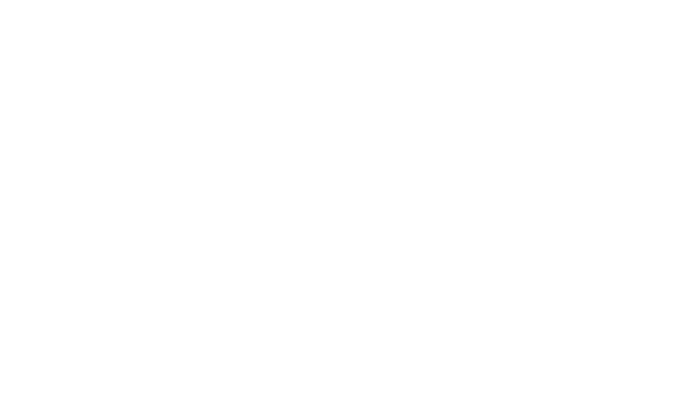安美佳(アンミカ)は、1972年3月25日、韓国の済州島(チェジュとう)生まれで、
「牡羊座のO型です」
3歳のとき、早くに親を亡くして教会が心の拠り所だった父親が、恩人であるドイツ人神父が大阪市生野区の教会に赴任することになったため、その手伝いをするために家族を伴って来日。
すべて年子という5人兄妹の真ん中の次女で、兄、姉、妹、弟がおり、父親は鶴橋の工場に住み込みで働き、家族7人は、工場の段ボール置き場の2階の四畳半で暮らした。
神奈川県川崎市で生まれ、幼い頃に済州島に戻ったという母親は、お肉の代わりにパンの耳で「10円カツサンド」をつくったり、市場で捨てられた果物でスイーツをつくり、一家はスイカの皮で体を洗うなど、つつましい生活。
しかしアンミカは、ひもじい思いをしたことはなかったという。
「お金は全然なかったけど、両親は明るく愛に溢れていて、クリエイティブ。
腐りかけの果物も工夫して美味しいおやつをつくってくれるような親たちでしたから。
小学校に通い始めると我が家は他の家とは全く違うと気づきましたけど、我が家はカトリックだから「清貧は素晴らしい」という考えで、「持たざる者は美しい、他人に与えよ」を実践していることは、むしろ誇りでもありました」
5歳のとき、誤って2階の四畳半から階段を転げ落ち、口の中に大ケガを負って口の周りが黒ずみ、治った後も笑うと唇が大きくめくれ上がる後遺症が残った。
「普通、子どもがニッコリ笑うと、周りの人もつられて笑顔になったりするじゃないですか。
でも友達は私が笑うと逆に怖がったり、沈痛な面持ちをするようになって。
それがショックで、どんどんコンプレックスが高まっていきました。
うちは5人兄弟で、私は3月末生まれということもあり、保育所の中でも小さいほうでした。
成長が他の子より少し遅く、体もポッチャリしていて、そういった体型や顔のケガで思い悩みました」
「姉や妹はかわいいといわれるのに私だけチビでデブでブサイク」
そう思うと人と目を合わせるのが怖く、いつもうつむき、人と話すときは顔をみることができず目だけを相手に向けて
「目つきが悪い」
いわれると、さらに傷つき、イジけてオドオドして、
「目を見て話しなさい」
といわれると恥ずかして泣いてしまった。
そんなコンプレックスの塊だった保育園児のアンミカを、化粧品会社で働き、美容やマナーの勉強をしていた母親は、
「ミカちゃんは手足が長いから、将来モデルさんになれるかもね」
と褒めた。
その言葉は、幼子心に強く響き、アンミカは自然と
「将来モデルになるんだ」
母親は、さらに
「ミカちゃん、顔がいい人だけが美人と違う。
一緒にいて心地が良いな、気持ちが良いなと思える人が、本当の美人なのよ」
といい、
「実行したら絶対に美人になれる」
といって4つのポイント、アンミカいわく「4つの魔法」を教えた。
それは
1 姿勢をよくする
2 口角を上げる
3 相手の目を見て話す
4 人の話をちゃんと聞く
姿勢に関しては、母親は、
「女のコは姿勢が綺麗だと印象が良いよ」
「相手の目を見て話さないと暗い子と思われるけど、目を見ることができなくても姿勢さえよければシャイな子にみえる」
「胸に目があると思って、胸の目で相手をみなさい」
とアドバイス。
口角を上げることに関しては、
「口角を上げると可愛い笑顔になるよ」
「口角を上げて笑顔になりなさい。
自分が笑って笑顔の種をまくと、それがうつって(伝染して」相手も笑顔になるから」
「顔の筋肉は脳に1番近いから、笑顔でいると脳も笑い脳になるのよ」
相手の目を見て話すこと、人の話をちゃんと聞くことに関しては、
「相手の目を見ると感じがいいよ」
「優しい声で話しかけると心地がいいよ」
と教えた。
そしてアンミカの顔や背中を指差しながら、
「姿勢!」
「目線!」
「口角!」
「声!」
と注意。
アンミカは、鏡に向かって笑顔の練習や姿勢のチェックを行うなど、この4つの魔法を何度も練習。
母親に
「上手にできたね、かわいい!」
と褒められると、ますます頑張り、家族以外の大人に
「ミカちゃん、姿勢ががいいな。
顔は不細工やけど」
といわれると
(よしっ、勝った!)
と心の中でガッツポーズ。
コンプレックスは徐々に消え、性格も明るくなり、小学生になると
「めっちゃ明るい子」
になっていた。
「母は、兄妹1人1人の素質を伸ばすことが、とても上手だったと思います。
よく喋る子だった兄には「法律を勉強して弁護士になったらいい」といい、貧乏ゆすりの癖があった姉には、「リズム感が良い」「ドラムをやりなさい」
今考えると無理矢理だなって思いますが、その一言が私たちに小さな自信をつけてくれたんです。
幼い頃に母からもらった言葉は、私の人格形成に凄く影響していると思います」
家が貧しかったため、兄妹全員が保育園の制服であるスモックで登校したり、小学校で給食費を滞納したり、お小遣いが週に20円で兄妹5人分集めないと袋のスナック菓子が買えなかったりしたが、悲壮感はゼロ。
貧乏で手に入らないものがあったが、大きな愛があり、与えられたもので楽しんでやろうという精神もあり、明るく活発はアンミカは、地元の地域のキックベースボールクラブに入り、キャプテンとして男子と対戦。
「ませていたし、気も強かったから、周囲の子を意のままに支配しようとしたことも……。
今思うと可愛くない子でしたね。
クラスでも疎まれた時期もありました」
カレーでもシチューでも、なんにでもキムチをドボドボ入れる父親は、ラーメン屋に社員として就職。
「ウチは大家族だから、住み込みにさせてくれないか」
と頼み、家族7人の住み家は、4畳半から6畳にグレードアップ。
アンミカは学校から帰るとカウンターの上に椅子を上げ、床にモップをかけ、弟の手を引いて鶏ガラを買いに行くこともあった。
そうこうしていると保険の外交員をしている母が帰ってきて、餃子の仕込みを開始。
店に鉄柱があり、それを母が包丁で叩いて
「カンカンカーン」
と鳴ると兄妹は1階に降りてカウンターの端っこでご飯を食べた。
仕事を終えた母がエプロン姿のまま倒れるように横になると、アンミカと姉は、すかさず足を揉み、弟が背中を踏んでマッサージ。
それは母とおしゃべりできる貴重な時間で、競うように学校での出来事を話した。
母親は、朝、仕事に出て、夕方に帰ってくると深夜まで自宅を兼ねたラーメン屋さんで働いていたが、元々体が弱く、アンミカが9歳のときにガンが発覚。
その後、入退院を繰り返した。
「いつも明るくて優しい母でしたが、実は病気がちで気管支が弱く、学校にもあまり行けなかったと聞いています。
膝に水がたまったり、結核で入院したりした時期を経て、30代半ばにガンを発症。
以降は放射線治療を受けていました。
昔は放射線の治療を受けると、その場所にマーキング用の紫のインクが残り、2カ月くらい消えないのです。
母は咽頭ガンだったので首でしたが、ガンの治療中であることが一目瞭然なので、その上から湿布を貼って隠していました。
子どもの目から見ても、本当に働きづめの人生だったと思います。
ガンが見つかってからの母は、時間をつくっては私に編み物の指導をしたり、姉と妹に料理を教えたりするようになりました。
おそらく自分の命が長くないことを察して、娘たちに家事を託そうとしていたのでしょう。
コンプレックスの強い私には、自信を持たせるためか『エチケット入門』という素敵な本の贈り物もしてくれました。
そして性教育まで!
当時は子供にそんなことをいうの?と思っていましたが、母なりに今のうちにすべて伝えておかなくてはと考えていたのかもしれません。
忙しい母と触れ合った時間は、1日のうち、せいぜい1時間ほど。
でもその1時間は、実に密度の濃い時間でした。
こうして母の言葉を振り返る機会をいただくたびに、笑顔でいっぱいだった日々を懐かしく思い出します」
4年生のとき、仲良しだった友達の家に遊びにいくと
「ミカちゃん、韓国人やから一緒に遊んだらアカンってママにいわれた」
といわれ、初めて差別を受け、
「なぜ?」
とわけがわからず、悲しい気持ちになった。
「今でこそ差別は理不尽な行為だと理解できますが、当時の私は、まだ子供。
ただ悲しいだけではない、うまく言葉にできない感情で心がモヤモヤしていました。
折しも家の近所の公園に金木犀の花が咲き、あたりにいい香りが漂っていた季節。
金木犀の香りは大好きですが、今もその香りをかぐとあの日の辛さがよみがえり、胸が締めつけられます」
帰宅後、母親に報告。
すると母親は娘の悲しみを一蹴するように、
「アラッ、みんな知らないんだわ。
韓国はとっても美しくて、ご飯が美味しいところなのにね。
明日学校に行って教えてあげなさい」
と明るく話し、友達のことは一切怒らなかった。
そしてアンミカを膝に乗せ、
「ミカちゃんにそういったお友達を呼んで、美味しい韓国料理をごちそうしましょう」
と提案。
「そうなんや
私は何も悪いことないんや」
翌日、アンミカは、いわれた通り、韓国のいいところを友達に伝えた。
そして後日、理由をつけて
「お食事会をしますので来てください」
と数人の友達を誘い、母親はラーメン、餃子に加え、店では出していないチヂミやプルコギなども出し、終始、笑顔で
「韓国ってすごくいいところなのよ」
「これからもミカちゃんをよろしくね」
友達は大喜びしてくれ、食事会は大成功した。
「もしもそこで母が「なんてひどいことを。今からその子たちの家に抗議に行ってくるわ!」などと逆上したら、私の心に傷が残っただけでなく「韓国人であることはトラブルを招くのだ」という間違った認識を持ってしまったはず。
友達だって、もし母が怒ってクレームをつけていたら、私のことを避けていたかもしれません。
本当に母のあの対応には救われました」
結果、差別や仲間外れは自然消滅していったが、中に1人だけしつこい男の子がいた。
パン屋でその男の子で鉢合わせになったとき、
「韓国人は国に帰れ」
といいながらトングで突いてきたので
「もう、しつこいなあ」
といいながら軽く叩き返すと男の子はよろけて棚にぶつかり、パンが床になだれ落ちた。
「お前のせいや」
男の子が叩き返すとアンミカは棚に頭をブツけて流血。
「スイッチがカチッとオンになりました」
アンミカは、無我夢中で飛びかかり、取っ組み合いのケンカ。
結果、店内は無茶苦茶になった。
「人をボコボコに殴ったのは生れて初めてでした」
知らせを受けてかけつけた父親は、店や相手の子供と親に平謝りし、アンミカを叱りつけた。
(事情も知らないくせに)
アンミカは納得がいかなかったが、ケンカに至った経緯を説明すると父親は
「それやったらしゃーないな。
でもお父さんはパン代を弁証せなアカンねん。
ケンカするなら外でしなさい」
といって笑って、アンミカの背中を叩いた。
アンミカは、
「自分はどうしても守らなければならないを守った」
と後悔することはなかった。