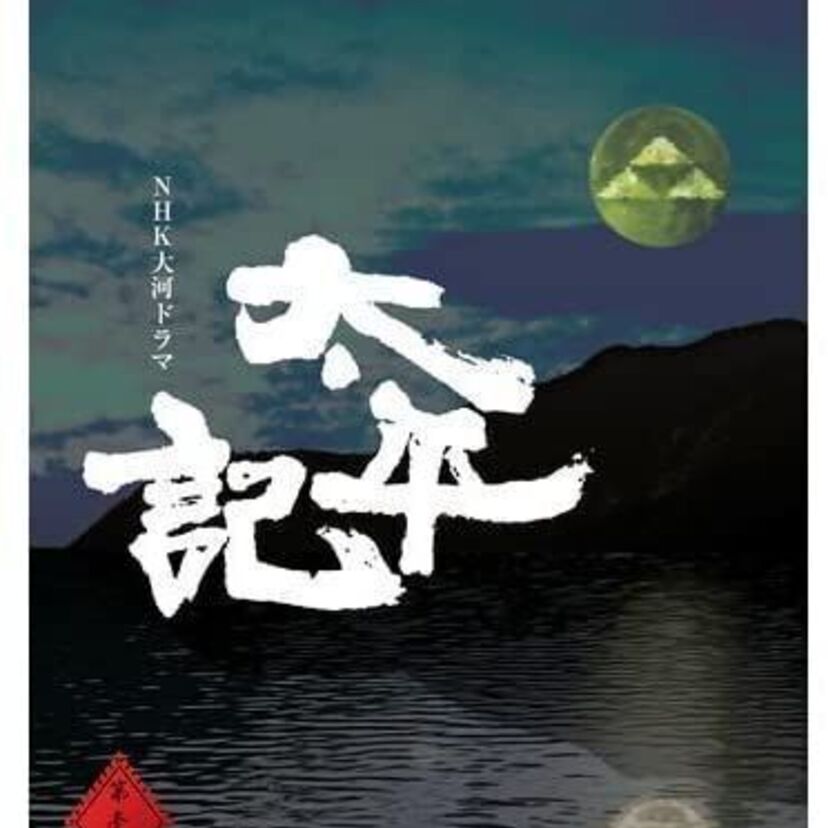「太平記」の放送時期
大河ドラマ「太平記」は1991年に放送された大河ドラマです。前年は「翔が如く」、翌年は「信長 KING OF ZIPANGU」が放送されていました。
112月8日に本編が終了。その後12月22日から4日間にかけて総集編が放送されました。長らく再放送はされていませんでしたが、2020年4月からNHK BSプレミアムにて日曜日の18時から再放送されています。見たい!という方はチェックしてみてくださいね。
原作は吉川英治さんの小説

原作は吉川英治さんの「私本太平記」です。1958年から毎日新聞で連載されていた作品です。全13巻の大作ですよ!
吉川さんの作品は、1965年の「太閤記」、1972年の「新・平家物語」、2003年の「武蔵 MUSASHI」と、2020年現在4作大河ドラマになっています。
脚本は池端俊策さんと仲倉重郎さん。どちらも大河ドラマ初執筆でした。
「太平記」の時代背景

「太平記」は鎌倉時代末期から南北朝時代までを描いた作品です。大河ドラマは戦国時代もしくは幕末を描いた作品が多く、それ以外の時代の作品は珍しいですよね。この時代を描いた大河ドラマは、2020年現在あとにも先にもこれ1本なんです。普段見慣れない時代のドラマなので新鮮な感じがしますよね。
主人公は室町幕府を開いた足利尊氏。足利尊氏が挙兵したところから鎌倉幕府の滅亡、建武の新政、南北朝動乱、室町幕府成立、尊氏の死までを描いています。足利尊氏は明治時代までは悪人だと伝えられてきていました。ですから南北朝時代のことは戦前までタブーだったんですよね。1950年代にこの原作を書いていたというのもすごいのですが、TVドラマにしていいものかどうかという葛藤はあったようです。
テレビドラマは原作とはまた違う展開でオリジナルストーリーが多いです。
南北朝時代を描いた作品ではあるんド絵巣が南北朝時代はあまり長く描かれていません。全49回のうち、鎌倉幕府滅亡までが22回。38回までが建武新政期。南北朝時代は十数回でした。やはりこの時代を長く描くことに抵抗がある人もいたのかもしれませんね。
「太平記」のキャスト
太平記 (NHK大河ドラマ) - Wikipedia
主演の足利尊氏は真田広之さん。その他のキャストも豪華ですよね~。30年近く前の作品なのに今見ても豪華というのはすごいと思います。
真田広之さんが大河ドラマに出演するのは1987年の「独眼竜政宗」以来。4年ぶりの出演ですね。大河ドラマ出演2回目で主役というのはすごいです。
尊氏の父、足利貞氏は緒形拳さん。正室の赤橋登子は沢口靖子さんが演じています。
尊氏の盟友でもあり、ライバルでもある楠木正成は武田鉄矢さん。楠木は忠臣のイメージが強いので武田鉄矢さんは最初オファーを受けるか迷ったそうです。ですが「河内の気のいいおっさん」という設定になっているということを聞いて受けたそうです。
同じ人物の役でも作品によって扱いが違いますからね。自分の持っているイメージと違うと迷うのも納得です。
楠木同様、尊氏の盟友であり宿敵である新田義貞は萩原健一さんでした。ですが真珠腫性中耳炎[4を患って途中降板。その後、根津甚八さんが引き継いでいます。メインキャストが途中降板というのは大変だったでしょうね。
後醍醐天皇は片岡孝夫さんが演じています。
その他チョイ役で豊川悦司さん、常盤貴子さん、大杉錬さんなども出演されているのでぜひチェックしてみてください!
また、このドラマでもう1つ注目してほしいポイントは貴族や公家の言葉遣い。1988年の「武田信玄」から御所言葉を使うことが多かったです。ですが「太平記」では標準後に近い言葉を使っています。これで武士や庶民との違いを表現していたんですね。このドラマは歴代の大河ドラマの中でも貴族や公家の登場人物が多いこともあり、そのような表現をしていたんですね。ですが1998年の「徳川慶喜」ではまた御所言葉が定着してきました。
大河ドラマのあのコーナーは「太平記」がきっかけ!
「太平記」はその後の大河ドラマにも影響を与えているんですよ。
それは番組終了後のミニコーナー。今でも大河ドラマの最後に、その回にまつわる名所、跡地を紹介するコーナーがありますよね。そのコーナーが始まったのはじつは「太平記」からだったんです。「太平記のふるさと」という名前で放送されていました。今では「〇〇紀行」という名前になっていますね。30年近くこのコーナーが継承されているので人気だったんでしょうね。確かに、実際の場所を紹介されると行ってたくなりますもんね。