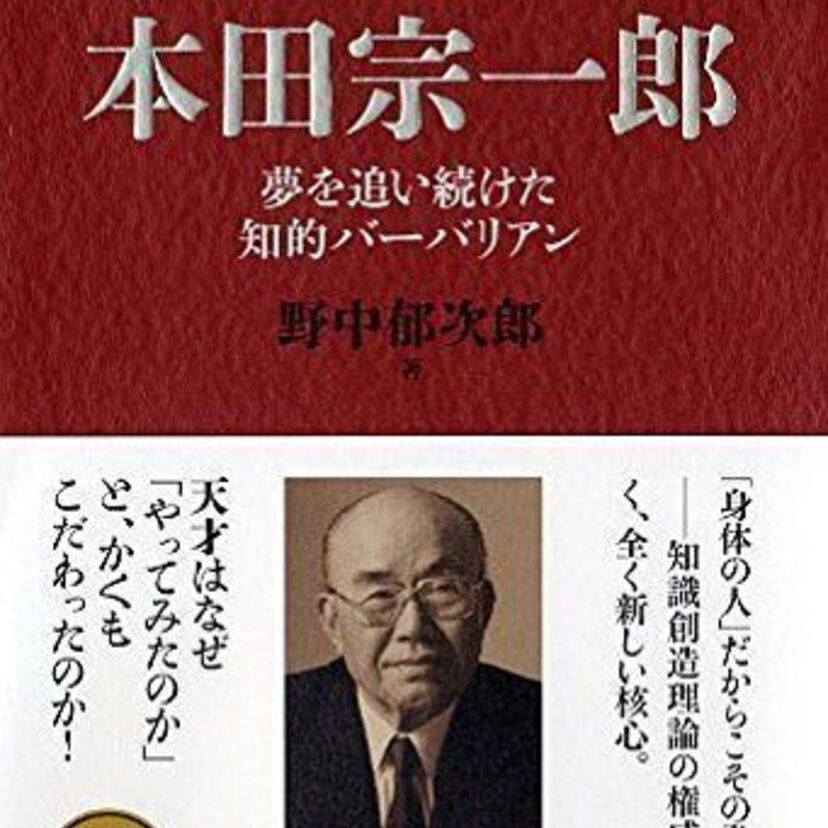The Power of Dreams
夢の力、と訳して良いだろう。
トヨタ、日産、マツダをはじめとして自動車メーカーには理念や個性といったものがつきものである。
ホンダの場合、そういったものを一言で現わすならば《夢》になるのだろう。
もっともホンダを《自動車メーカー》としてくくるかどうかは人によって印象が異なっているだろう。
ホンダは自動車メーカーとしては売上日本3位、一方でバイク、すなわち《二輪車メーカー》としては3位カワサキ、2位ヤマハを大きく離しての日本首位。平成27年から28年までの成績である。
今回は《ホンダ》こと本田技研工業の創設者、本田宗一郎について紹介しよう。
本田宗一郎の幼少期
本田宗一郎は1906年、静岡県の生まれである。
1906年というのがまずすごい。年号に直すと明治39年。
第一次西園寺内閣が成立し日本社会党が結成され、伊藤博文、新渡戸稲造、マハトマ・ガンディー、夏目漱石、島崎藤村といった歴史上の人物たちが現役だった時代である。
身近な題材で言うと夏目漱石「坊っちゃん」と本田宗一郎は同年、ということになる。
特筆――というわけでもないが、教科書にたまに顔をだす小説家坂口安吾も1906年の生まれである。
他にも鈴木真砂女という俳人がいるのだが、これはよほど俳句か文学に親しんでいる人でないとぱっとはしないだろう。

坊つちやん
坊つちやん | 夏目漱石 | 日本の小説・文芸 | Kindleストア | Amazon
鍛冶屋の長男として生まれた本田宗一郎は1913年に尋常小学校に入学。
自動車を見に行ったり飛行機を見に行ったりしていたようであるが、当時の本田の心を強く打ったのはアート・スミスによる曲芸飛行だったようだ。
その後、無事に高等小学校を卒業し現在のアート金属工業に入社。
入社と言っても、こちらも大正時代のことである。
つまるところが丁稚奉公のような扱いで、しばらくの間、仕事と言えば社長の子供のお守りをすることばかりだったという。
独立
最初に本田が店を構えたのが1928年のことである。年号にすると昭和3年。
店を構えたと言っても《ホンダ》が立ち上がったわけではない。丁稚奉公から修行をすること6年、アート商会(アート金属工業の当時の名前)の支店をたてるかたちで独立することを許された――といった具合である。
奉公明けからの独立はよくある流れだが、この、いわゆる暖簾分けを社長から許されたのは当時本田宗一郎ひとりだけだったという。

私の手が語る (講談社文庫)
私の手が語る (講談社文庫) | 本田 宗一郎 |本 | 通販 | Amazon
この頃、後の本田宗一郎を形作っているであろういくつかのポイントが発生している。
まずは《結婚》である。
平成も30年を迎え、学術的にも生活的にも現代性というものが煮詰まってきている昨今、《結婚》について頭を悩ませる人は数多くいる。
これは重大な問題なのだが、当時の結婚というのがいかなるものだったのか、そして本田宗一郎たちにとって結婚というのがいかなる問題だったのか、ざんねんながら手元に資料が無い。
ひとつ想像できることがあるにはある。
当時は食器洗浄機も無ければ全自動洗濯機も無いだろう。家事が著しく大変で、結婚をするとうことはこのあたりの家事に、ひいては生活全般に影響を与ええたということである。
本田宗一郎は愛妻家だったろうか? そうであったとしてもそうでなかったとしても不思議は無いな、というのは不埒な想像かもしれない。理由は後述する。
さて次のポイントに《第1回全国自動車競走大会》の逸話がある。
これについては詳しい人も多いであろう、簡単に引用をしておく。
これは〝らしい〟エピソードであろう。
この時にどちらかがエンジニア、どちらかがドライバーとして活動したというのなら話もわかるのだが、両方きっちり出場しているのが興味深い。

多摩川スピードウェイメインスタンド跡
多摩川スピードウェイ - Wikipedia
さて3つ目のポイント。《浜松高等工業学校の聴講》である。
この背景には自動車修理事業の拡大と東海精機重工業株式会社の社長就任がある。
本田は、ご存知の通りエンジニア色と現場色の強いタイプの経営者である。
そのこだわりは強いものがあり、勲一等瑞宝章親授式への出席で皇居に行くことになった際も作業着――すなわちツナギ行こうとした、という逸話がある。
だがひたすらにひとつの場所に居続けた人物でもなかったようである。
この時はみっちり3年間ほど金属工学の研究に打ち込んだらしい。
なお、余談に近いがここに少々転換期のようなものが発生している。
本田が金属工学の研究にいそしんだのは1937年からの3年間。
研究と言っても実学。アート商会で稼いだ金をどんどん使って実験、研究、開発を進め、特許も増えていった。
さて、転換の原因となった出来事というのは《戦争》である。
1938年には国家総動員法が発令され、1941年には太平洋戦争が始まる。
この時、本田がそれまで行っていたような研究と実験の方法は国が許すか許さないかということを気にしなければならないようになってしまった。
この学問への取り組みが1年早いか遅いかしていれば、本田の《研究》の成果は、そして本田宗一郎という人間が歩む道はがらりと違うものになっていたのだろう。

定本 本田宗一郎伝―飽くなき挑戦 大いなる勇気
定本 本田宗一郎伝―飽くなき挑戦 大いなる勇気 | 中部 博 |本 | 通販 | Amazon
〝人間休業〟とホンダの設立
戦後、本田は荒れていた。
何が原因だっただろう。
戦争での体験か、戦後に荒れた街でなすべきことが無かったのか。
ここで本田は、
らしい。この時期を〝人間休業〟と呼ぶ人もいたそうだ。
戦後というのは大きく3つの時期に分かれている。
ひとつは戦争直後の、いわゆる〝傷跡〟が残る時期。
そしてそれから割合すぐに訪れる、〝復興〟を目指した時期。
最後に訪れるのが戦後という観点から外れるか外れないか、という〝成長〟の時期である。この時期は高度経済成長期ともかぶっていく。
そういう意味だと本田のような男が力を発揮するのは、たしかに〝復興〟以降の話のようにも思える。時代はまだ〝傷跡〟が色濃く残る季節だった。
土や油にまみれることをいとわない男の、その人間性が垣間見れる一局面がどうやらここにもあるようである。
ちなみに、アート商会のほうは社員に譲り、その後設立した東海精機株式会社は売却がなされている。その資金は〝人間休業〟の元手にもなっていたのだが、売却先は《豊田自動織機》。
今のトヨタの本家筋にあたる。