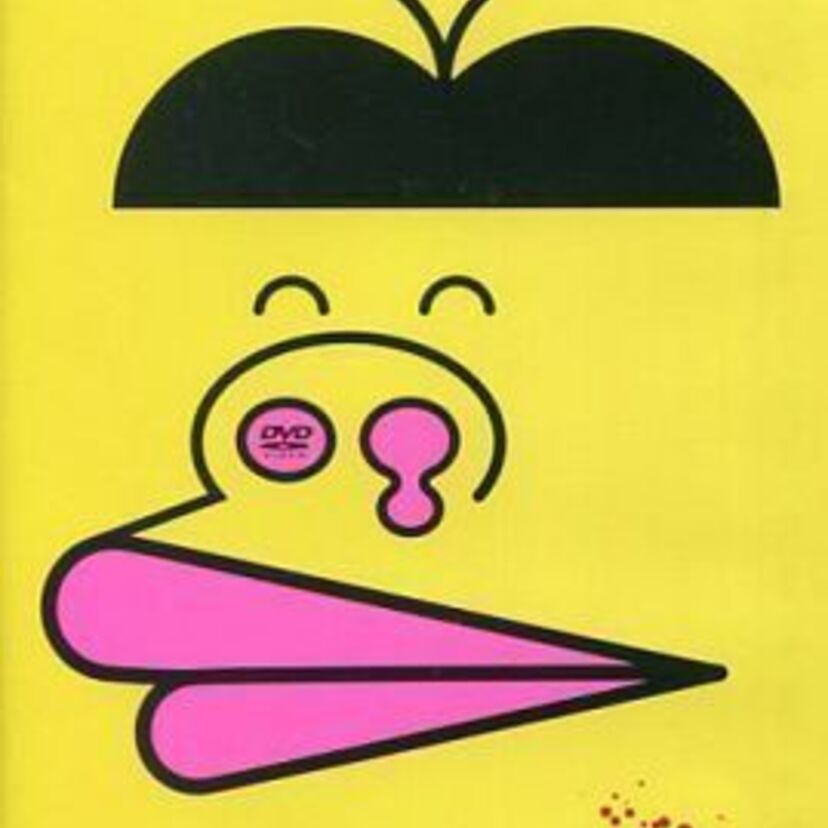谷岡ヤスジ
70年年代に、もしくは80年代に青春時代を過ごした男性であるなら、谷岡ヤスジの名前はしっかりと心に刻まれていることでしょう。
「天才バカボン」や「おそ松くん」などで知られる赤塚不二夫と並ぶ日本のギャグ漫画界の巨匠です。

谷岡ヤスジ
谷岡ヤスジは70年代と80年代に大きなブームを起こしています。
最初のブームのきっかけとなった作品は、週刊誌「少年マガジン」に1970年~1971年に連載された「ヤスジのメッタメタガキ道講座」です。

少年マガジン
【Reader Store】[ヤスジのメッタメタガキ道講座(谷岡ヤスジ) : ソニー・デジタルエンタテインメント・サービス] - ソニーの電子書籍ストア
それまでは無難ともいえるサラリーマン漫画を描いていた谷岡ヤスジでしたが、担当者から「今のままでは売れない」と言われ、そこから作風が変わったとされています。
つまり、谷岡ヤスジは作風を変えることが出来たのです。谷岡ヤスジが天才と称される一端が伺えますね。
もっとも当時の「少年マガジン」は、誌面に新しい風を送り込みたかった。そのために無名だった谷岡ヤスジを少年雑誌の売れっ子作家に仕立て上げる必要があったようです。
ヤスジのメッタメタガキ道講座
それまでの作品とは作風を変えて「ヤスジのメッタメタガキ道講座」は、メジャー誌に掲載されることになりました

ヤスジのメッタメタガキ道講座
普通に考えると、少年誌ですし、メジャー週刊誌の連載ということになると過激な表現は抑えられるのではないかと思います。
「ヤスジのメッタメタガキ道講座」は逆です。編集者の思惑もあったのでしょうが、それまでの谷岡ヤスジ作品よりも激しくなっています。
主人公は子供ですが、刃物が飛び交い、殴る、蹴るの連続です。子供が平気で親や教師を侮辱するという当時としてはかなりの型破りな作品でした。そして、これが大ヒットしたのです。
もっとも、殴ったり蹴ったして血が出るという様をあっけらかん描いてギャグにしています。
つまり、流行語にもなった「鼻血ブー!」です。

鼻血ブー
これはですね、毎回読んでいると、道徳的に教育的にどうこういうよりも、もう、鼻血がでるのが待ち遠しくってしょうがない!といった感じになります。
ストーリーを追うと、たとえば、こんな感じです。

ヤスジのメッタメタガキ道講座
この「鼻血ブー」で青少年の心は鷲掴みにされました。
「ヤスジのメッタメタガキ道講座」にはヒットした要因がもうひとつあります。それは奇想天外なキャラクターである「ムジ鳥」です。

ムジ鳥
「アサー「ヒルー」「ヨルー」とビルの上から時を告げるのがムジ鳥です。他には何もしません。ただ時を告げるだけです。
あ、たまに丸焼きにされたりしていますが、次の週には何事もなかったかのように平然と登場します。
これは、他の登場人物も同様で、谷岡ヤスジの作品の特徴であり、「死」という概念はないかのようです。
登場人物といえば、主人公はざっくりと子供たちです。読み切りとはいえ大胆ですね。
それに、当時は一般的には無名だったにも関わらず作者の名を冠するタイトルをつけるというのも他に例をみませんね。
関連商品
漫画の大ヒットを受けて「ヤスジのメッタメタガキ道講座」は1971年に映画化されています。

谷岡ヤスジのメッタメタガキ道講座